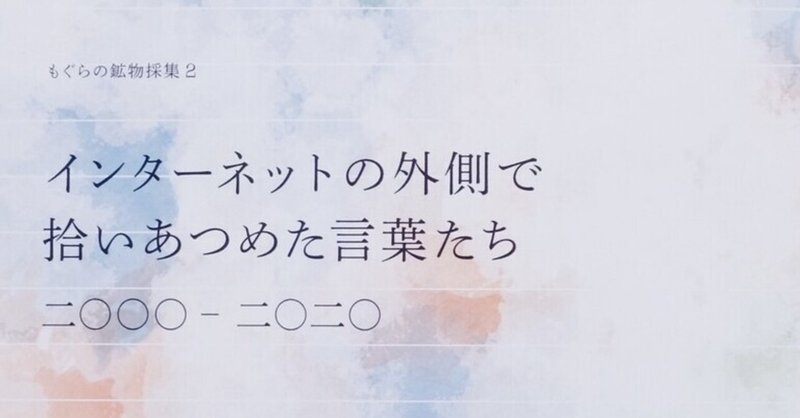
インターネット販売開始します。『もぐらの鉱物採集2 インターネットの外側で拾いあつめた言葉たち 二〇〇〇ー二〇二〇』
こんにちは。もぐら会の有志で制作した「もぐら本2」は、5月16日開催予定の文学フリマ東京にて販売を予定していますが…
このたびインターネットでも予約受付を開始しました!
遠方の方、当日お越しになれない方は、ぜひこちらでお求めください。
★予約受付開始:2021年5月8日
★発送開始:2021年5月下旬予定
もぐら会主宰の紫原明子から、みなさんへ
もぐら会主宰の紫原明子です。もぐら会のメンバーが中心となって作った本、通称“もぐら本”。去年に引き続きなんと2冊目ができました。今日は、この本を私たちが制作するまでの経緯や、その過程についてご紹介します。
*
これまでの記事でもご紹介してきましたが、今回の本のタイトルは『もぐらの鉱物採集2 インターネットの外側で拾いあつめた言葉たち 二〇〇〇ー二〇二〇』です(もぐらの鉱物採集シリーズとして名付けた経緯はこちらをご覧ください)。エッセイ集とした前作に対して、今回はインタビュー集です。この本の制作は、もぐら会メンバーで発起人のエミコさんと、その情熱に動かされた9名によってスタートしました。
そもそももぐら会は「お話会」を主軸とした集まりで、お話会では月に一度、特にテーマを設けず、一人ひとりがその日、話したいことを話していきます。冒頭でも紹介されている通り、語られるのは大抵、その人の極めて私的な話です。基本的に誰かの話したことに質問を投げかけたり、感想や意見を言ったりはせず、みんなが話しっぱなしです。一方で誰かの話を受けて、それを聞いたあとの人の話す内容が静かに変容するということはしばしばあります。お話会というのはそんなふうに、非直接的な形で他者との対話を試みる場でもあります。
この本の前作となるエッセイ集『もぐらの鉱物採集 あの人今、泣こうとしたのかな』では、そんなお話会の模様をそのまま本にするべく、執筆者には、本に収録される順番に応じて執筆の日時を細かく指定し、リレー形式で綴っていきました。またすべてのエッセイを袋とじにすることで、読者の皆さんにも、まずはページを破るという面倒かつ不可逆な行為を体験していただき、誰かの心を覗くことの重みを感じられる仕掛けを作りました。今回これに続く二作目に、何者でもない私たちのインタビュー集として作ってみたい、というエミコさんからの提案を受け、私たちはまず、“なぜそれをもぐら会でやるのか”について、時間をかけて話し合うことになりました。
何者かであろうとなかろうと、一人ひとりの人生には等しく価値があり、その語りはすべて魅力的なものである。そのことを、私たちはお話会を通じてよく知っています。
エミコさんはかつて、「婚活のつもりが浄水器を売りこまれた、あの夏のはなし」というエッセイの中で、コンプレックスを持つ自分、自信のない自分、そんな自分をどうにかしたいともがく自分の内面を明かした上で、次のように綴っています。
“ねえ、商品を売るという目的を隠して、ただのお茶のふりして喫茶店に誘うあなたが持つ「本当の自信」って一体なんですか? それのどのあたりが「本当」なの? 私、後ろめたいと感じる人間の気持ち、捨てたくないんですけど。”
これを読んだもぐら会のメンバーがこんな感想を寄せました。
“普通の人間をなめんな、という気迫が凄い”
普通の人間をなめんなよ、という気迫がすごい。圧倒される。勧誘でつらい思いをしたことある人は、代弁してくれたような気持ちになるだろう。
— 里芋はじめ (@944ikuzak) September 23, 2020
婚活のつもりが浄水器を売りこまれた、あの夏のはなし|結婚がゴールだったエミコ @EMIKOpipipipink #note https://t.co/4TFMaWU1db
成功者たちの自信に満ち溢れた語りでは描き得ないものを、ないものにされてたまるか。エミコさんのこの強い想いは、制作チームのみんながすぐに理解し、賛同するものでした。
問題は「インタビュー」という形式です。通常、直接的な対話の場では、互いに望む、望まないに関わらず、評価や理解、共感などの受け渡しが絶えず行われています。これによって喜びが生まれる場合もあれば、傷つくこともあります。このことは、私たちが誰かと話しをする上で心に重くのしかかります。他者からの反応を予測して言葉を選んだり、反応によって話す内容を変えてしまうこともあります。お話会ではルールによってそれを極力排除し、社会的な自分から切り離した、自分だけの自分を見つけていこうと試みています。これに対してインタビューの場では、聞き手の質問によって語り手の答えが引き出されます。自分と外の世界とに橋がかかり、自分の中にある出来事や感情が、他者の誘導によって形になっていきます。聞き手が少なからず期待の目を向ける中で引き出される言葉が、聞き手によってまとめられ、ある人の人生、ある人の姿として記録されます。そこではどんなに繊細に配慮しようとも、作り手、聞き手の暴力性が介在します。私たちはなぜ、あえてその形でやろうとするのか。ここに答えを持てなければ、もぐら会で誰かの人生のインタビュー集を作るべきではないと思いました。
もちろん、生きている限り私たちは他者と関わらないわけにはいかず、他者からもたらされる、自分では制御できない外的な刺激をすべて暴力性と一括りにすれば、そこから完全に逃れることなどできません。もぐら会でやろうと努めていることは、自分の内側にある不可侵の領域を少しでもたしかなものにすることで、けれどそれを大切に守り続けるためにも、他者と関わって生きることに耐え得るある程度の強靭さを、自分自身で培っていかなくてはなりません。そう考えると、インタビューという形式は約2年間、自己との対話を続けてきた私たちが、次なる課題として取り組むべき新たな試みと言えるかもしれません。とはいえこれはあくまで私たち自身の事情です。ではなぜそれを手間暇かけて本にし、広く届けるのか。そんな議論を続けた先で、この本が今、こうして形となっている背景には、2020年以降、今なお世界が直面しているコロナ禍と、それに伴う新しい生活が私たちにもたらした気付きが、強く影響しています。
2020年、初めて緊急事態宣言が発令され、家に籠る日が続く中で、自分の内側の時間が妙におかしくなっているような気がしました。一日一日が、さながら歪んだゴム板の上を歩くかのように、ぬるっと音もなく過ぎていく。ある人が「毎日夢の中にいるような感覚」と言うのを聞いて、まさにその通りだと感じました。幸い私たちの生活にはインターネットがあって、家にいながらにして誰かの日常を文字で知ることも、映像を見たり、音を聞いて知ることもできました。そこにはたしかに安心があって、それから、感動や、怒りや、恐怖や、喜びといった強い感情を喚起する力もありました。にも関わらず、一向に夢から目覚めることができないのです。
外出自粛期間が明けて、マスク越しにも再び他者と何気なく言葉を交わせるようになったとき、それまで足りなかったものの正体が少しだけわかったような気がしました。それはたとえば、ストッキングに生じる伝線や、長く着たセーターにいつの間にか出てきている毛玉のようなもの。本来は柔らかですべすべとした私たちの心に、知らず知らずのうちに残されていく、小さな他者からの爪痕。他者と空気を共有し、情報と呼ぶには申し訳ないほど些細な、だからこそインターネットには拾い上げられることのない、名前もつかない何かを交換し合う。その際に生じる摩擦によって、私たちの思考や感情のさらに奥にある何かに、小さな無数の傷が生まれる。
傷なんてない方が良いと思っていたけれど、必ずしもそうではないのかもしれないと思いました。他者とのやり取りを通じて、わずかな刺激とともに小さく傷つき続ける。そんな中で私たちは、自分の外側にある世界の輪郭を、さらには自分が生きていることそのものの輪郭を、たしかめようとしていたのかもしれません。またこれがあることによって、私たちがたしかなものにしようと努めてきた自分だけの自分も、健全に守られるのかもしれません。であればこそ、私たちが今作る本は、そんな自分と他者とのやり取りによって生まれる何かを記録したものであるべきだと考えました。
インタビューや編集の指針は、企画チームのエミコさんとイトウさんが、社会学者である岸政彦先生によって2020年7月から実施された、「東京の生活史プロジェクト」に執筆者として参加した経験を生かし、生活史調査の手法を一部取り入れた上で設定してくれました。参加してくれた聞き手は、インタビューの際のすべての会話を一度文字に起こし、一言や一文を聞き手の都合で抜粋して繋げるのではなく、エピソードをブロックごとに連ねていくという形でまとめています。またこの間に語り手は二度、三度、原稿を確認します。話したことが何一つ省かれることなく文字になって戻ってくるという経験は、おそらくすべての語り手にとって初めてのことで、仕上がった原稿を目にし、良くも悪くもさまざまな思いを抱えたのではないかと思います。これに対し企画チームの中からは、取材後の語り手の思いを吐き出せる場を作るべきではないかという意見も出ましたが、複雑な思いを、あくまでも聞き手と語り手の関係性の中で受け止めてもらうということもまた、この本を作る中での価値あるプロセスの一つだと判断し、あえて場を設けるということはしませんでした。
通常、ネットメディアに載る一本の記事は、大半が約3000〜4000字で構成されています。そんな中、この本に掲載されているインタビューは一記事につき約1万字。村上春樹でもない、イチローでもない、何者でもない私たちの人生のインタビューに1万字。そう思うと一見とても多いように感じますが、その実、読み終わってみるとこの分量も、誰かを”知った”と思うには全くもって不十分であることがわかります。読み終わった後にはむしろ、その人のことを何も“知らない”ということがわかった、私はそんな感想を持ちました。これはよく考えれば不思議なことです。なにしろ私たちは日頃ツイッターのたった140文字で、あるいはブログ記事の2000文字、3000文字で、誰かをすっかり知った気になって、好きになったり嫌いになったり、腹を立てて議論したりしているのです。
たとえば喫茶店で、偶然隣り合わせた知らない二人の会話に、本を読むふりをしてひっそりと耳をそばだてている。この本を手に取って読んでくださる方は、もしかするとそんな気分になるかもしれません。名前も知らない誰かが、名前も知らないもう一人の誰かに語って聞かせる人生の話。彼らとこの先、一度も言葉を交わすことはないかもしれないけれど、それでも語り手たちは、この20年と、今この瞬間とを、たしかにあなたと同じ世界で生きています。
ネット上の、大きな揺るぎない声に、わけもなく自分が責められているように感じたとき。自分には何もできることがないと全てを投げ出したくなったとき。そんなときに、よければぜひこの本を読んでみてください。誰一人として思うようには生きていない、大半は、なるようにしかならなかった。そんな人生を生きる彼らは、私たちは、それでも案外、生きているな、と感じられるのではないかと思うんです。
2020年発行のもぐら本はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
