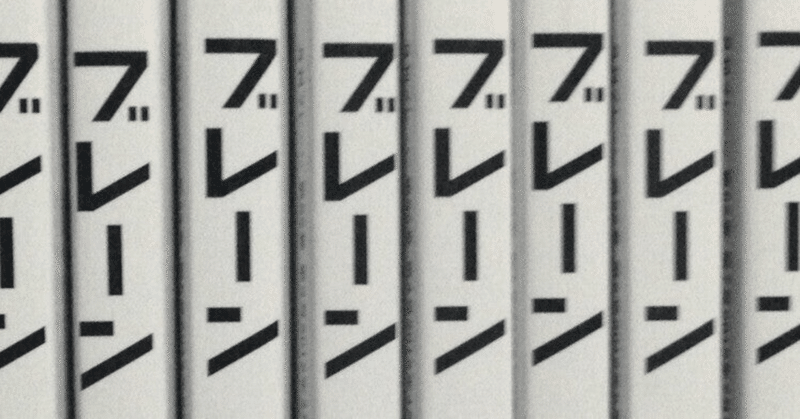
ChatGPTと宣伝会議賞。~AIと公募の交わるところ~
確実に開催されるという情報はまったく得てはいないのだが、あと3か月もすれば宣伝会議賞の時期となる。
去年までと違うのが、ChatGPTの存在である。果たして、この利用に関してどのような判断が下されるのか。
AIに関する事務局の対応については、ざっくり分けるとこんな感じになる。
1.AI全面禁止
2.AI一部利用可
3.AI全面OK
4.言及しない
ほんとにざっくり分けたはいいものの、現実に照らし合わせると様々な問題がありおりはべりいまそかり。特に禁止の方向だと問題が多いと推測される。OKにしてもそれはそれで問題がありそうだが。
禁止した場合の問題点1
「AI使用の有無の証明」
悪魔の証明ではないが、応募はWEB応募である以上、考える過程については調査できない。だから「使いませんでした」と言われればそこでおしまいである。まあだからこれはAIに限らず、例えば人に考えてもらったとか、知り合いのコピーライターに添削してもらったとかだとしても同じだが。あくまで「応募者が考えたもの」という基本線を守っていると判断するしかないので、性善説に立ったルールとなる。ただまあ正直過去作の盗作よりは発覚もしにくい。
禁止した場合の問題点2
「審査員の価値・人間の力の軽視」
「AIの書いた小説だと癖があるので見抜ける」という話が海外SF小説コンテストの主催者から出てたことがあった。ではコピーでも同じような癖があるのだろうか。そしてそれを審査員である一線級のコピーライターが見抜けるのだろうか。
ぶっちゃけ全部は無理だと思う。なにせ「人間がいいと思うパターン」を学習して考えつくのだろうし。禁止しても見分けるのが難しいとなれば、実際それで通過したものが出ると今度は審査員の価値が問われだす、とまったくもってリスキー。
では逆に、OKとした場合はどうだろうか。「全部OK」と「一部OK」を挙げたが、正直たいして差はないというか区別がつかない。句読点だけ調整しましたとなれば「一部使用」で通せるのかとか、またまた基準が難しいことになるので。
許可した場合の問題点1
「模倣・パクリの発生」
AIは、「似たような表現が世に出ていないかどうか」までは調べてこないはずである。もし既にそういうフィルター能力を持っているんだとしたらすみませんというしかないが。ただでさえ通過作と同じで審査から漏れていたものを追加通過としたり、過去の受賞または通過作と同じものが通ったりしているのに、宣伝会議賞の範囲に限らないところから似たようなものをAIが出したとしても、まず審査時点で気づくことはないだろう(超有名コピーをパクった場合除く)。
許可した場合の問題点2
「受賞の価値低下・開催の意義」
最初からAIでの応募を認めていた珍しい例として「星新一賞」というのがある。これはもともとAIというのがSFショートショートの大家でもあった星新一氏の作品にも通じるところがあったので特に違和感はなかった。ただ、企業が知名度を上げたり情報を多く広めるために協賛金を払って、最終的にAIの作品でした、となると恐らく反発が生まれるのではないかと思う。実際にはAIに対して細かい条件提示をしたり修正をしたりといった「指導」が必要と思われるが、実態が分からない層からすると「コンピュータに適当に考えさせてみたような言葉に賞を与えるのか?」という意見が出そうだからである。だったら企業側の人がAI使えばよかったではないか、とかも言われそう。本来はコピーを求める+知名度アップ・周知度アップが狙い、というかどちらかというと後者の比重が高いとは思うが。
ちなみに「言及しない」場合。
AIを使用するなともしてもいいとも言わない。まあ現実的にはこれが一番事務局にとっての負担が少ない。自由判断というか。公募系Youtuberとかがいるのかどうか知らないが、もしいたら「日本最大の公募にAIで大量応募してみた」といった企画にはなりそうである。先に応募作を出せないのがネックにはなるが。
そもそもの話になるが、「いいコピーと感じたのであれば人間が考えたものでもAIが考えたものでも関係ない」という考え方もある。実際、TwitterでAIについて触れた時そういうコメントもいただいた。ただやっぱりまだまだ「人間は人間に感動したい欲」があると感じる。料理に例えると、「この料理めちゃくちゃ美味い!シェフを呼んでくれ!」と言ったら「あ、それインスタントです」と言われた時の気まずさというか。美味しいのは本当だったんだからいいだろ、と切り替えられるかどうかである。
ただ、それっぽい言い回しやワードのチョイスはいくらでも過去例から持ってこれると思うが「発見」がある言葉が出せるかどうか?
いずれにしてもこういう議論ができるのも過渡期だからであって、もうしばらくしたらあらゆる分野で当たり前にAIを使っているかもしれないが…。
まあ色々好き勝手に語ったが、別にこちらに決定権はないので事務局の出方を待つだけである。
サポートいただけた場合、新しい刺激を得るため、様々なインプットに使用させていただきます。その後アウトプットに活かします、たぶん。
