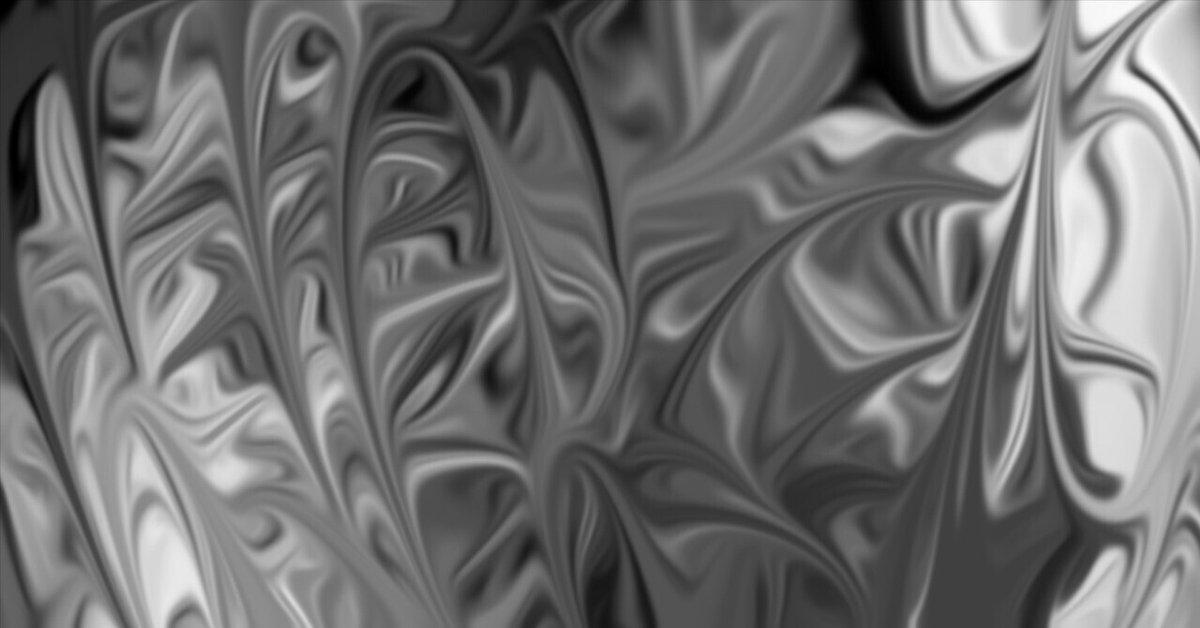
見た夢を小説っぽく書いてみた。
放課後の教室。電気は消されているが、窓からはオレンジ色の光が差し込み、室内を染めていた。
一番うしろの席に座り、ぼんやりと窓の外を見つめている男子生徒がいる。彼の栗色の髪の毛が、夕日を受けてキラキラと光っていた。
教室の後ろのドアから覗き込んだ私は、ここへ来た目的を忘れかける。
彼がとても美しいもののように感じて、しばし見とれてしまう。
ここから彼の表情は見えない。彼は今どんな顔をして、何を考えているのだろうか。しかし、いつまでもこうしているわけにはいかない。
「ゆうたぁー?」
他に人がいない教室に、間延びした私の声がやけによく響く。
前触れもなく声をかけたにもかかわらず、彼は驚きもせずに振り返り、微笑んだ。それはとても柔らかい笑みだった。
彼は物静かな人で、だからと言って決して無口で愛想が悪いというわけではなかった。口数は多くはないが、よく笑う。その笑顔がまた、人懐っこく嫌味がなくて、人好きのする笑顔だった。
友だちも多く、まさにドラマや漫画の世界から飛び出してきたのでは、と思うほどだ。
私たちは学年が違っていたが、そこに何らかの問題が起こることはなかった。互いが互いの教室に顔を出したり、一緒にお昼ご飯を食べたり、一緒に宿題をしたり。
どこにでもいるような恋人同士のようで、とても幸せだった。
私はゆうたと廊下を歩いている。
彼にうしろからハグされながら歩いているというのに、歩きづらさはまったく感じない。すっぽりと収まる感覚が心地良い。ふわふわとして穏やかで、これを『夢心地』というのかもしれない、と思った。
「これ以上太れないなぁ」
「えぇ~? なんでさぁ~?」
おっとりとした口調が頭上から落ちてくる。
「収まれないじゃん」
なんとなくスネた言い方になってしまったけれど、ゆうたは気にすることなく、じゃあ僕はもっと大きくなるよ、と笑って返した。
そんな私たちを、すれ違う他の生徒も先生も、誰も気に留めていない。
確かに存在しているはずなのに、それらはまるでただの背景のようだった。
穏やかで心地が良い日々が続いたある日。
私は昇降口で立ち尽くしていた。
私の靴箱が見つからないのだ。正確に言えば、自分の靴箱がどこなのかがわからない。
自分は何年生の何組なのか。出席番号は何番だったか。普通の学校生活を送っていたはずなのに。
急激に血の気が引いていく。
昇降口には何人もの生徒がいて、皆それぞれが普段通りに過ごしている。朝の挨拶を交わしながら靴を履き替えて、それぞれの教室へ向かう。
私はそんな光景を呆然と見つめるしかできないでいた。隣にはゆうたが居て、どうしたの、という表情でこちらを見ている。
「あ、ちょっと、ちょっと待ってね、」
彼の視線に気付いて焦って応えるものの、どうしたらいいのかわからない。
どうしてだろう。何が起こっているのだろう。
夢なのか現実なのか、それさえも曖昧になっていくみたいだ。
そこへ見知った顔が現れた。山内と田村だ。彼女たちは、私の隣のクラスだったはずだ。
焦る気持ちを抑えて、談笑している彼女たちに近付いていく。そして、なんとか笑顔を作って彼女たちに問う。
「ちょっと、ごめん。あのさ、変なこと聞くんだけど……、山内って何年何組だっけ?」
「あ、おはよう。1年4組だよ~」
明らかにおかしな質問なのに、山内はなんの疑問も持たず答えてくれた。
けれど、その答えは私をさらに戸惑わせた。
1年……? 1年生なわけがない、
だって、ゆうたは『後輩』だから、
私は、2年生以上のはずで、
ゆうたは『後輩』じゃない? ゆうたは誰?
これは、現実なのか——、
「大丈夫?」
心配そうに、ゆうたが身を屈めて私の顔を覗き込んでくる。
なんの疑念も持っていなさそうなまっすぐな瞳に、私はいっそ泣き出しそうになる。
「あ……、私、頭、おかしくなっちゃったのかな?」
涙をこらえて精一杯だけれどぎこちなく笑ってゆうたに訴える。
助けてほしい。
ゆうたなら、なんとかしてくれるかもしれない。いつでも私を穏やかにしてくれるのは、ゆうただった。
ゆうたは何も言わず、いつもと同じように柔らかい笑顔を見せた。その笑顔を見ても、私の心はザワザワと落ち着かない。むしろ静かに静かに、恐怖が襲ってくるようだった。
「あのね、ゆうた、私、今ね……、」
現状を伝えようと口を開くと、震えた声が出た。
「ふふっ、はっ、ははっ」
するとゆうたが声を出して笑い始めた。冗談だよ、とでも言いそうな笑い方だ。ゆうたの笑い声は止まらない。
「えっ? ゆうた、なんで? どうして、」
笑い声はどんどん、どんどん大きくなっていく。
「はははっ! ははっ、はーっはっ!」
彼が、狂ったように笑っている。
彼の笑い声だけが私の耳に届いて、私の周りは一点の光もない真暗な黒に包まれた。
一体、どうしてこんなところにいるんだろう——
私はアジア街のような場所に立っていた。テレビでは見たことがあるような景色。まっすぐに伸びる大通りの両脇には屋台がずらりと並び、その大通りには簡素な机といすが置かれている。大勢の人が食べ歩き、あるいは設置されたいすに座り何人かでお酒を飲み交わしている。とても賑やかだ。
その光景はとても現実味があるのに、どこか別世界のようだった。
……ゆうたを、探さないと。
なぜだかわからないけれど、私はゆうたを追いかけてこの場所にいるのだと思った。
一歩、足を踏み出した途端に、自分がひどく汚れているような感覚に襲われる。見た目が汚い、ということではなく、全身——、身も心も、血管の一本一本まで埃っぽく、すすけているような感覚なのだ。
嫌だ、嫌だ、と無意識のうちに体をさすっていた。しかし、さすった手をみても、なんの汚れもついてはいない。それでも「汚い」という気持ちが消えてはくれない。
まるで寒さをしのぐように、体をさすり続けながら歩く。
そして、彼を見つけた。10メートルほど先に、ゆうたが、居る。それはうしろ姿だけれど、絶対に彼だという確信があった。やっと見つけた彼の姿から、かつての穏やかさは微塵も感じられない。
私はそこから足を進められず、ただじっとそこに立って彼を見た。
彼の前にある机を挟んだ向かい側で、男女がセックスをしていた。彼らの顔はぼんやりとしていて、誰だかはわからない。ただ男女である、ということだけがわかった。こんな場所での行為なんて異常な光景でしかない。それなのに、一人として気にしてはいない。そこだけ異次元のようだ。
相変わらず彼のうしろ姿しか見えないけれど、彼はその女性に執着があるようだった。なぜだかはわからない。
私はなんの思考も持たず、判別もできないほどにぼんやりとした女性の顔に視線を向け続けた。
どれだけの時間そうしていたかわからない。
ゆうたがこちらを振り向いた。振り返った彼は、いつかに見せた人懐っこく柔らかい笑顔のかけらも見せなかった。
口は真一文字にむすばれたままで、表情はぴくりとも動かさない。瞬きさえもしないままで、じっとこちらを見ている。
今まで見たこともないほど冷たく、暗く、残酷な瞳だった。
前に見たすごく後味も気味も悪い夢を、ふと思い立って小説っぽく書いてみました。
一応 "夢の最後" (?)までは見れた気がするし、なんとなくストーリー性もあるようなないような夢で本当、気味悪い夢でした。なので思わず起きてすぐメモしてた。
それを基に、「小説っぽく」なるようには多少の脚色はしてあります。おおむねは見た夢のまま。
夢なので支離滅裂でオチもない。しいていうなら「夢オチ」がオチってことになるかも。
ちなみに「ゆうた」は見たこともない男の子でした。途中で出てきた「山内」と「田村」は本当の同級生。(名前は変えた) もう何年も会ってない。
夢分析とかやったらなにかあるんだろうか……
なんか怖い……!
読んでいただいて、ありがとうございます。
2022.09.30 もげら
よかったら、マシュマロ気軽に投げてください~。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
