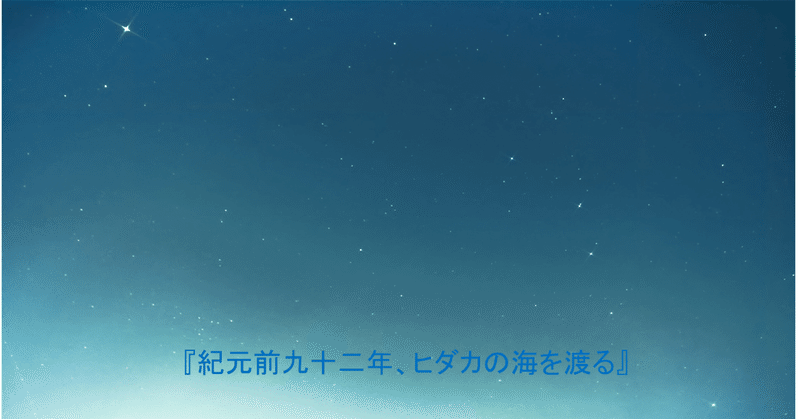
『紀元前九十二年、ヒダカの海を渡る』[027]ナオトの父のオシト
第2章 フヨの入り江のソグド商人
第2節 ヨーゼフ
[027] ■2話 父、オシト
ナオトの父のオシトは、もともと、鳥見山の北麓で伐った舟材を九十九の島があるといわれる象潟の浜まで運んで暮らしを立てていた。同じ樵仕事をする仲間にカケルの父親がいた。
何人もが力を合わせて太綱を引き、倒れる向きを変えながら石の斧と大小の木の楔だけで太い木を伐り倒すのは難しく、誰にでもできるという仕事ではなかった。
手付かずの鳥見山の山裾には太い大きな木が多く、伐った杉の大木の枝を落として山の北を流れる川――いまの奈曽川――に浮かべ、筏に組んで海まで下っていく。雨や雪が多いために水も多く、伐ってしまえば、あとは急な山肌と木の重みでどうにかなる。浜まで運んで行った木は、土地の産物やコメなどと交換する。
象潟の浜の舟作りの親方に頼まれて、常にも増して大きな木を伐り出すときもあった。頼んだ舟主が野代やその奥の十三湊からわざわざ何日も掛けてやって来て、「沢から離れた北向きの木がいい」、「太さはこれくらい」、「できれば二本、似た木が欲しい」とか語り出す。
舟の良し悪しは使う木で決まる。丸木舟にするのに真っすぐで太い大きな木がいいというのはよくわかるので、なんとか望みのものを見つけてやりたいと、帰り路に目印にする岩間の白い花を踏まないようにと気を付けながら、稀にしか入らない山の奥まで入っていく。
それだけ川の流れからは離れるので、運び出すのにいつもの仲間だけでは足らず、他所から来てもらった手伝いと一緒に何日か掛けて、伐った木を水辺まで下すこともあった。
木に掛けた太い麻綱をところどころ岸で曳いて渓流を下り、ようやっと親方の舟寄せに付けると、待ちきれずに訪ねてきていた野代の舟主が一目見て気に入り、払いは吾れが自分で手渡すとばかりに、楽しみにしていたコメを俵一つ余分に渡してくれたりする。
「あのときは疲れが吹っ飛ぶ気持ちがした」
父がそう話してくれたことがある。
「一緒に仕事をするのはみな、力の強い大きな男たちだった」
と、ナオトは母から聞いていた。その中でも父は、背中といい、手のひらといい、ひときわ大きな人に見えたそうだ。自分でも、そうだったかなと思う。それでナオトは、ヨーゼフ老人の問いに、
「はい」
と、短く、間を置かずに答えられた。
「どれほど背が高い?」
ヨーゼフがなおも身振りで熱心に問う。
「そうだなぁ……」
そう呟いて、自分よりも頭一つ大きめに手をかざした。童子の目にはとても大きく見えたのだ。だからそうした。
しかし、自分の背が伸びはじめる前に父は帰らぬ人となり、実際に背比べしたことはないので、いまでは、もう同じぐらいになっているかもしれない。ナオトも背が高く、善知鳥の仲間のうちでは頭一つ抜けている。
黙って見ていたヨーゼフ爺さんは、やっぱりそうかというふうに、会ったときと同じ声を出した。
「アヤーブ!」
どうも、驚いたときに言う言葉らしい。
「そうですね。アヤーブだ」
ナオトが真似て口にし、立ち上がった。
言葉をすぐに覚えて繰り返したナオトに驚いた様子の老人をそのままに、
「うまかった、ありがとう」
と、ヒダカ言葉で言って外に出ようとした。
「どこへ行く?」
ヨーゼフが異人の言葉で訊く。
「そろそろ浜に寝床を探しに行きます」
ヒダカ言葉で答えると、手振りで「ネシャ」とか何とかと言う。
――座れ、ということか。落ち着け、かもしれない……。
ナオトは、好奇心が抑えきれなくなって訊いた。
「ヨーゼフ爺さん、あんたはどこの言葉を話しているんですか?」
第2節3話[028]へ
前の話[026]に戻る
目次とあらすじへ
