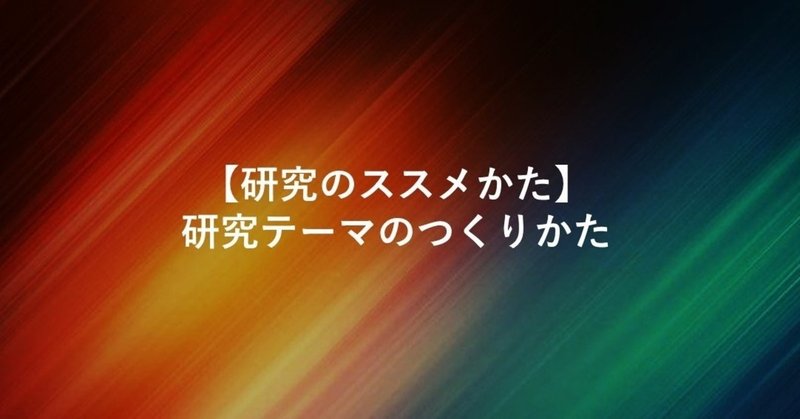
【研究のススメかた】研究テーマのつくりかた
1. 記事の狙いと想定読者層
研究を進めるうえでのTIPSをまとめていくシリーズです。筆者が指導教官を務めるゼミや授業での活用を念頭においています。
読者層としては「大学の学部または大学院で、卒業論文/修士論文研究に取り組む」人たちを想定しています(すでに研究者として独り立ちしている同輩の皆さまや、そのタマゴとしてすでに修士論文研究等は経験済みの博士課程大学院生の方々にも、ご参考になるかもしれません)。
今回は、ズバリ研究テーマをつくるときの考え方(心構え、に近いかも)について書いてみます。
2. 大前提:テーマは変わる(ことが多い)
研究を進めるには、テーマが必要です。
とりあえず研究してみて、そのうち自然とテーマが浮かび上がってくる、ということはありません。先行研究を調べるにせよ、自分の研究の構想を練るにせよ、テーマがなければ何も始められないからです。
ただし、その一方で、「研究を進めていくうちにテーマが変わる」ことは、往々にしてありえます。というか、少なくとも卒業論文や修士論文など、それまでにあなたが「研究」なるものを実施した経験がそれほどない状態で研究活動に取り組む場合には、当初思い描いていた通りのテーマで論文脱稿することは、まずない、と思っていていいと思います。
なぜか。
よくあるのは、先行研究をみていくうちに、当初想定していたテーマに関してじつは多くの研究がなされており、あなたが知りたいと思っていた答えがもうすでに発見されていることが分かっ(てしまっ)た、というケース。知りたいと思っていた答えが見つかったのは素晴らしいことですが、研究とはまだ分かっていないことに対して、何かしらの答えを見出すプロセスです(何が研究「ではないか」については、下記の別記事「警句:『研究』と『勉強』は違います」をご参照ください)ので、既知の事柄を改めてまとめても研究としての価値はゼロです。
(ちなみに、この「自分が知りたいと思っていた答えが、先行研究でもうすでに明らかにされていた」場合に、それでもテーマを変えずに進めようとすると、よくて指導教官からストップがかかり、万一そのまま論文を書き上げるところまで行ってしまったりすると、99.999%口頭試問のときに「これって、ABC & DEF (1987) の論文で言われているのとどこが違うの?」とツッコまれて轟沈します。「なんとかバレずに通せるのでは」などと、プロの研究者をナメてはいけません。)
より前向きなパターンとしては、先行研究を読み、構想をブラッシュアップするなかで、当初思い描いていたものよりももっと好奇心をそそる、面白そうなテーマを思いつく、という場合もあります。あるいは、ゼミなどであれば、研究についてゼミ内で進捗報告をした際にゼミ仲間や指導教官からフィードバックを受けて方向を修正することにした、ということもあるでしょう。
いずれにせよ、「今思い描いているテーマは私の人生を賭けた唯一絶対のものだ、ここから一寸たりとも退きはせぬ!」と思い込むのはドツボにハマる可能性が極大です。退く必要はありませんが、方向性を修正(ピボット)することは当然の想定内としておくようにしましょう。
3. 研究テーマは「CAN×WANT×NEEDEDの掛け算」で絞り込む
「研究テーマは変わりうる」ということを前提にしたうえで、ではどうやってテーマを絞り込んでいったらいいのか。
良い研究テーマを自動的に生成するアルゴリズムはありません(あればプロの研究者はみんなそれを使っています)が、少なくとも「これは筋が悪い」というテーマをあぶりだすためのアプローチはいくつか存在します。
そのなかで、僕個人は「CAN(やれる)」×「NEEDED(やるべき)」×「WANT(やりたい)」という三つの要素の掛け合わせ(下図参照)でスクリーニングするのが、特に卒論修論研究では有効だと思います。

- CAN(やれる):
卒業または修了がかかっている卒業論文や修士論文研究では、定められた期限内に研究を完了させられることが絶対要件です。
ちなみに、論文を書き上げるまでに必要なステップとしては、関連する主な先行研究をまとめて(※)→ 仮説を導出し → それを検証するためのアンケート調査や実験などのリサーチをデザインして → 実際にデータを集めて → 分析し → その結果を考察して → 論文にまとめあげる
…だけでは終わらず(←ココ、激しく重要ですのでご留意ください)、
そこで書き上げた第一稿に指導教官からフィードバックを受けて書き直し(場合によってはデータの再分析、あるいは最悪データのとり直し)をすることになりますので、そこまで見込んだうえでの「完了させられる」とご理解ください。
※ 先行研究のレビューのやりかたについては、別noteをまとめましたので、合わせてご参照ください。
ですので、たとえば、「AIが人類に与える影響とは」といった非常に大きなテーマは、(プロの研究者が、自分の生涯にわたる業績を方向づけるうえでは有用な羅針盤となりますが)長くても1年、多くの場合は数ヶ月で着想から脱稿まで持っていかなければならない卒業論文や修士論文研究では不適当です。卒論/修論の研究テーマはできる限りシンプルに、的を絞りに絞ってフォーカスしましょう。
- NEEDED(やるべき):
研究とは、「巨人の肩の上」に登り、先人の目が届かなかった遠くを見通す行為です。
先行研究に目を通すと、そこでは必ず(Limitations & Future Directionsといった項に)「今回の研究でここまでは分かった。ここから先は今後さらなる検証が必要だ」と注記されています。こうした先人の示唆から、どのような研究が必要とされているかを明らかにすることができます。
ただし、先行研究で未検証だからといって、それが「やるべき」テーマとなるわけではないことには、くれぐれもご留意ください。
先行研究をレビューしたうえで「これこれのポイントについて詳しく検証した研究はまだない。なので、本研究はこのポイントを検証する」といったロジックで研究の意義を打ち立てようとすることは、卒論/修論研究に限らず、プロの論文でもまれに見受けられます(個人的には、これを“X hasn't been done” fallacyと呼んでいます)。
しかし、「先行研究で検証されていない」テーマというのは、もしかしたら「研究するまでもない」から検証されていない、という可能性もあるわけです。
したがって、「この点は先行研究において未検証である」というのは、研究テーマを設定するうえでの必要条件ではあっても、それだけで十分なものとはなりません(ここは「研究の意義」に関わる重要なポイントなので、後日改めて別記事にまとめようと思います)。
- WANT(やりたい):
さらに、いくら「やれる」「やるべき」であっても、あなた自身がそれを「やりたい」と思えるテーマでなければ、研究する意味がありません。
特に卒業論文・修士論文研究というのは、学部あるいは修士課程の集大成となる大きなプロジェクトであり、あなたの時間とエネルギーを大いに費やすことになります。したがって、「この問いに対する答えをぜひ知りたい」「この研究が(指導教官を含む)第三者からどう評価されるかは別にして、この問題に精一杯取り組めれば、少なくとも自分としては納得がいく」と思えるテーマを設定すべきでしょう。
研究は、長く、暗い森の中を手探りで行きつ戻りつしながら進む、孤独なプロセスです(だからこそゼミ仲間との支え合いや指導教官をはじめとする教員とのコミュニケーションが重要になります)。先が見えない、このまま進んでもどこにもたどりつけないんじゃないか、自分は間違った方向に歩いていっているんでは、といった思いに駆られることは想定の範囲内と思っておいてください(でも、自分から投げ出したり、先送りしたりしない限りは必ず終わるもの、でもあります。あなたの先輩たちも皆、上記のような思いに駆られ、それでも論文を書き上げたことを忘れないように!)。
そんなとき、「なんで自分はこの研究に取り組んでるんだっけ」「そうだ、自分はこの問いに対する答えを探していたんだった」と立ち戻ることができるテーマを設定しておくことは、この上なく重要です。
4. 研究テーマづくりと先行研究レビューは表裏一体
以上、研究テーマを絞り込むうえでの「三要素の掛け合わせアプローチ」についてご説明しました。
ただし、研究テーマのつくりこみは、あなたのアタマの中だけで完結するプロセス、ではありません。
三要素の中にも「NEEDED(やるべき)」が含まれているように、先行研究で何が分かっていて、何は未検証なのか、言い換えると「人類の知の限界=フロンティアはどこか」を見極めないことには、良い研究テーマはつくりようがありません。
ここは、鶏と卵の関係に似た構造があります。
まずは自分の興味関心が出発点です。これがハッキリしないと、先行研究を読もうにもどこから手をつけていいか定めようがありません。
しかし、一旦先行研究を読み始めると、そこで見つかる研究成果によって、あなたの問題意識は多かれ少なかれ確実に影響を受けていきます。上述の通り、ときにはもともと探していた答えがほぼそのままの形ですでに論文になっているためにテーマの修正せざるをえないこともあるでしょう。
したがって、先行研究レビューを進めることで、あなたの研究テーマはどんどん進化していきます。
すると今度は、新たにバージョンアップしたテーマに即して、あなたが目を通す先行研究の種類も変わっていくはずです。
そして、その結果またテーマが進化して…と、研究テーマづくりと先行研究レビューは相互に影響し合う表裏一体のプロセスです。一人の研究者としてのあなたと、あなたが興味関心を覚える問題の解明になにかしらの形で携わってきた無数の先達との、論文を介した対話であるとも言えます。
このため、研究テーマづくりは、ときに果てしない旅路であるように感じられます。「もうこのテーマ ”で” いいや」と妥協したくなることもあります。
でも、辛抱強く続けていくと、必ずどこかでテーマとレビューの往還は収束します。「対話」のメタファーで言うと、あるとき関連分野の先輩研究者たちから「このテーマについてはあなたに託した。よろしく頼む」と言われたように感じる瞬間が訪れる、ということです。
そこまでテーマをつくりこむことができれば、その後の研究がすごく楽になります。自分がやるべきことがクリアに見えている状態になるので、あとはそれをできる限り信頼性と妥当性を担保する形で検証するだけ、だからです(もちろん、「できる限り信頼性と妥当性を担保する」ことも決して簡単ではないのですが、それには確立された科学的方法論が使えます。方法論については、別途記事をまとめていきます)。
5. まとめ
研究をススメるためには、テーマが必要です。関連する先行研究のレビューを進めていくうちにテーマはほぼ間違いなく修正されていきますが、それを乗り越えるとどこかで必ず収束します。当初のテーマからピボットすることを前提に、「CAN(期限内に完了させられる)」「NEEDED(先行研究に鑑みて、検証する意義がある)」そして「WANT(他ならぬ自分自身が取り組みたいと思える)」の三つの観点から絞り込んでいって、貴重なあなたの人生を捧げるに足る研究テーマをつくりあげていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
