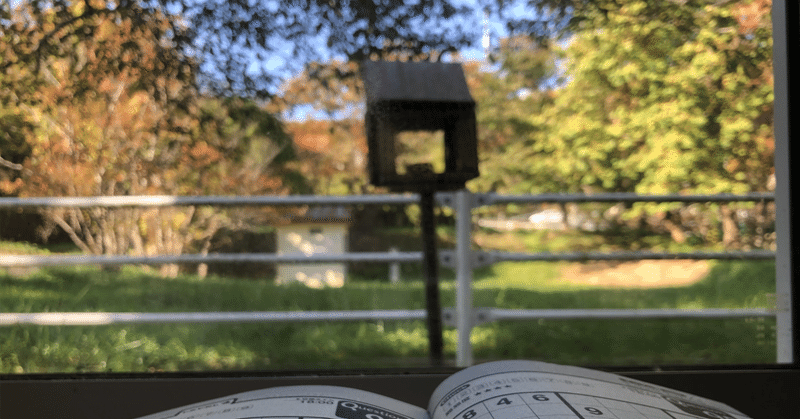
応援したくなる理由 book review
『その魔球に、まだ名はない』
エレン・クレイジス・著
橋本 恵・訳
あすなろ書房
この本を読んだ直後、朝日新聞の朝刊に、女子プロ野球の記事が二回掲載された。一つは七色の変化球を持つ投手の記事。もう一つはプロ引退後の選手が、社会人チームに入り、コーチ兼、選手として再びグランドに戻った記事。そして、近く映画『プリティ・リーグ』がテレビで放送される。これは、偶然ではなく、必然だと思わずにはいられない。
物語の舞台は、1950年代後半のアメリカ西部、サンフランシスコ。もうすぐ10歳になるケイティは、誰も打てない魔球、スーパー・ナックルを操る剛腕投手だ。
夏休みも終わりに近づいた午後、ケイティは近所の空き地で仲間たちと野球をしていた。それを見ていたリトルリーグのコーチに、投球を見込まれ、トライアウトに誘われる。
後日、相棒のキャッチャー、ピーウィーと一緒に、トライアウトを受け、ともに合格。最初の練習試合では先発投手も任された。晴れてリトルリーグの選手だ!と、喜んだのも束の間、女子選手はルールで対象外。コーチは当初ケイティを男子だと思っていた。ルールを破ったら、リトルリーグの認可を取り消されかねない。ケイティの剛腕を認めながらも、なす術がない。
「納得できない!合格したのに!」。その日からケイティの長い旅は始まった。でも、その旅は孤独ではなかった。彼女には理解者が沢山いたし、以前と変わることなく、草野球をする仲間もいる。
特にケイティのママは、自分の信念を貫いた人だ。大学に解雇され、裁判に勝訴するまでの時間を耐えた。そして、大学教授に復帰した今も、不等な扱いを受けている。それでも、三人の娘には、何があろうと、正しいと思うことをして欲しいと願っている。
私は泣いてしまった。ことは違っても、自身の選択に重なることが多すぎて、他人事だと思えない。自分自身に正直でありたいと、私は何時も思っていた。それがマイノリティに属すると気づいたのは、何時だっただろう…。その生きづらさと孤独。世間、他者へ募る不信。誰も何も信じられない。子どもの頃からそんな時を、何度越えてきただろう。それは今も、多分これからも変わらない。
ルールと言われても、ケイティはあきらめなかった。弁護士のアドバイスを受け、リトルリーグの本部に手紙を書く。トライアウトの結果を示し、レギュラー選手として試用期間をあたえて欲しいと訴えた。返事はノーだ。でも、ここで引き下がるわけにはいかない。
親友のジュールズも彼女の味方だった。リトルリーグの返信は、ナンセンスのオンパレードで、野球が男子専用で、野球史上、ケイティ以外に女子選手がいないなんて、ありえないと。このことがきっかけで、女子野球の歴史が浮かびあがる。実在した選手たちは、意外にもケイティの近くにいた。
この物語は、公民権、人種・男女差別と、いくつもの要素を含んでいる。日本は現代でさえ、もっと遅れている。それで良しとする人たちが、多すぎるのだ。
私はケイティを取り巻くすべての人たちと、握手したい気分だった。図書館の司書にはありがとう!と言いたかった。それこそが仕事だと、思うから。
そして、ケイティの相棒ピーウィー。彼は誰よりもケイティの投球を知っている。タイヤの穴に向かって投げていた彼女を見たときから、ずっとフェアだった。
同人誌『季節風』掲載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
