
サブカル大蔵経999三木成夫『胎児の世界』(中公新書)
999冊目に紹介しようと思っていた本に、ようやくたどり着きました。
本書は、読み返すたびに驚きと緊張と発見がある、捨てページの一切ない狂気と幻想のオールタイムベスト新書です。
マッドな科学者か、真実の探求者なのか。医学と仏教の融合、西洋と東洋の因縁、科学と情緒の相克、フィロソフィー心技体、それを後押しする本能。
まなざし、おもかげ、懐かしさ、記憶。
これらは、どこから来ているのか。
自身の生命の進化の旅が始まります。
もちろん、このような論議のすべてを超えて、やはり人間社会には「見てはならぬもの」があろう。母胎の世界はその最も厳粛なものの1つである。そこに展開される光景がどんなものであろうとも、やはりそれは、永遠の神秘のかなたにそっとしまっておくというのが、世の東西を超えた人情の常ではなかろうか…。
本書ではしかし、この最後の垣根も乗り越えられる。この動向を冷静に分析すれば、そこには「教育」という、一見、大義名分の隠れ蓑をまとう、ほとんど狂気に近い実証の精神が妖しい光を放っているその奥深くで「生命記憶」の太古の世界を目指す"遡行本能"が滔々と渦を巻く。
この本能の命を受けて、その実証の刃が一閃したのであろう。p.222-223
「見てはならぬもの」「垣根を乗り越えられる」。読者との共犯関係が結ばれようとしています。
以上、書評的な俯瞰を許さない迫力が、本書に通底しています。いにしえの新書の誇りの高さが許されていた時代の最高峰ではないでしょうか。
…おれたちの祖先は、見よ!このとおり鰓を持った魚だったのだ…と、胎児は、みずからのからだを張って、そのまぎれもない事実を、人びとに訴えようとしているかのようだ。読者は、どうかこの迫真の無言劇を目をそらないでご覧になってほしい。p.109
見てはいけないけど、
目をそらさないでほしい。
本当はあまりたくさんの文章を引用してはいけないと思います。しかし、この文章を世に知らしめるためだけに、私はここまでこの連載を課して続けていました。
引用させていただきます。
事は、二番目の男の子が生まれて間もない赤ん坊のときに起こった。それは、親から受けた免疫抗体が切れる、そんなある日、突如として高熱を発し、まるっきり乳を飲まなくなるというところから始まったのである。当然、母親の乳房はおそろしい形相に怒張し、搾乳器もこわがって作動しなくなる。やむなく友人の小児科医に相談すると、それは亭主が吸うのだという。
「なに?」こちらの肉体は、もちろん、そういうことは拒絶する。考えてもみるがいい。哺乳動物の雄が授乳期の雌のからだに近寄り、しかもその哺乳のあいだに割って入る、などという光景があるだろうか。母性はしかし、まことに広大無辺だ。そういった男性の思惑など、まるでひと飲みだ。あの深海性鮟鱇の矮雄の運命か。
「吸え!」それはだから、もはや至上命令に等しかったのである。
奥さんの乳を吸う医学者。
さきごろ、テレビのフランス映画で、主人公がピカピカのギロチンに掛けられるところがあった。そのまえに、真新しいワイシャツの白い襟が大きな裁断鋏で襟ぐりに沿ってジョキジョキと切られていくシーンが出てくる。それが、どういうわけか、いまだに当時の情景と重なり合う。それは、わたくしの人生における、あるいは最も生命的な出来事の一つではなかったかと思っている。
ここで終わればエッセイなのですが、まだ終わりません。
この内なる動乱は、しかし、その液体がこちらにやって来た瞬間に、完全に消しとんでしまう。それは一瞬の転換だった。かすかに体温より低いものが口の中にスーッと流れ込んでくる。そこには、予想していた味もなければ匂いもない。それでいて、からだの原形質に溶け込んでいくような不思議な感触がある。いったい、どうしてこんな液体がこの世に存在するのか……。
次の瞬間、ふたたび意識はもどる。あとから思えば、まるで獣のような素速さで身をひるがえし、ステンレスの流しの上に大量の唾液とともに、何かいのちを惜しむように静かにそれを流し出す。飲んではいけない。けっして飲んではいけない。おのれの一部のような液体でありながら、絶対にそれを受け付けようとしない自分がそこにあるのを、そのとき、はっきりと意識した。この肉体は、寸刻の妥協もそこでは許さなかったのである。生命の流れを逆行させることは、いいかえれば、おのれのいのちを見すてることに等しいのだから…。
(以上p.30-32)
三木成夫さんのことを調べると、たくさんの方がその伝説と影響を語っていました。
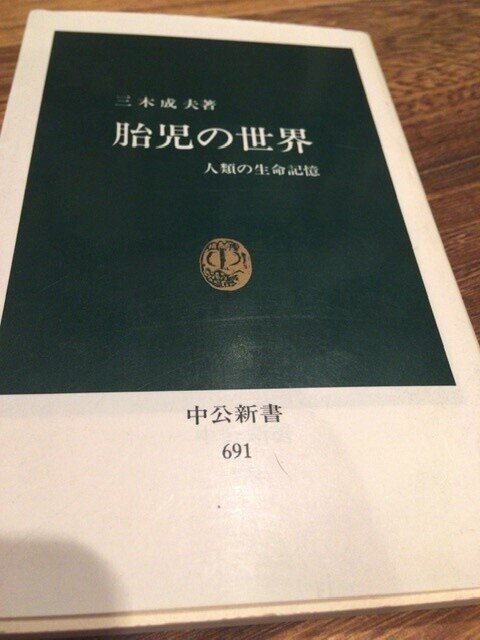
釈尊の築き上げた五重の機能ー「色」「受」「想」「行」「識」の第三番「想」の現われにそれはほかならない。ちなみに、「想」の言語のsam-jñāは、samすなわち「シンクロナイズ」のsyn(一致)とjñāすなわちknow(知得)の合成語であると言う。p.16
こころをたどっていくと、まさかのサンスクリット解釈から始まります。
マ行の音「マ・ミ・ム・メ・モ」は、一般に「唇音labial」とよばれる。唇なしには出てこないからだ。したがってこれは、哺乳動物の象徴音ということにもなる。ネコの「ミャー」、ヒツジの「メエー」、ウシの「モォー」とともに、人間の赤ん坊の原始の音声が「ンマンマ」であることは万国共通であろう。唇をもたぬ爬虫類では、だから、この唇音にかわるものとして、「口蓋音gutteral」のカ行「カ・キ・ク・ケ・コ」が出てくる。もし中生代の恐竜の発したであろう音声を再現するとなれば、このカ行の音を考えなければならないであろう。今日の鳥たちの啼き声を聞くがいい。かれらは「栄光ある爬虫類」とよばれているのであるから。もちろん哺乳類にも、この口蓋音は、たとえば断末魔の絶叫においてその本性を現すだろう。/一方、この「マ」音は、所有代名詞(ma,my…)の意味にも発展する。それは、私有の「私」/いいかえれば"おのれ"の姿にまで通じていく。そして最後に、この「マ」音は、古代インドの√māすなわちmeasure(測る)に示されるように、欲求の強さを測るという意味にまで引き伸ばされていく。あの「マナ識」のmanasすなわちmindは、ここから出てきたという。
こうして見てくると、この「マ」音の意味の進展をとおして、そこに一つの関係が浮き彫りにされてくるのではなかろうか。それは、生物の根源の欲求の一つである「食」の世界を舞台として展開された食物と自分の分極、そしてその両者を距てる一つの「間」と言う構造形態であろう。p.37-38
「マー」から始まる太古の言語学。
とにかくこの本で、自分が哺乳類ということを意識させられました。
明治の初め、西洋医学が正統のものとして時の政府からお墨付きをもらったのも、あの天然痘に対処する種痘所の苦心の設立と、そして無虜数十万の生命を奪ったコレラの防疫対策の成果だったと聞く。そこでは「細菌感染と発病」そして「細菌撲滅と治療」という、万人の認めずにはいられない"因果"の図式が否応なしに錦の御旗と化して、伝統の東洋医学はしだいにしだいに民間の片すみに押しやられてしまったのであろう。いうなれば、問題の黒船が新型バイキンを専用の疫学と抱き合わせにこの国に持ち込んだのであろう。歴史の必然に裏打ちされた、これが西洋医学渡来の経緯と思われる。
それでは、東洋医学とはいったい何か。
それは一言でいえば、細菌と共存する世界のようだ。
そこでは、だから、つねにそれが可能な体質が問題となる。しかしこの場合にも、たとえば「抵抗力」といったことばは出てこない。それは「予防」とか「殲滅」などともいうように、あくまでも細菌を"敵性国家"と見なす人間の精神から出たもので、こうした意志的発想は、本来の東洋医学の世界では育たない。この平和を愛する国柄は、いってみれば、純白のシーツによって撤去されようとしている。あの農村の土間の奥に藁を敷いた"万年床"の世界に、ものの見事に象徴される。「衛生」とは似て非なる、それは真の「養生」の世界というものか…。p.51
昨年読み返した時、現代を予言しているような文章だと思いました。
当然、哺乳類のウサギの注入にとりかかっていなければならなかった。それは妊娠した母ウサギを材料とする。その子宮をたち割って、なかから胎児を取り出すのである。しかしもう、それに進む必然性は、そのときの自分にはなかった。わが家には新しい生命が女房のお腹のなかに宿っていたのである。おのれの天職とまで思った注入の世界が確実に遠のいていくさまをジッと見つめている自分の姿がそこにあった。p.102
実験と家族のはざま。
しかし祖先物語は、ときに白昼に、壮大なショウとして現れることがある。ひとむかしまえ、武道館の檜舞台で「世界の格闘技」と銘打って行われた世紀のイヴェントがそれだ。決着を待ち望んで裏切られた、おそらく世界数億の観衆のこころには、しかし、それでもなお、得体の知れない興奮の燻りが長く尾を引いて残ったはずだ。その勝負の意味するものは、じつはゴング直後の一緒に炸裂していた。一方の横倒し・足蹴りを、他方がひらりとかわす。爬虫類と哺乳類の、それは宿命の対決だったのだ。アマゾンのワニの尻尾の一撃。密林の王者の誇らかなドラミング。そこには、アルプス造山運動を背景に1億年の興亡を賭けた両者のドラマが一つの"所作事"として、夢のごとくに再現されていたのである。p.144-145
まさかの〈猪木ーアリ戦〉の実況中継!
猪木がワニで、アリがゴリラ!
相原コージ先生の作品を彷彿とさせる。
これはボーナストラック過ぎます!
この記事が参加している募集
本を買って読みます。
