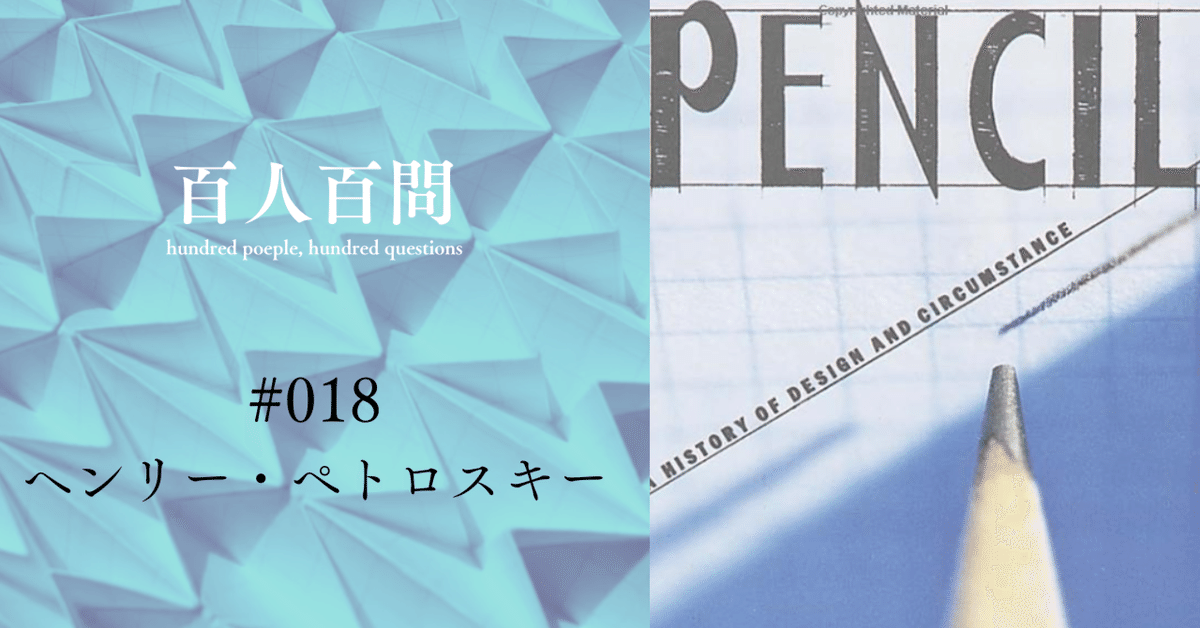
道具はどう進化するのか?―ヘンリー・ペトロスキー【百人百問#018】
初代iPhone登場の驚きは、そこに大きなボタンが一つしかなかったことだった。しかもそれは大きくて凹んでいた。それはなぜか?
日本のガラケーはボタンがたくさんあり、BlackBerryもキーボードが付属していた。しかし、iPhoneはタッチスクリーンを採用したことで、スクリーンが大きくなり、物理ボタンを最小限まで減らすことができた。
正面にはボタンを1個にしたことで、ボタン自体を大きくすることができ、大きいことで凹ませることができた。それによって誤ってボタンを押してしまうことを防いだ。さらに、タッチスクリーンの技術を向上させたことで、もはやボタンを無くすというiPhone Xまで進化した。
ドナルド・ノーマン(#002)は初代iPhoneを見て、「そこまで驚かなかった」と言っている。それは「既存の技術をうまくまとめた、Apple社の典型的な製品」だと付け加えている。「指でなぞって画面が流れるように動く」だけだったというが、それがユーザー体験を変化させた。
最初はボタンに依存していたユーザーも、次第にボタン無しのインターフェイスに慣れ、それが当たり前になっていった。道具は身体に合わせて進化し、身体もまた道具に合わせて進化する。
これは共進化とも言えるもので、人と機械がともに共依存しながら進化している。人類は石器で栗を割っていた時代から、「手のひら」のサイズのものを生み出し続けた。たいまつも、槍も、銃も、マグカップも、リモコンも、そしてスマホも「手のひら」とともに歩んできたのだ。
アメリカの建築家であるルイス・サリヴァンは「形態は機能に従う(Form ever follows function)」という言葉を残し、デザイン機能主義の合言葉になっている。銃もスマホも機能に従った結果だろう。
しかしながら、なぜこの形になっているのか、というのは思いどおりの「機能」だけに依存しているわけではない。そう主張したのが、工学者のヘンリー・ペトロスキーである。彼は、「形は"失敗"に従う」と主張した。それはどういう意味なのかを今日は探ってみたい。
ペトロスキーに『フォークの歯はなぜ四本になったか』という本がある。タイトルから好奇心を喚起させる問いになっている。まずはこのフォークの進化を追いかけてみたい。
フォークのルーツはナイフであり、ナイフのルーツは黒曜石やフリントと呼ばれる堆積岩の破片である。手のひらの石器からどのようにフォークになったのだろうか。
黒曜石は手で握り、鋭利な切れ味で肉や魚を切ることができる。しかし、火を使うようになると、切ったものをそのまま火にかけることができない。そのため、木の枝に肉を突き刺して炙るようにした。
そうして、切るための黒曜石やフリントと、突き刺すための枝が合体して、ナイフの原型のようなものができた。槍のような形である。1000年前のイギリスのアングロサクソン人は「スクラマサックス」というナイフを所有し、戦いや食事に使ったという。庶民の大半がまだ歯と指で肉をむさぼっていた時代に、一部の上品な人々がナイフをつかっていたのかもしれない。
中世の最も格式高い食事では、ナイフ2本で食事することもあったという。左右の手で1本ずつナイフをもち、左手のナイフで肉を押さえ、右手のナイフで適当な大きさに切った。切ったものはナイフに刺して口に運んだ。少しずつフォークに近づいている。
しかし、肉を押さえる際にナイフだと、肉が回転してしまい肉をしっかり固定できない。そのため、結局指で抑えることも多かったという。そこで、初の実用的な食べ物用のフォークが登場する。その先の歯(タイン)は二叉に分かれていた。
主に台所で肉を切り上げる時に使われ、歯が2本であるため、肉が回転せず押さえやすい。このときのフォークは調理用のもので、歯も大きくて長いものだった。目の前で焼いてくれる鉄板焼レストランでシェフが使っているものに近く、大ぶりのものだった。
17世紀あたりで、次第に食卓でもフォークを使うようになっていく。テーブルフォークになると、大きなものは似つかわしくなく、歯は短く、細くなっていった。
短い歯で肉を押さえるためには、歯の間隔をある程度離さなければならない。すきっ歯のようなフォークは、小さくてぼろぼろとした食べ物のかけらは、歯と歯の隙間からこぼれ落としてしまう。初期のテーブルフォークは食べ物が滑り落ちやすかったのだ。
そこで、3本目の歯が登場する。それによって、匙で料理をすくって口に持っていくのと同じ機能を持つようになり、口まで落とさずに運べるようになったのだ。
3本が改良ならば、4本の方がなおさら良かった。18世紀初めになると、ドイツでは4本歯のフォークが登場し、19世紀終わりにはイギリスで4本歯のディナーフォークが一般的に使われるようになった。
もちろん、5本歯、6本歯も登場するが、4本がちょうどよかった。それは刺しやすさと、口の大きさとの関係だ。歯が細すぎては指しにくく、太すぎては口に入らない。刺すものと口と手の関係の”ちょうど”中間が4本だったのだ。
フォークで食べ物を刺すようになると、ナイフは「刺す」機能を失っていく。もともとは「刺す」と「切る」の2つの機能を持っていたのが、フォークの登場で、ナイフは「切る」のみになった。そのため先端は尖っている必要はなく、現在の丸みを帯びた先端へと進化する。
こうしてテーブルナイフとテーブルフォークは互いに影響を与えながら共進化していくことになる。フォークはさらにまっすぐだった歯が上顎を突き刺さないように湾曲状になり、より口に運びやすく進化する。そうして、我々がよく知っているナイフとフォークに至るのだ。
一方、箸は別の進化を辿る。もともとの起源は諸説あるようだが、食べ物が大鍋で調理され、食事ができたあともその中で保温されながら食べていた。その際に指でつまんでは火傷してしまうため、指の延長としての箸が生まれたという。
また、別の説では、ナイフを見ると君子が近寄らない屠殺場などの場所を思い起こすため、食卓ではナイフを使わないように、と孔子が諭したとも言われている。その結果、箸が発達し、料理自体も箸でちぎれるほどの柔らかい料理が多くなったという。
ナイフ、フォーク、箸。それぞれが人間と食べ物との関係によって変化し、いまの形になっている。これらの進化の過程は「形は機能に従う」説では説明ができない。
食べるという機能自体はいずれの道具も叶えている。しかしながら、文化や偶然や失敗の積み重ねで進化は進んでいく。
本当の意味でモノの形を決めるのは、ある働きを期待して使ったときに感知される現実の欠陥にほかならない。(中略)モノの欠点に目を留めることによって、革新家はそういったモノを部分的に修正して欠点を取り除き、新たな改良品を生み出した。
この欠点、欠陥に目を留めることで、ペトロスキーは「形は失敗に従う」と主張したのだ。
完璧なものなど一つもなく、そのうえ、完璧さに対するわれわれの観念でさえ定まっていないのだから、ありとあらゆるモノは、時の流れとともに変化を余儀なくされる。「完璧になった」人工物などありえない。
ペトロスキーによると、人工物の進化における失敗の役割を明快に論じたのは建築家のクリストファー・アレグザンダーだったという。アレグザンダーは失敗に目を向けなければ成功もできない、と言う。
彼は身近な例を挙げる。箱に入った種々雑多なボタンのなかから、同じボタンを探し出すには、「違う」ものに目を向けるしか無い。色の違うもの、形の違うもの、穴の数が違うもの、その「違う」を選り分けた結果、「同じ」ボタンに出会えるのだ。その違いに目を向けることが、すなわち「失敗」の連続なのである。
アレグザンダーによると、「デザイン」というのは、形と状況の不適合を引き起こす「不調和」や「苛立ち」の原因を中和するためのネガティブなプロセスだと述べている。「不適合が変化の誘因となる。申し分のない適合からは何も生まれない」とアレグザンダーは断言している。
われわれはみな既存の形を批評することができる。とくに重要なのは、こうした過程に創造的な知力が不要であるのを理解することである。その人には形を改良する能力など必要なく、失敗に気づいたとき、ある種の変化をもたらしさえすればよい。
このアレグザンダーの言葉には勇気をもらえる。新しいイノベーションを生み出すために能力はいらない。失敗に気づき、なんらかの変化を施せば、改善に向かっていく。失敗から気づきを得ることこそが重要なのだ。
道具はどう進化するのか?
iPhoneも数々の失敗を繰り返している。指紋認証は復活しないし、Lightningケーブルは不評だし、インカメラの切り欠き部分はずっと嫌われている。その失敗や欠陥に目を向けることで、これからも進化していくことを期待したいものだ。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
