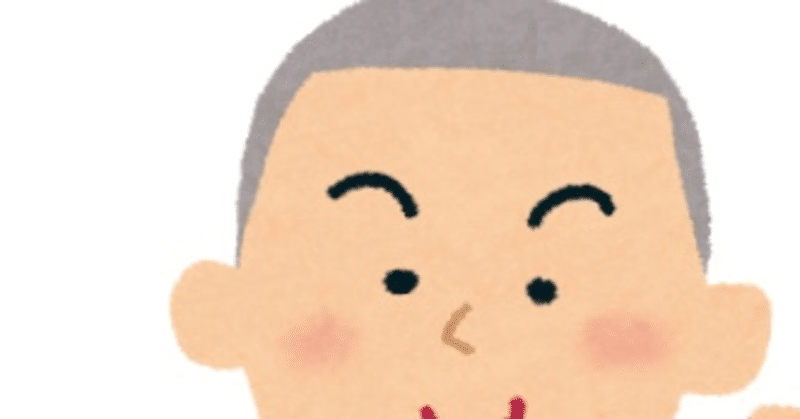
クレイジー過ぎて未だに納得のいかない「一休さん」の『くったくった』
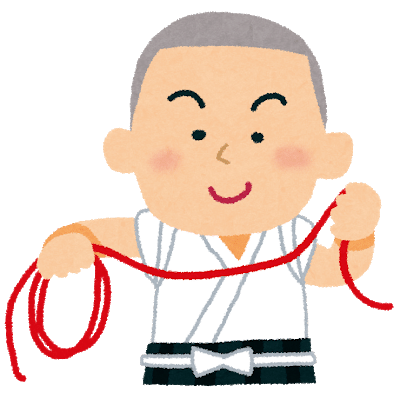
小説を書いたり講談教室に通うなどしているので、人一倍「物語の構成」というものが気になるの性格なのは間違いないが、小説も講談もやってなかった3才児のころから現在に至るまで全くもって納得のいかない昔話がある。「一休さん」のとんち小噺のひとつである『くったくった』(様々な言い方があるようだが、今回はこれで統一する)である。ネットで検索すると多少はヒットするものの、『渡るべからず』や『屏風の虎』と比べるとややマイナーな印象があるので、あらすじを改めて説明する。
①:和尚さんが檀家からお供え物のおまんじゅうをもらう。もちろん供物なので、「わしが留守の間に食べてはいかんぞ」と小坊主たちに釘をさす
②言いつけを破り、小坊主たちはおまんじゅうをぺろりと平らげてしまう。「どうしよう、和尚さんに怒られる」と不安になる小坊主たちの中で一休は策を講じる
③帰ってきた和尚さんは当然「お前たち食べただろ」と小坊主たちを叱る。しかし一休が「いえいえ、仏様が食べたのです。口元をご覧になってください」と反論。和尚さんがみると仏像の口元にあんこが付いている。一休たちが和尚さんが帰る前に塗っておいたのだ
④「そんなわけなかろう」と反論する和尚さん。すると和尚さんはなんと木魚のバチで仏像を叩き始める。「ほれみろ、“くわ〜ん、くわ〜ん”と響いておる。仏様は“くわん”のだ」
⑤しかし一休も反論。「和尚さま、寺の裏の池に仏様をしずめてみてください」。早速仏像を池に沈めてみる。すると“くった、くった”とゆっくり沈んでいく。「和尚さん、やっぱり仏様が“くった”のですよ」
…お断りしておくが、僕はひとつも誇張をしていない。しかし和尚さんも一休さんもクレイジー過ぎる。仏門に生きる人間が、仏像にあんこを塗りつけ、バチで叩き、池に沈めるって、こんなヤバイお寺見たことがない。この小噺の続きを作るなら、おそらく登場人物全員になんかしらのバチが当たるに違いない。 幼心に「コイツらイカれてる…」と思ったのは今も同じである。
昔話というのは大体「弱いものいじめをしてはいけない」とか「約束を守ろう」といった道徳的な教訓が込められている。じゃあ、この『くったくった』の教訓って…?いろんな昔話の教訓に当てはめて、少し考えてみたが…
・弱いものいじめをしない(桃太郎など)→仏様(仏像)をいじめてる
・約束を守る(鶴の恩返しなど)→破ってる
・物を大切にする(笠地蔵など)→してない
・正直に生きる(花咲じいさんなど)→ごまかしてる
ちっとも当てはまらない。まあ『渡るべからず』など、「教訓」より「とんち」がメインの「一休さん」だから、という“言い訳”は出来なくもない。
じゃあ「とんち」としてどうなのか?たしかに『渡るべからず』や『屏風の虎』といった小噺はちゃんと落語のような、掛け言葉や視点を変えて物事を捉える「オチ」がきちんとある。
対して『くったくった』だ。“くわーん”も“くったくった”も掛け言葉としては強引すぎる。大体擬音なんてみんな聴こえ方がそれぞれ違うし、お坊さんが仏像を叩いたり池に沈めたりと普通はしない(というか、常軌を逸した?)行動に出るなんて、ちょっと「ルール違反」という感じがする。桃から生まれたり、竜宮城が出てくるような昔話に「ルール違反」もクソもないが、少なくとも『一休さん』は「とんち」で物を片付ける以上、このファンタジー展開を使ってはダメだろう。ファンタジーがアリなら『屏風の虎』だって、「…するとお殿様は不思議な力を使って、屏風の虎をその場に出しました…」なんて展開もアリになってしまう。やはり「とんち」としても、“失格”と言わざるを得ない。
というわけでちょっと昔話に大人気なくムキになってしまったが、一体なぜ『一休さん』にこのクレイジーなエピソードが誕生したのか、疑問だけが残った…。改めて書いて分析すれば何か見えてくると思いきや、謎が深まるカタチに…。一休さんのとんち小噺の多くは後年の創作であることは広く知られているが、この無茶苦茶な『くったくった』は誰がなんのために創作したのか?いや、実話だとしたら、もっと問題があるけど…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
