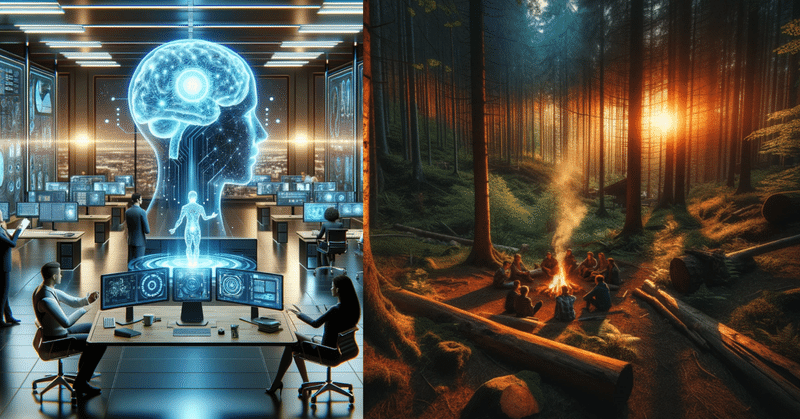
上司がChatGPTになりました...
● 人生のモノローグ。
● 焚き火と対話のステキな関係
● そびえ立つカベ
● そして、すべてはリーダーの肩に
● リーダーへのエール
人生のモノローグ。
とめどなく涙が溢れてくる。身を潜めていた声が一気に流れ出るように。「初対面の人たちにこんな話をしているのだろう。誰にも言いたくなかった弱さをさらけ出している」、「どうして涙がとまらないのだろう。人前で泣いたのは小学3年生の時以来か」焚き火を囲みながら、そんなことを考えていた。温かさがじんわりと伝わってくる。
「こんなに忙しいのに休みなんか取れる訳がないだろう」、「初対面の人たちと焚き火を囲む?何のために?」妻があまりにしつこく勧めてくるので、焚き火ダイアローグというイベントにしぶしぶ参加してみた。もしかしたら、何かが変わるきっかけになるかもしれないという期待もどこかにあったのかもしれない。明確なテーマもゴールもなく、そして判断もしない。
誰も言葉を発しない。薪が爆ぜる音だけが聞こえてくる。「この間は何だろう?何か話さないと気まずい。でも何を話せばいいのだろう...」聴くって何だろう。「もっと早くこの場に来ていたら、違った結果になっていたかもしれない」後悔の念が押し寄せてくる。涙は止まっていた。
焚き火と対話のステキな関係
「職場でよく話をしているのでコミュニケーションは取れています」という声をよく耳にする。このような場面で使われる“話をする”は、おしゃべりや会話を指していることが多い。本書では単に情報を伝達するだけではなく、深い理解と共感が生成される行為のことを対話として扱っている。
相手の言葉を真摯に受け止め、自らの思考や感情をありのままに表現することにより、より豊かな人間関係の土壌が養われていく。このような関係が構築できれば、リーダーもメンバーも腹落ちして同じ目標に向かっていけるのだが、実際には組織と対話との隔たりは大きい。
焚き火を囲むと自然と対話が生まれるのはなぜだろう。一つには、その環境がオープンでリラックスしたコミュニケーションを促進するからだろう。焚き火は物理的に人が一箇所に集まり、共有の経験を提供する。この共有された空間は、自然と会話を引き出し、人と人のつながりを深めるきっかけとなる。
焚き火の周りでは、日常生活の雑踏から離れ、いつもよりリラックスし開放的になれる。開かれた世界だ。リラックスした環境は、心を開いて本音で話すことを促し、より深いレベルでの対話を可能にする。
焚き火の周りでの対話は、しばしば人生の深い話題や個人的な経験へと進む。普段は語られないような話題についても、火を囲むことで安心して話すことができる。焚き火には人と人を結びつけるチカラがある。
そびえ立つカベ
自らが中心となって提案した新規事業を立ち上げることになった。ライバル企業も前年度に進出していたが、訴求ポイントをしっかり絞り込めば十分戦えると考えていた。問題は誰が旗を振るのか。
会社は旧態依然としていて、役員クラスは保守本流といった顔ぶれだ。新製品・新規事業開発は最重要テーマだったが、シーズありきの開発に終始していた。社長の鳴り物入りで始まったプロジェクトが2~3年後には撤退していた。
「必ずしも提案した人がやることはない」、「渦中の栗を拾いに行っても火傷するだけだ」、そんな思いが強かった。しかし、上司から背中を押され、共に検討してきたメンバーからも「もう腹をくくるしかないんじゃないですか…」と言われ、得体のしれない何かに飛び込むような気持ちだった。
間もなく、新しい部署ができたものの、トライ&エラーが日常であり、あらゆるものが常に不足していた。
あっという間に2年が過ぎ、ようやく事業が軌道に乗り出した頃に綻びも見え始めた。立ち上げ時を知らないメンバーが増えるにつれて、お互いの気持ちに心を寄せることができなくなっていった。
そんなある日、無理をして海外研修に出した2年目の若手が帰ってくると同時に退職した。そして、指導員だった立ち上げメンバーの様子がおかしくなった。「○○さんの責任じゃないから気にしないように」とは言ったものの、彼女の顔からしだいに笑顔は消えていった。
そして、すべてはリーダーの肩に
仕事では数字を追いかけ時間に追われ続ける。誰も先が見通せないにもかかわらず、上司からは結果を求められ続ける。その一方で、部下は答えばかりを求めてくる。
「会社で感情的になるな」「経過はどうでもいい、とにかく結果を出せ」、「お前の想いなんか関係ない」。私が若い頃はそんな時代だった。会社においては、個人の思いや価値観は存在すらしていなかった。自分が上司になったら絶対に変えたいと思っていた。そんな熱い想いと経験に加えて学びと実践のサイクルを回せば、よきリーダーになれると信じていた。
ところが、リーダーシップや組織論等に関するビジネス書をかたっぱしから読み続け、MBAでの学びを実践しようとすればするほど、周囲との溝は深くなっていった。いつしかビジネスの原理原則やロジックに囚われ、感情は置き去りにされていた。
時代は様変わりしたが、はたしてマネジメントは変わったのだろうか。
私はよく書店に足を運ぶが、リーダーやリーダーシップの本がこれでもかと並べられている。ビジネス書を読み漁ってきた感想を一言で言うと、「ここまで多くのことを期待されては、リーダーはもたない」である。ここ20~30年のビジネス環境の変化(コロナ禍も含めて)をすべてリーダーの力量に依存しているかのようだ。
組織やリーダーが直面する問題は技術的課題から適応課題へと変わってきている。気候変動への対応がイメージしやすいかもしれない。世界各国の首脳陣が定期的に集まって会合を繰り返しているが、各国の利害関係がはげしくぶつかり合って抜本的な対策案はいまだに見いだせていない。
このように解決が極めて困難であり、発見すら難しい問題の矢面に立たされているのがリーダーの実態ではないだろうか。これでは溜まらないだろう。リーダーになること自体が罰ゲーム化するのもうなずける。それでは、どうすればいいのだろう。一見、遠回りに見えるかもしれないが、対話からはじめるしか道はないというのが私の実感である。
リーダーへのエール
私が会社を去る時に、事業立ち上げ時の部下が送別会を開いてくれた。退職してしまった部下に対しては何もできなかったという自責の念が強く、気まずさを感じながら店に向かった。少しだけお酒の力も借りて、お互いの心情をようやく話すことができた。私にとっては生涯忘れ得ぬ大切な時間となったが、同時に「もっと職場で対話をしていれば、全く風景が広がっていたに違いない」というやり切れなさが込み上げてきた。
息詰まった関係性の中に閉じ込められているリーダーが多いのではないだろうか。私の苦い経験から得た学びが、そんな熱い想いをもったリーダーたちの役に立つのであればこれ以上の喜びはない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
