
いまさら聞けないお金の疑問③ 金利は誰が決めるもの?
こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。
前回は金利の役割などについてお伝えしました。
初回では金利について、意味や混同されがちな単語との違いを解説しているので、ご興味のある方はぜひこちらもあわせてご覧ください。
さて、3回目の今回は金利は誰が決め、社会にどのような影響を与えるかについて詳しくみてみましょう!
1.金利は誰がどうやって決めるの?
私たちがお金を預けたり、貸したりする際の金利は各金融機関が自由に決めています。
これを市場金利といいます。
自由に決められるとはいえ、もちろん基準になるものはあります。
それは日本の中央銀行である、日本銀行の政策金利です。
政策金利とは、中央銀行(日本の場合は日本銀行)が景気や物価の安定など、金融政策上の目標や目的を達成するために設定する金利です。日本銀行が一般の金融機関に貸し付ける際の基準となる金利でもあります。
そのため、政策金利に基づき市場金利も上がったり下がったりするのです。

政策金利は日本銀行で毎月開催される金融政策決定会合という会議で決定します。
達成すべき目的に応じて利率が変更されますが、社会に及ぼす影響が大きいため、基本的には大きな変動は行わないという原則があります。
そんななか、2024年3月の会合で2016年からずっと続いてきたマイナス金利が解除されると決まったことで大きな話題となりました。
2.金利はなぜ変動するの?
・変動する理由
スーパーに並ぶ野菜を思い出してみましょう。
その年の天候や天災などの影響で収穫が多すぎて値崩れしたり、収穫が少なすぎて価格が高騰したりすることがあります。
需要と供給のバランスが崩れた結果、価格が変動しますね。
金利も同様に、資金の需要と供給のバランスによって決まります。
お金の量が一定であるとき、資金を借りたい人が多く、需要が高い場合には金利が上がり、逆の場合には金利が下がります。
・金利が上がるとどうなる?

金利が上がると、利息も増えます。
預金や貯蓄をする際に有利になりますね。
消費するよりも貯蓄や預金、資産運用が選ばれることが増え、金融機関には資金がストックされます。
一方、金利が上がると利子も増えるので、借入するには不利になります。
企業の新規投資や積極的な事業展開が難しくなり、個人の消費活動も減るのです。
お金の流れが止まると消費も落ち込み、企業の業績が悪化します。
業績が悪化すれば株価も下落傾向になり、景気は減速していきます。
・金利が下がるとどうなる?

金利が下がると、金融機関は日本銀行から資金を低い金利で調達できるようになるため、借入する企業や個人にとって有利になります。
個人消費が増えたり、企業の事業展開がしやすくなります。
銀行に支払う利子が減る分、利益も多く出せるようになるのです。
一方、預金の金利も下がるので、貯蓄の意欲は薄れて投資や消費にお金を回す人が増えていきます。
経済活動も活発になるので、企業の株価も上昇傾向になり、景気は加速していきます。
・まとめ
金利が変動する理由などについて下記にまとめました。

3.さいごに
今回は金利の決め方や変動の理由などについてお届けしました。
金利がお金の流れや景気を左右するほどの影響力をもつことをご理解いただけたでしょうか?
次回は2024年6月から開始された定額減税制度について、どのような制度なのかをまとめて解説いたします!


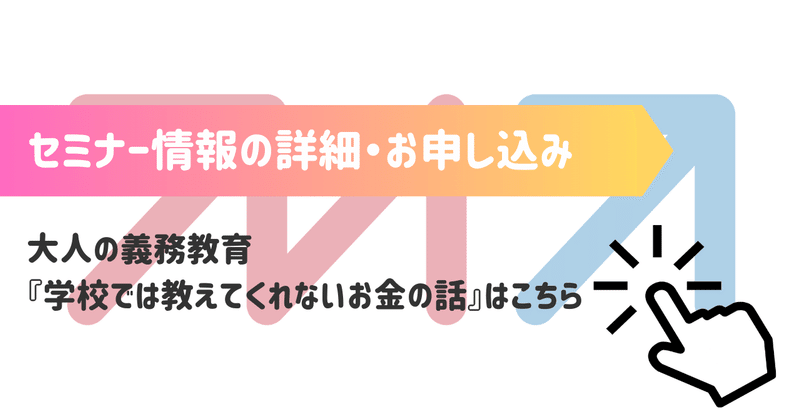
最後までお読みいただきありがとうございました! スキ♡・コメント・フォロー・サポートとっても励みになります◎
