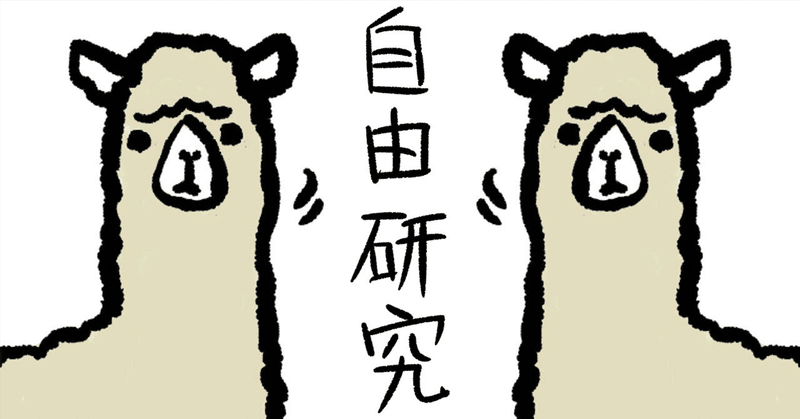
毎年怒りながら夏休みの宿題をやらせていたのに、今年は楽しくできたおハナシ
夏休みの宿題は、子どもの課題?
子どもの時からずっと、夏休みの宿題は、
子どもに課せられた課題だと考えていた。
わたしの親は夏休みの宿題を手伝いはしなかったので、
夏休みの宿題は自分でやるのが当たり前だと思ってきた。
子どもに課せられた課題なので、
子ども自身が解決するのが当たり前だと。
宿題を終わらせることができないのは、
計画性のなさと、根気のなさからと毎年のように落ち込んでいた。
親になってからも、
子どもの頃と同じように考えていたので、
子ども自身が主体的に取り組むために放任してみたり。
一方で、あの「宿題が終わらないかもしれない」という
焦りや不安は知っているので、
期限が近づいてきた頃に慌てて宿題に取り組ませたり。
わたしも焦っているから、
最終的にはわたしは怒りながら、息子は泣きながら、
という結果になった。
夏休みの宿題を親子で取り組むことだと考えてみる
長男は、【自由研究】を楽しみにしていた。
去年、私が怒りながら、
息子が泣きながら取り組んだ自由研究だったけど、
賞を取ったのが嬉しかったから。
息子の楽しみをよそに、
まるで子ども時代の夏の終わりに感じたような、
憂鬱な気分になっていた。
「今年も、怒りながら、泣きながら自由研究やるのかな?」
ところが、今年のわたしには子育てのメンターがついている。
夏休みの宿題は、親子で取り組む課題だと捉え直すことにした。
「べき思考」」に囚われていたわたしにとっては、
目から鱗。
でも、落ち着いて考えると、
小学2年生が自由研究まとめるのって、
どうしても親の助けはいるよね。
やり方だって習っていないのだから、
それも教えないといけないし。
それを、「教えないといけない」とか
「やらせないといけない」とか考えていると、
指導的になってしまう。
だから、一緒にやろうと考えてみた。
親は手を出してはいけないと考えてきたので、
けっこう恐る恐るだったけど、
エイッとやってみた。
口を出す代わりに手を出してしまおう
一緒に取り組むんだから、
全部子どもにやらせなくていいじゃない。
「さあ、やろう!」と軽やかに誘って、
一緒にやったらいいじゃない。
そうすると、
子どもに「なんて書くの?」
「ほら、書きなさい。」と
口うるさく言わなくていい。
「お母さんは、〇〇って書き方がいいと思うけど、君は?」
「じゃあ、〇〇って書いてごらん。」
「お母さんは、ここを塗ろうかな。」
タイトルを思いつかなかったから、
わたしがちょっとかっこいいのをいくつか挙げると、
その中から息子が決めた。
いいじゃない。
息子は文字を淡々と書いていくので、
わたしはその横から、アンダーラインを引いたり、
写真を貼ったりとデザインを担当した。
うん、なかなかいい出来。
いいじゃない。
夏休みの宿題は親子の共同プロジェクト
夏休みの宿題は、子どもに課せられた課題と捉えると、
それがクリアできているかどうか監視、監督したくなるけど、
親子の共同プロジェクトと捉えると、親子は協力関係になる。
自由研究に取り組んだ4日間は、
自由研究以外のことを全て後回しにして、
とびきりのご褒美を用意した。
それだけに集中できるように。
そして、プロジェクトは無事に完了した。
しかも、笑顔で。
こんなに楽しくて嬉しくて幸せなことはない。
宿題を楽しくする方法があるなんて思わなかった。
考え方を変えるのって難しいけど、
行動を変えると考えって変わるのかも
次にまた子どもたちが
難しい宿題や他の課題を持って来たとき、
今までのわたしは「自分のことは自分でやりなさい」
と言ったかもしれないけど、
この先は、「一緒にやってみる?」という選択肢がある。
難しい課題は一緒にやったらいいということが
体験として分かったから。
長年それが良いと考えてきたことって、
なかなか変えられないけど、
ちょっとエイッと行動を変えてみたら、
そういう考え方でもうまくいった。
行動を変えると考えって変わるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
