
#10 #LLVR [a Like Love within a Virtual Realm]
最近、少し前よりこのワールドの雰囲気が和やかだ。というのも、スリーが前ほどアインに固執しなくなったから、と見える。気持ち的にはアインのことを諦めたわけではないようだが、ナナちゃんというスリーにとってのイエスマンができたことが大きく影響しているのは確かだった。ナナちゃんはスリーのことを基本否定しない。少なくとも俺達の前では。ディーさんスリーちゃんのこと狙わないで下さいよ! と冗談めかして言ってきたが、多分あれは冗談ではなく本音だろう。別に狙う気など微塵もないので安心してくれ、とだけ答えておいた。
それにひきかえ――
「昨日仕事でミスしてしまって……」
「あー俺もそういうミスしたなぁ。大丈夫だよ、それくらい」
仕事でミスしていつもより凹んでいるノルちゃんの頭をアインが撫でる。いつも通りの光景だ。そう、いつも通り。そりゃあ付き合ってないって言ってるのにやたら距離の近い異性がいる奴を好きになったら苦しいよなぁ、とスリーにほんの少し、本当にほんの少しだけ同情しないでもない。でもまあこういう二人だしなぁ、とも思っている。
自分もリアルの彼女と、友達の段階で距離感がおかしかった覚えがあるのであまり人のことを強く言える立場ではない。知り合ってから恋人になるまでの過程で、一体どのラインからこれを恋愛と定義して恋人という契約を結ぶのか。難しい話だ。やることやってるけど恋人でないセフレなんていう関係もあるくらいだし、お前ら傍から見て恋人同士に見えるから恋人名乗れ、なんて言えるわけもなく。バリスではひとりで眠るのが寂しいからと一緒にVR睡眠をする人らもいるくらいなのだから、余計わけがわからない。リアルだったら据え膳食わぬはなんて言われている状況だ。そりゃあバーチャルでは手の出しようがないが。果たして恋とは愛とは関係とは。
「なーに虚無ってんの」
ひらひらと目の前で手を振られてはじめて自分が焦点の合わない目になっていたことに気づいた。カトルはどっこいしょと俺の隣に座り、カシュ、とおそらくチューハイの缶を開けた。
「寝かけてた」
「ふうん」
噓でしょ、と言う代わりの相槌。
「ディーんとこはどうなの、彼女さんと」
「平和だよ。びっくりするほど平和」
「ほんとにー?」
「ほんとほんと」
よっこらせ、と上体を起こして、俺も出していたハイボールの缶を開けた。
「おっいいね。かんぱーい」
「うぇーい」
ごくごくと缶を煽る。喉元を駆け抜けていく炭酸が気持ちいい。
「ぷはー。うま」
「本当に何もないの?」
「んー順調なのは本当。そろそろ結婚するかーみたいな話してる」
「え! めでたいじゃん!」
「そ、めでたい」
自分が順調だから尚のこと、周りの大変さがわからない。そりゃあ自分のとこだって喧嘩したこともあるし一度別れたこともあるが、元の鞘に納まったあたりいわゆる切り分けた一つのレモンの果実だったようだ。
「まー結婚したからといって何も変わるわけでもないけどねー。婚姻届っていう契約書を提出するだけ。オワリ」
「ロマンのない言い方するなぁ」
「結婚にロマン抱いてるやつは大抵失敗する」
「それはそうかも」
結婚とは契約だ。二人の人間が相互扶助し合って生きていきますという契約。だから別に人生のゴールでもなければお姫様になれる魔法でもない。
「ディーって意外と真面目よね」
「意外とは失礼な。こんなに清廉潔白なのに」
「どこがよ」
カトルは笑いながら酒を煽った。
「まあ、清廉潔白も嘘じゃないんでしょうね。彼女さんからしたら。意外と真面目だし」
「そ。俺は超真面目なの」
「超真面目な人はこんな適当な会話しないでしょ」
「それはそう」
視界の右側ではスリーとナナちゃんが、左側ではアインとノルちゃんが、仲睦まじくおしゃべりを楽しんでいる。不思議な光景だ。いつかはあの子達も、関係性をはっきりさせて将来のことを考え出すのかと思うと、こんなに大きくなって、という親戚のオッサンの気持ちがわかるというものだ。
「はあーぁ。いいなぁ皆。青春してて」
「いいかぁ?」
カトルの呟きに反射的に疑問形で返す。少なくとも青春という言葉が似合うほど爽やかではない気がする。特にスリー。
「絶対大変だと思うんだけど、でもやっぱさ、好きとか、そこまで行かなくても特別に仲良い相手とかいると、羨ましいなーって思うようになってきちゃって」
「老けたな」
「オイ」
はははっと笑って酒を飲んだ。そのときポーンとワールドの入室音が鳴って、カトルのフレンドであるリュウさんがやってきた。
「こんばんは」
「リュウさんこんばんはー」
皆口々に挨拶をする。リュウさんは律儀に挨拶を返した後カトルのいるこちらの輪の方へやってきた。
「こんばんは」
リュウさんが改めて挨拶をするとカトルはやっほーとリュウさんの長い髪を手でなぞった。
「飲んでるんですか」
「うん。華金だからね」
「リュウさんはお酒飲まないの?」
あまり飲んでるところを見たことがないので尋ねてみると、彼は少し考えてから口を開いた。
「飲まない、というか、正確には飲めるんですが、あまり強くないので、こういう場では控えています」
「ひとりでは飲むんだ」
「そうですね。まあそれでも飲む頻度はかなり低いですが」
「え、今お酒ないの」
カトルはうきうきしながらそうリュウさんに尋ねた。リュウさんは少し固まって、言おうかどうしようか迷っている気配を醸し出す。
「ないの?」
んー? とカトルがリュウさんの顔に自分の顔を近づける。これがリアルなら立派なアルハラだ。
「……取ってきます」
根負けしたのかリュウさんはAFKになり、しばらくして戻ってきた。なんとなくなのだが、リュウさんはカトルに大分弱いように見える。いや、甘いという方が適切だろうか。
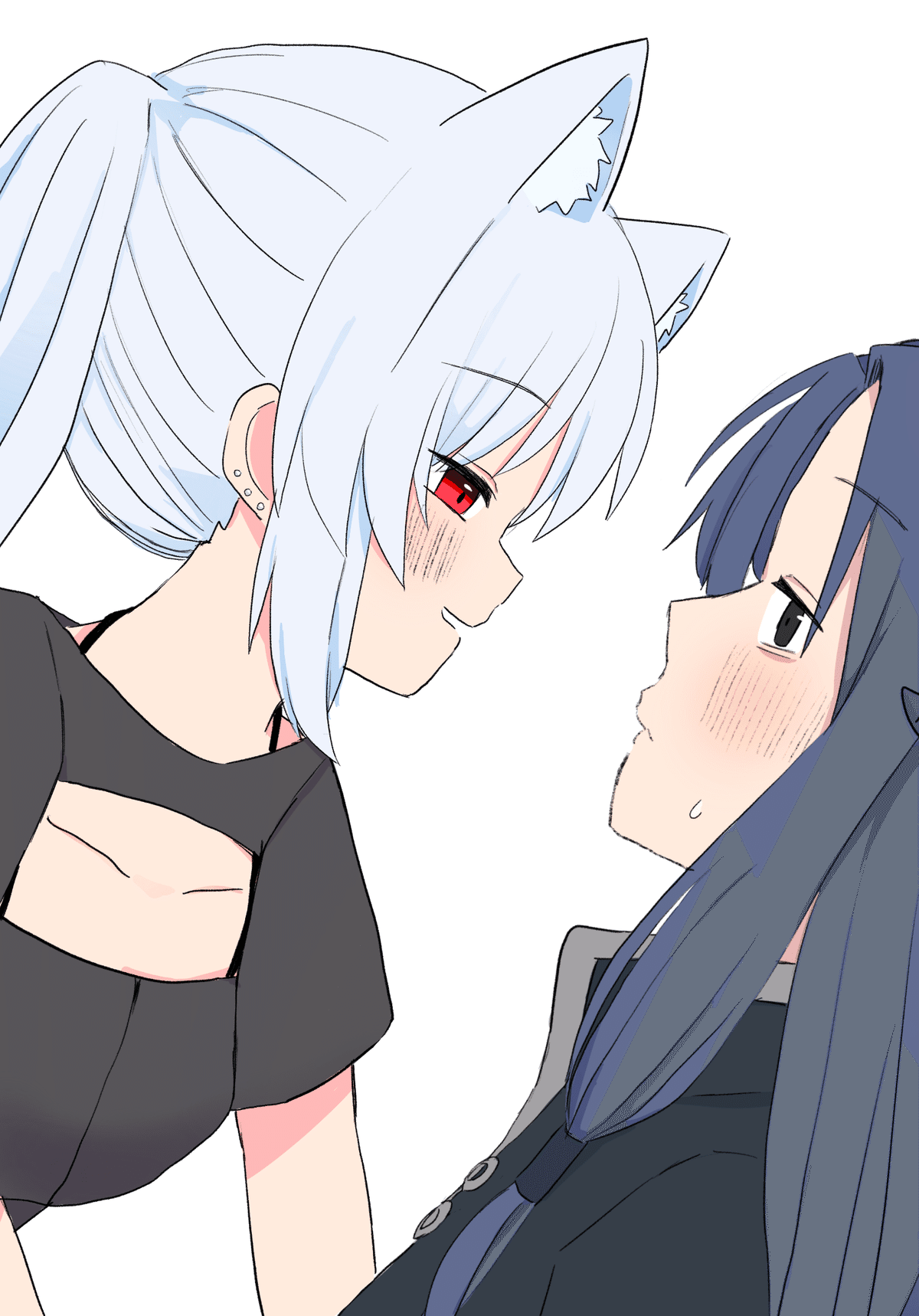
「お待たせしました」
「はーいかんぱーい!」
カトルが右手を上げたのでそれに倣って俺とリュウさんも右手を上げた。そのままリアルでも酒を煽って、ぷはーと息を吐く。
「あーうめぇ」
カトルはカトルでリュウさんに懐いているというか、興味津々というか、他の人とはまた違う接し方をしている気がする。
「ねね、リュウくんは何飲んでるの」
「ジントニックです」
「ジントニックいいね! ジンの度数は?」
「四十七、ですね」
「それで割ると大体十パーセントいかないくらい? それで酔っちゃうの?」
「はい。わりと」
「本当に弱いんだね」
へぇーとカトルはまた酒を煽る。カトルはいつもハイペースだ。酔うとふにゃふにゃになるが基本記憶を飛ばしたり他人に迷惑のかかる酔い方はしない。基本的には、なので、たまにタガが外れたりすることがあるが。
「カトルさんは、結構飲まれるんですね」
「まぁねー」
「でも酔うと」
「まぁねー」
カトルは既に酔ってきているように見える。リュウさんは煽るような飲み方はせず、嗜む、という飲み方をしているようだ。各々がそれぞれのペースで飲みながら、さっきの話題の続きを話す。恋愛とか結婚とか。
「リュウさんは、恋人いるの?」
「いないですね」
「モテそうなのに」
「そんなことは――」
「えーリュウくん恋人いるのー?」
酔ったカトルがリュウさんに完全に絡んでいる。
「いないって今言っただろ」
「んーならよろしい」
んふふーと言いながらカトルはリュウさんにもたれかかる。リュウさんは特に嫌がる様子もなく、なされるがままだ。酔ってないときもわりとなされるがままなので、カトルに対してはそれくらい心を許しているのだろう。
「カトルさんは、どうなんです」
「いないよぉー」
「意外ですね」
「そーお?」
「女性の気持ちとか、よく汲んでそうですが」
「んなことないよー。キャバクラで女の子やってるからって女の子の気持ちがわかるわけじゃないよー」
カトルはリュウさんの尻尾を伸ばしたり離したりして遊んでいる。
「それに女の子ってひとくくりにできるもんでもないしねー。私にはスリーの気持ちもノルちゃんの気持ちもわかんないよー」
自分の名前が出たのでスリーとノルちゃんがこちらを向いた。二人とも首を傾げたのでカトルの代わりになんでもないよ、と言った。ここで巻き込んだらややこしくなりそうだったので。
「現実じゃこんな簡単に話せないよー。すーぐセクハラだとか言うじゃん? リアルの女の子はむしろ苦手だよー」
カトルはごろりと寝頃がってリュウさんの尻尾に顔をうずめてもふもふしはじめた。最近のお気に入りらしく、リュウさんがいるとリュウさんの尻尾のあたりが定位置になっている。
「確かに、難しいですね」
「大変だねぇ。俺はそんなに深く考えてないな」
「ディーさんは、今の彼女さんとは、どういう経緯でお知り合いになられたんですか」
「俺の場合は特殊だな」
話を振られたので酒を一口飲んで座り直す。
「学生時代から付き合ってるんだよ。高校が一緒で、そんときは何もなくて。その後たまたま大学が一緒で、しばらく一緒に行動してて、んで気が合うなってんで付き合うことになった」
「そうだったんだ」
カトルがリュウさんの尻尾の間から顔を出した。
「でも確かにディーっぽい」
「俺っぽいとは」
「んーなんか変な駆け引きとかしてなさそうな感じが」
「あーそれはそうだな」
恋愛の駆け引きとやらは俺にはわからない。それらが必須事項だったら確実に恋人などできていないだろう。
「リュウさんは? 学生時代とかモテてそうだけど」
「いや、そんなことはないですね」
「彼女いたことないの?」
「いたことは、ありますが……」
リュウさんは煽るのではなく三口ほど酒を飲んで、珍しくうーんと唸った。
「……まあ、上手くいってないからここでこうしているわけです」
「なるほど?」
何やら含みを感じるが、つっこんで聞いていいものだろうか。気になりつつも、あまり深堀りはしないで適当な雑談で済ませよう。そう思い、適当な雑談に話を繋げた。
ぐでん、と力を抜いておそらく椅子の背もたれに体重を思いきりかけた座り方をしているリュウさんを、初めて見た。
「リュウさん、大丈夫?」
「……んん、はい」
「飲ませすぎちゃったかな。主にカトルのせいだけど」
飲め飲めと叫んでいた本人は珍しく寝落ちしている。
「いえ、だいじょぶ、です」
「大丈夫じゃなさそー」
こういうとき介抱してタクシーに詰め込んで帰らせるなどの手筈がいらないのがVRでの最大のメリットだと思う。
「ディーさん、お強いですね」
「まあね。その自覚がある程度には強いよ」
「羨ましいです」
「そうかぁ? 酔うって感覚がわかんないからコスパ悪いと思うよ」
「でも、飲んでる人の相手をするには、適度に飲めた方が、いいですから……」
「それは確かに」
アインやスリーたちは先に落ちてしまった。といってもさすがに夜中という時間を超えもうすぐ朝と言えなくもない時間帯なので、我々が夜更かししてしまっただけだが。
「カトルも寝てるし、さすがに俺らも落ちよう」
「そう、ですね」
「カトルなら大丈夫だよ。珍しいことだけど、何度か寝落ちしたことはあるから」
「……」
リュウさんはカトルの方を見つめている。カトルは寝返りを打ったせいであらぬ方向に手足が曲がっている。リュウさんは先に落ちそうにないので、俺が先に落ちることにした。
「じゃあおつかれさん。リュウさん、ちゃんと水飲んでね」
「はい。ありがとうございます」
「じゃ、おやすみ」
「おやすみなさい」
リュウさん、落ちなさそうだな。俺はそう思いながら、先にバリスから落ちた。
No.10
君が特別になったのは いつからだっただろう
その声が特別綺麗に聴こえるようになったのは
その瞳が特別輝いて見えるようになったのは
その手が特別あたたかく感じるようになったのは
僕が君の特別になったのは いつからだったのだろう
会うことが当たり前になって
話すことが当たり前になって
一緒に居るのが当たり前になって
触れ合うのが当たり前になって
激しく燃える恋じゃなかった
ゆったり育む恋だった
今では暖炉のようにチリチリと
小さな火花を散らしながら
ずっとあったかいままいてくれる
君に会えて本当に良かった
君と会えて本当に良かった
僕が僕らしくいられるまま
僕が恋をできてよかった
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
