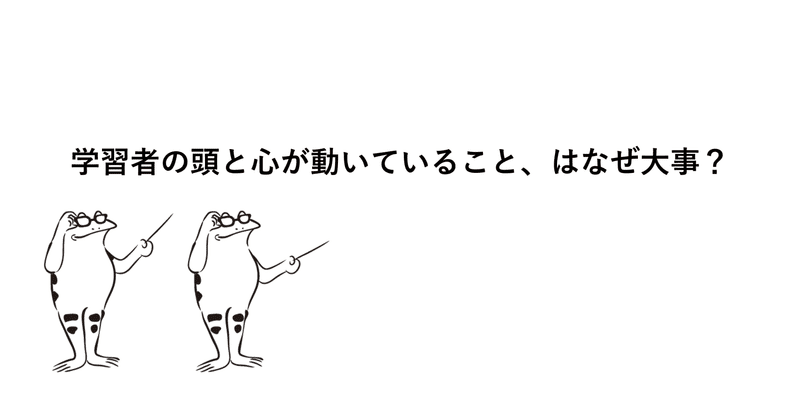
学習者の頭と心が動いていること、はなぜ大事?#日本語
初めまして。「日本語を教えること」が大好きな、控えめに言って天職だと思っていますが、今は教師を辞めて企業で人事をやっている、元日本語教師です。人事の経験も、人に関わるスキルをあげるための経験の1つになるだろうし、その間にすこしずつ自分らしく働ける準備を整えて、近いうちに本業=日本語教師に戻りたいと思ってます。
さて、最初の記事は自己紹介にもなるように、ちょっとだけ真面目に、私が大事だと感じていることを書こうと思います。
15年ほど日本語教育に携わってきました。日本語を教えるといっても、日本での生活のため、日本語能力を測る試験などの試験合格のため、ビジネスのため、子供の日本語学習支援のためなど、さまざまですが、私が主に携わってきたのは、ざっくり言うと「コミュニケーションのための日本語」です。日本人と話したい、日本で自分の日本語を使って暮らしたい、という人たちが、自分で考えて、日本語を話して、豊かに生活するための日本語をマスターできるように学習者をサポートしたい、と思ってやってきました。まぁ、ペーペー時代からそんな風にちゃんと考えられていたわけでは当然なく、いろんな先生や学習者との出会いを通して、私なりにたくさん大切なものを学び取ってきました。
自分で考えて、自分で話して、自分の生活を豊かにしていくことはとっても大事なことです。「あいうえお」から始めた学習者たちが、(面白いかはさておき)彼らなりのオリジナルのユーモアを交えて、日本語で感謝のスピーチをして卒業していく光景を何度も見てきました。彼らの後ろには鮮やかな光がさして、自信に満ちて、自分の足で立ってここにいるんだ!という強さも感じられて。言葉を自分で使えるようになると、世界は一気に大きく、そしてカラフルになるんだなあと実感します。
そんな学習者を育てていくために、私たちは何をしてきたんだろう?教える側はどう取り組んだらいいんだろう?と考えていて、整理してみたのがこの図です。(だいぶ前に、教師同士の勉強会で使ったものですが。)授業やクラスの在り方、教師の役割、学習者がすべきことをこんなふうに捉えたら、自分で考えて、話せる学習者のサポートができるんじゃないか?っていう図です。

例えば、「Vてもいいですか」を導入する時、「Can I~?=”Vてもいいですか”です。」って板書したり言ったりしてべたっと説明するのと、サイレントでも、声付きでも、場面を作って「あの、これ、つかってもいいですか?」「あ、どうぞどうぞ」って場面を見せるのと、どっちが学習者は考えるか?頭が動くか?ってことです。上手に見せて(ここたのしい)、気づかせて(ここもたのしい)、「そうそうそう!」(ここ最高にたのしい)とポイント押さえたら、今度はどんどん試させて、うまくいったり、間違えたりしながら、「あ~、じゃあこうも言える?」「こうは言えないってことか~」「~語とちがうのか!」「おもしろい!」と頭と心をフル回転させながらつかんでいくのを手助けする。中には、べたっと説明されるのが好きな人もいるかもしれないけど、そういう人は本で自習しても同じくらい効果的かもしれない、と個人的には思います。
ということで、これまで学び取ってきたこと、これから考えたいこと、今思うことなんかをここに蓄積していきたいなと思ってます。日本語の具体的な教え方や、教案、教材づくりなどについても書いてみたいです。
あ、それと、タイトルにある通り「人の話し方が気になる」ので、気になったことも書いてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
