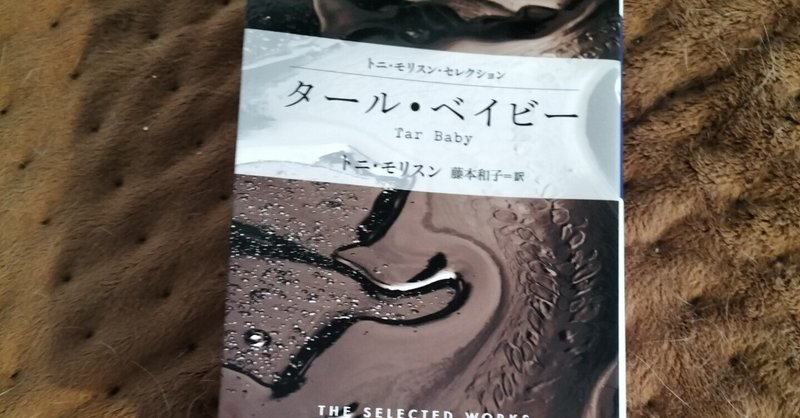
ト二・モリスン『タール・ベイビー』藤本和子訳、早川書房
素晴らしい小説だった。いろいろな小さいテーマが大きな物語を構成する。舞台はカリブ海の小島、そこに暮らす風変りな金持ちの白人の男とその家族や使用人、地元の黒人たちが描かれる。そこにアメリカから来た黒人の若い男が乱入する。
ひと口に黒人といっても、生まれや境遇によってさまざまに違う。フィラデルフィアで白人一家に仕えてきたシドニーとオンディーンは主人ヴァレリアンと共にいまは島の屋敷で暮らしているが、フィラデルフィア黒人としてのプライドを捨ておらず、現地の黒人を(たとえば名前ではなく「雑役夫」と呼ぶなど)見下している。しかし黒人としての感覚を捨てたわけではなく、また少々古いものの人間らしい感覚を持っている。彼らの姪ジェイドはヴァレリアンの経済支援でフランスの大学で美術史を学び、モデルをしたり、たまに映画にも出ている。この姪は黒人でありながらもはや中身は白人のようだ。一方で現地の黒人たち、テレーズやギデオンは彼らなりの暮らしをしていたが、近くに住むようになった白人一家にまったく影響されないはずはない。こういう設定の舞台に飛び込んできたのが、フロリダの田舎町に生まれた無学な(しかし美しい)黒人男性のサン。彼は底辺の黒人のひとりとして現地の黒人たちに共感を示す。
主人ヴァレリアンは白人社会から逃げ出してこの島に暮らしているが、白人の文化を完全に捨てたわけではない。またその美しい妻マーガレットは子どものころからの心の傷を抱えたまま、アメリカと島を行ったり来たりで暮らしている。二人にはマイケルという息子がいるが、クリスマスに帰って来る気配はない。
物語は都会的で教養のある娘ジェイドと、「瞳の中にサバンナ」「星のようにセックスする」などと描写される野性的なサンの恋を中心に進む。こんなにも育った文化が違う二人は果たしてうまくいくのか。答えはオープン・エンディング。
主人のヴァレリアンは、飛び込んできて食べ物を盗み食いしながら屋敷に潜んでいたサンがクロゼットで見つかっても、追い出そうとしないばかりか客人扱いする。そして、招待した者が誰も来ないとわかったクリスマスには、サンだけでなく、使用人のシドニーとオンディーンの夫婦もゲストとして食卓に招待する。一見、ユートピア的な情景であるが、オンディーンはそんな偽りをひっくり返すような衝撃的な発言をして、結果彼らはバラバラになってしまう。
これからの黒人はどう生きるのがよいのか。大学で学んで教養を身につける? 野生を忘れずに生きる? 故郷の田舎町の生気のない黒人たちをいつまでも愛する? 都会でスマートに生きる? 娘は子どもを産んで老いた親を世話して生きるべき? いろいろな道があり、若い二人はこれから悩みながら生きていくのだろう。この小説にはシェイクスピアの『テンペスト』を彷彿とさせるような部分もある。プロスペローが島を去ったあとのキャリバンはどう生きたのだろうと考えてしまった。
題名の「タール・ベイビー」は解説によると黒人の口承民話の話らしい。作者モリスンは「自分は口承で伝えられる民話を聞いた最後の世代だ」と言い、口承がありえなくなっても違うかたちで黒人の文学を伝えていきたいと考えている。その意志はこの小説の文体にもあらわれているようだ。小説ではあるのだが、いたるところでまるで叙事詩を読んでいるような豊かな言葉のリズムとイメージが溢れている。トニ・モリスン、ほんとにすごい作家だ。わたしがひそかに持っていた「黒人文学」への偏見(暗い、つらい、共感しにくい)を完全にひっくり返してしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
