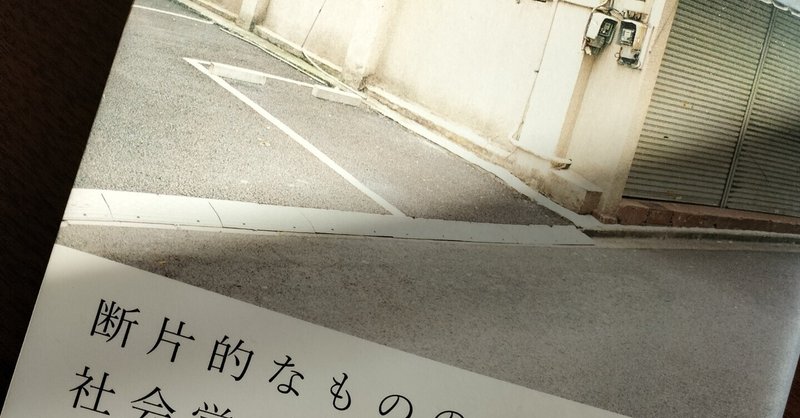
岸政彦『断片的なものの社会学』朝日出版社
不思議な魅力を持つ本だ。社会学の論文には入れられない、だけど作者にとっては大事なこと、だがうまく記述できない……そんな<断片>が集まっている。
冒頭のエピソードでは、沖縄に行ってある人を自宅に訪ねてインタビューしていたら、突然その家の犬が死んだ(と息子が父に告げに来る)。なのにインタビューされている男はそのまま話し続ける。その場面が、作者にとっては奇妙な記憶となる。「何が書いてあるのかはっきりとわからないが、妙に記憶に残る短編小説のよう」と表現される。あるいは、どこか不条理な夢のような記憶かもしれない。
切れ味よくは記述できない、なぜ自分がそこにひっかかるのか自分でもわからない、そういう出来事がたぶん誰にでもあるが、忙しい毎日でそんな断片は頭から振り落とされる。でもこの作者はそこにこだわるのだ。そこに人間のとらえにくさや人生の不思議さがあると感じるのだ。
たとえば、ネット上には誰に読まれるとも意識しないで素人が書いた断片の文章が漂っている。下手な文章。何を書こうとしているのかもわからない、そんな「誰にも隠されていないが誰からも見えていない」言葉が漂っている。それを作者は「美しい」と感じる。
たとえばこんな話も。あるマンションの一室で、問題をいろいろ抱えていた家族がついに散り散りばらばらになって出ていく。その部屋はゴミ屋敷になっていたらしい。階下の住人が天井にシミが出た、虫が出た、悪臭があるとか文句を言う。ついにある日、自治会でその部屋を開けてみたら、何もないからっぽのきれいな部屋だったという。村上春樹の東京奇譚集にでも出そうな話だ。
いま、村上春樹とつい書いたけれど、この本に収められている不思議な感触の断片は、もしフィクションにできるなら村上春樹が書けそうだと思う。
わたしが一番気になった話。廃業したガソリンスタンドの建物の中に(乾燥に強い)ユッカの鉢植えがあり、完全に枯れている。外は雨が降っている。ユッカが完全に枯れるまでには相当な時間が流れていたはずだ、と作者は思う……。また、彼はある男をインタビューし、その男が犯罪のために10年間香港の刑務所にいたことを知る。その男の10年間と、それとは無関係に流れていた自分自身の10年のことを考える。時間の流れと人間の本来的な孤独を。「しかし私は、彼の十年は私の十年でもあった、というただそれだけのことが私と彼のあいだに、何らかの「会話」を、言葉にも感情にもよらない無音の対話を成立させているような気がするのだ。」うーん、この感覚、なぜだかよくわかる。<胸がかきむしられる>では強すぎる。<胸がぞわっとする>ぐらいな感覚だ。たぶんわからない人はわからないだろうが……。
そこからつづいて……ある地味な大学生が突然に大学を辞めるという。アメリカでロックスターになりたいから、そのために音楽の専門学校に入ったり、英語の勉強をしたいという。作者は、その学生が希望どおりに成功する可能性は非常に低いことを承知しながらも、それでもやったらいいんじゃないかと思うのだ。何者かになれず、失敗する人生は多いが、多くの失敗者がいて初めて成功する天才も出るのだから。そして、数多くの失敗した人生は、成功した人生とは本当に無関係なのだろうか。
「いつも私の頭の片隅にあるのは、私たちの無意味な人生が、自分にはまったく知りえないどこか遠い、高いところで、誰かにとって意味があるのかもしれない、ということだ。」
同じ地上で同じように流れる時間を生きているわたしたちは、お互いにまったく無関係でいるようで、実は「無音の対話」をしながら微かに作用し合っているのかもしれない、と思った。
「何が書いてあるのかはっきりとわからないが、妙に記憶に残る」この本を読んで共感する人と話がしてみたい。お酒でも飲みながら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
