
【書籍紹介】 永守流 経営とお金の原則 "生きる伝説の経営者"
今回は僕が尊敬する経営者の一人、日本電産(現:Nidec)/永守さんの著書のご紹介。
本書を読む前、永守さんは見た目通りの溢れ出る情熱で突き進んできた人だと思っていました。高い志を掲げ、ハードワークでベンチャーから日本を代表する大企業を一代築いた、凄いパワーの持ち主。しかし本書を読んで、永守さんは、「お金周りの戦略、財務の戦略が不可欠」と語気を強めて言うほど、非常に財務戦略を大切にする経営者でもあると分かりました。
それは序章でも書かれていた、創業間もない時、不渡で資本金上回る不渡手形を食らい、
一時は真剣に自殺を考えた所まで追い詰められた強烈な経験が影響しています。
本書を読むと、会社を潰さない為の財務戦略を深く学ぶ事が出来ます。
この本を読んで欲しい人
自分の会社を立ち上げたいと考えている人
財務戦略を考える機会がある人
金融機関で働いている人
M&Aを検討している人
日本電産へ投資している/しようと考えている人
大学の教授が説く、うわべ的な話ではなく、実践を通じ自身で経験したエピソードばかりで凄くリアル。独特な語り口調で書かれていて読みやすく一気に読んでしまいました。
今回は本書の中で特に印書に残った内容につき、自分の感想も交えて書いていきたいと思います。
目次について
本の目次は以下のとおり
序 章 お金の戦略が必要だ
第1章 キャッシュこそ企業価値の源泉
第2章 会社を成長へ導く財務戦略
第3章 創業期の資金の集め方
第4章 金融機関とどう付き合うか
第5章 取引先を見極める方法
第6章 チャレンジと財務バランス
第7章 いざ株式上場 規律の中で鍛える
第8章 M&Aをどう活用するか
第9章 海外展開は飛躍のチャンス
第10章 波乱の時代をどう乗り切るか
どの章も読みごたえ抜群。優れた経営者の経験と知恵が凝縮されたものが1,600円(+税)で読めるのは、本当に本はコスパ高いし、得られるものが多いとつくづく感じます。こういう本との出会いがあるから読書はやめられません!!
先日、帰りの電車で席の向かいに座ったおじさんが同じ本を読んでおり、嬉しくておじさんを見ながらニコニコしていました(笑)
第1章 お金の戦略が必要だ
財務への無頓着が破綻を招く
永守さんは自身で「怖がり」と自負しています。しかし経営者の素養として、この怖がり、臆病さは極めて重要と仰っています。
なぜなら日本電産と同時期に旗揚げした会社は多くが退出しており、破綻した企業が共通するのはみな経営や財務の数字に弱かったから。
日本電産と言えば、シャープや日産など外部から後継者としての人材をヘッドハンティングする事で有名ですが、多くの候補者と採用面談を行うと、総じて財務に弱い人が多いと言います。財務をきちんと理解できていない候補者は「そろばんを持っていない経営者」であるとし、そんな人に会社を任せるわけにはいかないと強烈なダメ出し。
経営者はバランスシートを頭に叩き込む必要がある。担当者に聞かないと分からないようでは経営者失格と語気を強めます。
とりわけ創業5~10年くらいまでの間は以下について、よくよく認識しておく
バランスシートの数字をソラで言えることが大切
最後に鍵を握るのはキャッシュ(現金)
バランスシートの資産サイドの現預金がいくらあるのか
すぐに現金化できない売掛金や在庫が膨らみ過ぎていないか
負債サイドで1年以内に返済する必要のある借入金の規模はどれ位か
そして、投資計画などを考える上でもバランスシートにどのような影響が出るのかしっかり捉える。数値面で考える事は非常に重要。認識すべき内容は以下のとおり
研究開発投資をする場合、投じたお金を将来どのように回収するのか
無理な投資でバランスシートが大きく崩れないか
自己資本比率はどうなるか
負債は増え過ぎないか
過剰に意識すると攻めの投資が出来なくなるが回復にどれくらい時間がかかるのか
会社全体の財務状況を把握し、どれだけの資金を将来への投資に向け、それをどう回収するのか、経営者はそのメカニズムを瞬間的に判断できる力を持っていなければいけない。
株式投資で学んだお金の仕組み
実は永守さんは16歳から投資を始めた生粋の投資家。これを認識している人はあまりいないのでは❓僕自身が本書を読むまで知りませんでした。
少年の時から起業したい考えがあり、株式投資もその準備で始めたとの事。株式投資をやると感覚で分かってくるが、どういう企業の株価が上がるのか、下がるのか非常に敏感に感じ、勉強するようになります。結果がダイレクトに自分へ帰ってくるのが株式投資の醍醐味であり、恐ろしい所でもある。
若き永守さんも株式投資をやりながらバランスシートの見かたが理解出来るようになったという。しかしながら投資は全てが順風満帆ではなく、空売りで損失を出す等の失敗も多く経験し、原則を定めた。それは以下2点。
・信用取引には手を出さない
・成長が見込める銘柄への長期投資
永守さんは、日本に財務が弱い経営者が多いのは日本の教育にも原因があるという。学校でお金の仕組みをきちんと教えることが少なく、経営者を育てようというプログラムも無い。お金のことを考えるのは恥だといった風潮すらある。
正しく、個人投資家界隈で言われている事と同じ事を仰っています。日本人のお金に対する理解力を上げていく事は個人は勿論、会社員、経営者、日本で働くすべての人の底力を上げる事に繋がるのだと思います。

第5章 取引先を見極める方法

日本電産を創業し5年程の間に3度、会社をつぶしかねない危機に陥った。理由は全て取引先企業が倒産し、手形が不渡りになった事。冒頭にもあったが創業期にお金周りで非常に苦労された事から、付き合う取引先を選定する上の注意点、考え方を詳しく語られています。
注文は取りにくい所から
優良企業ほど敷居が高く、新たに取引を始めるのは極めて難しい。そしていざ取引が始まっても、色々な面でのレベルの向上も要求される。工場にもよりいい設備、機械を入れる必要も出てくる。
それでも永守さんは、そういう事を一つひとつクリアしていくうちに、自分たち自身が鍛えられ、経営体質の強化につながったという。
新規取引、経営者が自ら見極め
永守さんは、新規取引を始めるにあたっては、経営者が自らの目で相手先をしっかり調査する必要があるという。その際には自分がその会社の経営者になったつもりで、気が付く不備な点を挙げる。
★チェックポイント★
売上の規模に比べ立派な建物に入っている会社
工場が立派過ぎる会社
応接室の灰皿をチェック
蜘蛛の巣張ってる、窓ガラスの割れ
社長の出社時間
最初の2つは本業以外の所に余計なお金を使っている可能性がある為、チェックすべきポイントとして挙げている。
応接室の灰皿チェックは、その会社の性格を図る上のチェックポイント。永守さんは「初めて訪問する会社へは午前10時に行け」と指示するとの事。前日の灰皿がまだゴミが残っているのは、仕事がいい加減、おおざっぱな可能性が高いと。また蜘蛛の巣・窓ガラスの割れ確認は、細かな事に気を配れるほど余裕がないの会社なのだと見抜く為のポイント。
社長の出社時間が遅い会社ほど取引先として危険と考える。永守さんは朝の早い会社は何か問題があっても必ず解決できるパワーがあると考える。社長が率先して会社へ早く来る会社は経営力が強いというのが経験則から分かっているという。
このように、ほんの些細なことではあるけれど、実態を知るのに気に掛けるポイントを整理すると、とても納得感がある。ご自身の働いている会社にあてはめて考えると・・・取引先から見て、自分の会社がどう見られているのか、そういう視点を持つと面白いと思います。
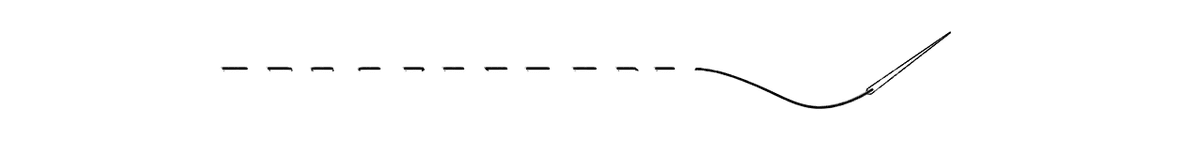
第8章 M&Aをどう活用するか
これまで60社以上のM&Aを成功させ、世界40数か国・地域でビジネスを展開する日本電産グループ。日本企業には難しいとされるM&Aを成功に導く秘訣とは❓永守さんが定める原則は非常に参考になります。
成功の3条件
永守さんが決めている「M&A成功の3条件」
1.高い価格で買わない
2.ポリシー
3.シナジー
この中で一番重要と考えるのは①高い価格で買わない事。M&A失敗の大きな要因は高すぎる価格で買っている為だという。その為、買収価格には徹底的にこだわる。適正価格を十分に見極め、折り合いがつかなければ買わない。
・重視する数値はEBITDA(Earnings Before Interest, Depereciation and Amortization)倍率という指標。
・EBITDA=税引前利益+支払利息+減価償却
永守さんは買収額がEBITDAの10倍を超えるものには手を出さないと決めているという。買収価格が高いというのは、企業価値に対するプレミアム分、つまり「のれん代」が高いという意味。それだけで買収後にのれんの価値を引き下げる減損処理を実施するリスクが高まる。
永守さんは日本企業のM&Aの殆どが高い価格で買っていると指摘する。以前永守さんがソフトバンクの社外取締役を務めていた際、英国のアームを3兆円で買収することになり、日本電産なら3,000億円でも買わないと言って紙面をにぎわせた事を思い出しました。
永守さんの頭の中には常に理想とする事業ポートフォリオがあり、その完成図に近づける為に、ジグソーパズルのピースを埋める感覚で会社を買うと言います。単に規模を大きくするのではなく、より強い企業グループを作るところに重きを置いているのが素晴らしい。
買うと決めたら何年かけてでも
基本的には国内、海外問わず一流の企業からしか買わない方針。特にファンドが持っている会社はなるべく手を出さない。
これから買おうと思っている企業のトップに対して手紙を出す、「是非買わせてください」と提案。手紙の数は毎年、数十通にも及ぶ。すぐに成約に至る事は少ないが、ひとたび声をかけておくと、いざという時に向こうから最初に話が来ることがあるという。
実際、声をかけて何年もたってからM&Aに結び付けたケースは幾つかあり、2010年の米電機大手エマソン・エレクトリックのモーター事業は10年かけてグループ入りに至った。
M&Aの相手先を分析する時はバランスシートをじっくり読み込む。損益部分は悪くても立て直せるが、バランスシートの修正には時間がかかるから。ここでも永守さんは経営者はバランスシートを見てその本質を理解出来なければならないと主張する。特に資産の中身をきちんと分析出来るかが重要。
何処を直せば会社が良くなるか、健全な財務状況になるにはどれくらいの時間がかかるのか、はっきりわからないうちは買わない。
PMIがM&Aの8割を占める
M&Aの成功のカギを握るのは買収後。タイトルにあるPMIとは、Post-Merger Integrationの略。つまり、M&A(合併・買収)後の統合プロセスを指す。
買うまでが2割、買ってからが8割。
どこまでシナジーを高められるかは、買ってからの施策で決まる。PMIをスムーズに進める為には、「ポリシーが同じ会社」、「シナジーが得やすい会社」を選ぶ事が重要。前述で言った「M&A成功の3条件」の価格以外のポイント2つ。
PMIを行う上で絶対欠かせないのが、相手先の経営陣と社員の意識改革。実施するのは2つ。「赤字は罪悪である」との意識を植え付け、そして、日本電産流の「3Q6S」を徹底する。
3Q6Sとは、3つのQualityと、6つの日本語のSから始まる言葉
・3Q 「良い社員」、「良い会社」、「良い製品」」
・6S 「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」、「作法」、「しつけ」
6Sを徹底して3Qを目指す「3Q6S」は日本電産の基本理念。これを徹底すると再建に繋がるという。6Sにより工具や物品がきちんと整理されると、無駄な作業が無くなる。社員が6Sを常に意識すると作業が効率化されコスト削減に繋がる。社員の士気も高まり、おのずと収益も上がるという。
そして大事な事をもう一つ。それは「買収先への敬意を忘れない」こと。原則として経営陣の入れ替えはせず、人員整理にも手を付けない。各社の個性と独立意識を大事にするため、基本的に会社のブランドは残す。
みんなそれぞれにプライドを持っているのだから、直ぐに名前を消す、合併することをしてはいけない。資本の論理という刀は相手の前で決して抜いてはいけないと強調する。
45分と少々長いですが、永守さんの実際の声も聴ける企業な講演映像あったので、時間ある方は是非ご覧あれ。話術も独特ですが、非常に上手で引き込まれます。うーん、実際生で講演を聞いてみたいものです。

第10章 波乱の時代をどう乗り切るか

創業し約50年が経過。今や日本を代表する大企業へと成長した日本電産。しかし永守さんは、今かつてない緊張感をもって経営にあたっているという。
これ程変化の激しい時代はかつて経験が無く、今は気を抜くと落城は3時間、いやほんの3分あれば十分ではないかと思うほど。
一方で変化の時代はチャンスの時代とも考え、ベンチャーや規模が小さい企業でも飛躍の可能性があると感じているという。最終章では、変化の時代を勝ち抜き、飛躍するための戦略、心構えについて詳しく書かれている。
トップの心構え
永守さんは、同じ京都に本社を構える、同じくベンチャーから大企業へと育てた偉大な2名の経営者から多大な影響を受けています。その2名とは、
オムロン創業者 立石一真氏
京セラ創業者 稲盛和夫氏
立石氏からは創業者の執念、覚悟を学んだと言います。
エピソードとして立石氏が創業間もない企業を支援する日本初の民間ベンチャーキャピタルのトップを務めていた頃、創業間もない永守さんはダメ元で出資をお願いし小額ではあるものの出資に至った。それがきっかけで周りの見る目が変わり銀行からの借入でも有利に働いたという。
立石氏からお昼ご飯に誘われ会社に呼ばれた時、ちょうどオムロンが自動改札機の開発・実用化を進めていた頃で、「もう無理です。限界です」と報告する部下に対し、立石氏は「出来るはずだ」と決して譲らない声が聞こえてきたと。結局部下との話を終えたのはお昼ご飯をすっかり過ぎた午後3時過ぎだったというエピソードは非常に印象に残った。
ベンチャー企業は無から有を生み出す。簡単ではないし、何より創業者があきらめると出来るものも出来なくなる。その時、創業者の執念、覚悟を痛いほど学んだという。
稲盛氏は年齢が永守さんより一回り上。同じ創業経営者として尊敬すると共に、超えるべきライバルとして常に闘争心を燃やしてきたという。
永守さんが驚いたのは、稲盛さんのハードワークぶり。京都銀行からの紹介で2人で会食をした際、会食が終わっても当然のように会社に帰って仕事をする。成長企業のトップはこうでなければと、その時更に仕事への情熱を燃やしたと言います。
日本電産の経営の原点である「三大精神」
・「情熱、熱意、執念」
・「知的ハードワーキング」
・「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」
この原則も、京セラを追いかける中で出来たものだという。よきライバル、指針があるのは自身の成長にとっても素晴らしい事です。
この章での好きな言葉
目標は高く持つ事をとても大事にしている。それは高い壁に挑んでいく事で人は鍛えられる。上場して満足するのではなく、より高い山を目指す事だ。時には失敗もあるだろうが、本当に強い人間は挫折の数と深さから生み出される。挑戦を続ける中で尊敬する経営者、闘争心を刺激するようなライバルに出会えれば尚よいだろう
心に刻みたい深い言葉です。
経営者のための10か条
以下10か条につき、タイトルのみ記載します。
一つずつ詳細書かれているので気になる方は是非本書お読み下さい。これだけでも物凄い価値があると僕は思います。
ベンチャー経営者の資質を鍛えよう
何でもするという覚悟を
スペシャルマーケットを狙え
技術だけでは会社は伸びない
基本方針は常に反芻・確認する
創業後5年間の財務戦略は安全第一
社員に数字感覚を植え付ける
よきハンターはよき調教師たれ
コスト意識を社内に徹底させる
経営者としての倫理を守る

まとめ
今回は日本電産創業者/永守さんの著書を紹介しました。
ベンチャーから中堅、大企業へと一代で駆け抜けてこられた、日本の社長が選ぶNo.1社長にも選ばれた、永守さんならではの自身の豊富な経験に基づく非常に実践的で説得感のある提言ばかりでした。
グダグダ京都銀行とネタにしていた駆け出しの時に助けてもらった京都銀行には今でも非常に恩を感じていて、最近グダグダ言わなくなったので言ってくれと伝えているという面白エピソードがあったりと、思わずにやっと笑ってしまう内容も盛り沢山です。
今回は、ほんの一部の紹介になっているので気なる方は是非手に取ってお読み下さい。読み物としても単純に面白いです^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
