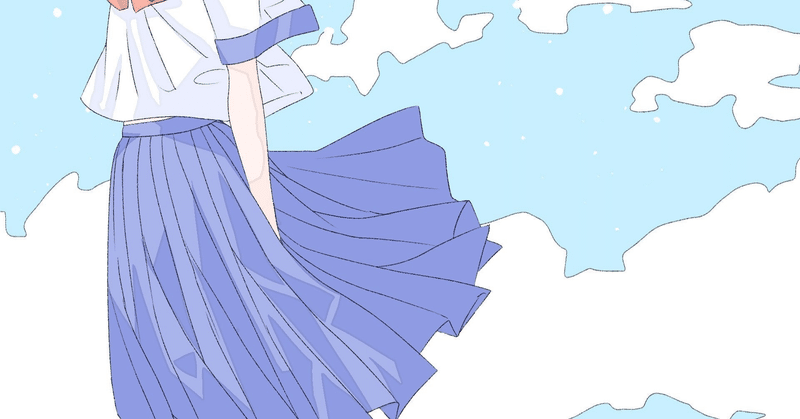
【掌編小説】ある夏の回想録
1999年の夏、わたしたちは罪を犯した。世間がノストラダムスの終末論で騒がしいなか、わたしたちは陽炎みたいに揺らいでいた。
わたしは、市街地から30分ほど離れた霊園に来ている。ヒンヤリとしているから不思議だ。あれだけ自己主張の強い蝉たちが大人しいのは、その異質さからなのかもしれない。わたしはお墓に手を合わせ、祈りを捧げた。
(ユリカ…)
10年前のあの夏以来、ユリカはわたしの心の中にひっそりと影を潜め住み着いている。
はじめはちょっとした悪戯感覚だった。わたしとユリカは、彼女の母の飲み物に朝顔の種を擦りおろした粉を混ぜた。
「いい気味。1時間近くトイレにこもってたわ。お陰でトイレが使えなくてコンビニに行くハメになったけど」
ユリカは甘美な笑みを浮かべていった。
(その笑顔をもっと見たい…)
ユリカの笑顔に惹かれていた。
わたしたちは放課後、よく学校の図書館で過ごした。ユリカは何やら小難しい専門書を持ってきてはわたしに相談した。
「これはどうかな?」
「これは効きそうね」
真っ白な歯を見せ笑いながらいうのだ。そして何度も試し、ユリカの母親が苦しむ様子を見てはふたりして笑った。
(いつか飽きるよね?)
不安がるわたしの想いに反して、ユリカはいたって真面目に、本気に母親を葬ろうとしていた。
夏休みに入ったある夜、わたしはユリカの家に泊まることになった。その日、台風13号が猛威を振るい、ユリカの住む小さな平屋はガタガタと震え今にも吹き飛んでしまいそうだった。
ユリカの母は夕飯をご馳走してくれた。タラコのパスタとキノコのスープ。煩雑な盛り付けが味の薄さを際立たせていた。
まもなく日付が変わる頃。わたしたちはいつものように「悪ふざけ」をした。ユリカの母は身体が弱いのか、複数の薬を服用していた。その割にかなりの量のお酒を飲み、キツめのタバコを毎日2箱吸うヘビースモーカー。お酒を煽り、そのままテーブルで寝るらしかった。
わたしたちは、いつも飲んでる薬をお菓子のラムネに変えた。子供騙しのように思ったけど、お酒のせいで判断は鈍っているようだった。なんの疑いもせず薬を飲み酒を飲み、眠りについた。
次の日の朝、ユリカが声をかけても起きないので揺すってみると、華奢で枯れ木のようなユリカの母は崩れ落ちた。
「みっともないわね…」
ユリカは笑い声を殺して呟いた。
ユリカはカーテンを開けた。台風は去り、雲の切間から朝日が部屋中に差し込んでくる。光を浴びたユリカの栗色の長髪が、キラキラとキレイだった。
「お母さん、死んじゃったね」
わたしがいうと、ユリカは頷いた。
「あいつ、わたしにこういったのよ…」
ユリカは、枯れ葉で散乱した庭を眺めながらいった。
「あんたはわたしの何がわかるの?社会を知らないガキのくせに」
ユリカは顔を歪めていった。一言一言に憎しみが込められている。
「そのとき思ったの。消さなきゃって…」
ユリカは凛としていた。けれど、どことなく淋しさがあった。ぶつける矛先が無くなったせいなのかもしれない。
しばらくして、ユリカは救急に連絡した。それからは慌ただしかった。台風が戻ってきたみたいに。いつのまにか、夏休みは終わった。
夏休みが明けると、ユリカは学校に来なかった。隣町にある祖母の家に転校したらしい。年が明けて2000年になっても、結局世界は滅びなかった。あれほど騒いでいた世間の興味はゴシップに移っていた。
桜が芽吹く頃、風の便りでユリカが亡くなったことを知った。理由は知らない。
10年経った今でも、世界はあり続けている。姿を変えながらも、変わらないものを残しながら、無情にも変化し続けている。取り残された時代遅れの産物は、隅の方に追いやられてしまうだろう。
わたしは、毎年ここを訪れ祈り続ける。隅に追いやられ世間があの夏を忘れてしまっても、わたしたちの世界はここにまだある。
「ユリカ、また来るね」
わたしはひとりごちると、お墓を後にした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
