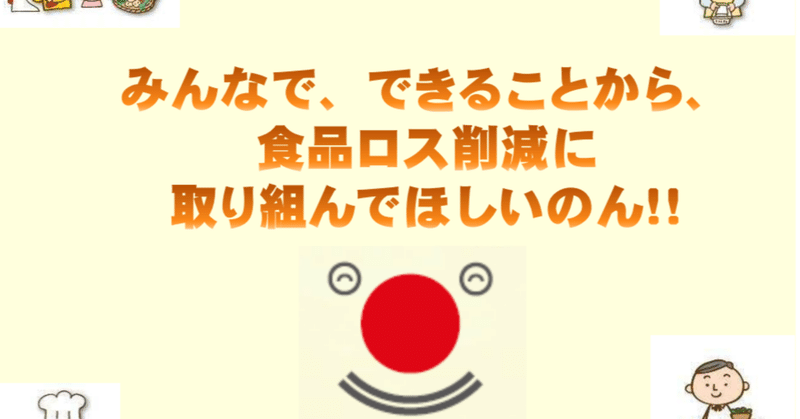
「食ロスを、ひもじい人へ」は、正解なようでちょっと間違い。
あまから手帖 連載「食のSDGs事典」2021年3月号より。バックナンバーはこちらから。
「フードバンク」というシステムのことを聞いたことがある人の多くは、「余っている食品を、困っている人へ」という循環だと思っているんじゃないだろうか。「バンク」という言葉が、そういう連想をひとり歩きさせてしまっているとも言える。(上のバナーは農林水産省の資料「フードバンクの現状について」。こういう論調が「ひとり歩き」を助長している)
前提になっているのは「食ロスの解消」ではなく、豊かと言われる世の中で、事情あって満足に食べられない人への「食支援」なのだ。
取材した「フードバンク関西」では、寄付された食べ物の引き取りや分配の仕事に、多くのボランティアスタッフが黙々と働いていた。
路上生活者から、食べ盛りの子供がいる家庭まで、食品を求めている人のニーズもさまざま。台所に電子レンジがあるのかないのか、食べる環境もそれぞれだ。食べ物を受け取る人への個々のきめ細やかなケア、梱包に添える温かい応援メッセージなどを見ていて、この活動が「いらない食べ物を循環させる」こととは全く違うことがわかった。
フードバンクでは食品の寄付を募っているが、中には開封済みや賞味期限切れなど、見るからに「いらない食品」を持ってくる人がいるそうだ。
人間にとって、食べることは平等に必要で、楽しいことのはずだ。
他人にもお腹いっぱい食べてもらいたいと思う気持ちで寄付をする行動は尊いが、そこに「不用品」という気持ちを混ぜこんでしまっては残念だ。
言葉尻だけの話ではない。
「余っている食品を、困っている人へ」ではなく、「必要としている人へ、適切に食を手渡す」ことが、フードバンクの活動なのだ。
ネットを見ると、いろんな団体が食支援の活動をしているようだ。気になるのが、子供の貧困をことさらアピールするコマーシャルを流して寄付を募っている団体もあることだ。
ママはシングルマザー。いつもお腹が空いていると感じている葵ちゃん、、、。泣かせるCMに「かわいそう」という感情を掻き立てられたら、何かしたいと思って当然なのだが、そこで財布に余っている小銭を寄付して「かわいそう」という気持ちをスッキリさせることは、正解なようでちょっと間違いかもしれない。
それって、自分が台所をスッキリするために、始末に困る食べ残しを寄付することに、似てないか?
世知辛い世の中である。
活動内容などは自身で調べて、共感できる団体と関係をつくることをおすすめする。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
