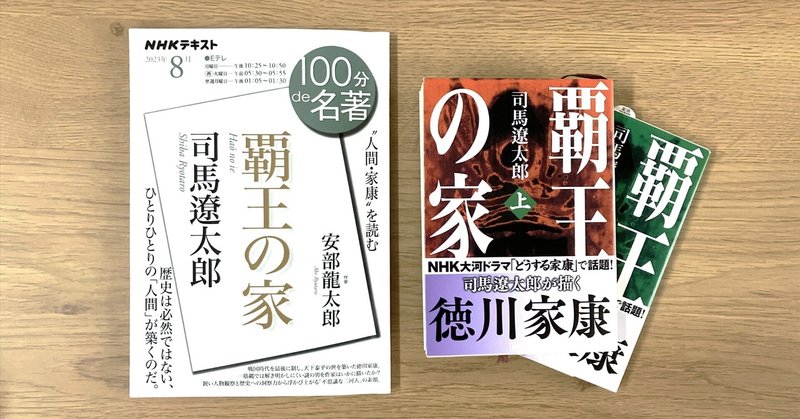
歴史小説家や歴史愛好家から学ぶアイドルの推し方
はじめに
2023年8月にEテレの番組「100分de名著」で「覇王の家」が紹介されました。「覇王の家」は、司馬遼太郎が徳川家康を主人公に書いた小説です。司馬作品を読んだことがないわたしですが、ちょうどそのころ大河ドラマの展開がよくわかんなくなってきたところだったので、見てみることにしました。その結果、指南役の安部龍太郎さんのお話が聞きやすくて楽しかったですし、わたしなりの気づきもいくつか持てました。それらの気づきの中には、ことしの大河ドラマがわたしが思ってたのと違うと感じた理由もあるのですが、それは、きょうやっと読み始めた「覇王の家」を読み終えた後にまた別のnoteにしたいと思います(いつ読み終えられるか不明ですが)。ここで書きたいのは、歴史フィクションと推し活の類似点です。ハア?何言ってんの?って思われるかもしれませんが、自分なりにけっこうまじめに考えました。
わたしはふだん、KPOPグループのTOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)を推しています。このグループのファンはMOA(モア)と呼ばれています。そして、100分de名著を見たあと、「司馬遼太郎が『覇王の家』を書いたときに考えていたかもしれないこと」と「MOAがTOMORROW X TOGETHERについてnoteやSNSで語るときに考えているかもしれないこと」には共通点があるんじゃないかなと思いました。どちらも根底には「その人がどんな人なのか解き明かしたい」、「わからないけれど、わかりたいので、何とか工夫して考えてみる」という気持ちがあると思いました。
共通点Ⅰ. すべては人物造形から始まる
「決めつけ」に納得できたとき、物語はめっちゃおもしろく感じるようになる
歴史上の偉人は、本人によって書かれた文、家来がしたためた記録などが残っていることがあり、そこから大まかな出来事がわかっています。しかし、日々何を考えて、家臣や家族とどんな会話をして過ごしていたのかまでは細かく残っていません。だからこそ、大河ドラマをはじめ時代劇のフィクションでは、作家があらゆる想像をして人物像を築き上げていきます。「覇王の家」の場合、登場人物の性格や思考の「決めつけ」が大胆に行われているのですが、この決めつけ具合が絶妙なために魅力的な作品になっているというようなことを、阿部さんはおっしゃっていたと思います。実在した人物だからといって、わかっていることを羅列するだけではおもしろい時代小説にはなりません。人物にキャラを与えて、断片と断片をつなぐストーリーをつくって入れるからこそ、続きが気になる物語になると思います。
MOAの場合でも、同様に、多くのファンがTOMORROW X TOGETHER(以下TXT)のメンバーたちの人物造形を無意識にしていると思います。家康と違ってTXTは今わたしたちと同じ時代に生きているわけですが、個人的に出会って話を聞くことなど不可能という点では、過去の偉人と同じくらい遠いと言えると思います。そこで、MOAも、ある程度メンバーの人格の「決めつけ」を行い、自分の中のTXT像をより魅力的なものにしようとしていると思います。そして、自分と比較的近い人物造形をしたファン同士がSNS上で仲良くなり、それを前提に会話がはずんでいくという構図があります。これは歴史ファンの方にも同様のことが言えそうな気がします。
生まれ育った地域による「決めつけ」
さきほど、「覇王の家」の場合、登場人物の性格や思考の「決めつけ」が大胆に行われていると書きましたが、この「決めつけ」の筆頭が「三河かたぎ」というものです。地域別の人の性質のあるあるみたいなもので「人国記」という文献に基づいているそうです。それによると、三河の人は誠実、忠実、洗練されてはいないが義に厚い、頑固、みたいな人だそうです。華やかな尾張商人とは根本的に考え方が違い、たいして肥沃でもない土地を懸命に耕し続けるような人みたいです。そして、家康や家臣団が何かを決断するたび、司馬遼太郎は「三河の人はそういう人だからそうする」という導き方をするそうです。けっこう強引な気もしますが、実際に「覇王の家」を少し読み始めてみたらこれがかなり納得でした。
そういえば、KPOPアイドルにもこういう決めつけはやってるなあと思いました。ジミンとジョングクは釜山の出身なので、口はうまくないが男気があり情に厚いとか、ユンギ、テテ、ボムギュを輩出したまちだから大邱は美男子が多いし、性質がおっとりしているとかはファンの間で言われていたりします。また、Z世代アイドルは幼いころIMF危機が起きたために、米国への移住政策が国によって進められたことから米国育ちの方がけっこういて、そういった人たちにはそのクラスタ特有の気質があるのではないかと考えるファンもいます。これもまた、「三河かたぎ」で人物造形していく手法と似ていておもしろいなあと思いました。
「決めつけ」にはこんな効果も
安部龍太郎さんのお話で「なるほど!!!!」って首もげそうなくらいうなづいたことのひとつが、「歴史小説家は、あまりにも真正面から対象人物に向き合ってしまうと、その存在の大きさに身動きがとれなくなってしまう」みたいなお話でした。そうならないために、あえて対象人物の捉え方に屈折を入れる、その一つが「決めつけ」ということだったと思います(解釈違ってたらすみません)。
これは、アイドルを推す場合にもあるような気がします。自分の推しがあまりにもかっこいい場合、もうライブを見ても曲を聞いても息が止まって「良い…」しか感想が出てこなくなります。なので、ファンは推しのちょっとおもしろい部分や笑えるような部分をクローズアップさせて語ったり、悲しんでいるシーンや泣いているシーンをわざと話題にしてみたり、赤ちゃん呼びしたり、かわいらしいファンアートを書いたり、いろいろな「決めつけ」を始めると思います。そうすることで呼吸ができるようになり、身動きがとれるようになって、「良い…」以外の感想を口に出せるようになってくるからなんだと思います。
共通点Ⅱ. 資料/史料の活用
人物造形のためにはいろいろな資料が用いられるのも似ているなと思います。
分類してみた
これは、わたしが勝手に考えた家康とTXTを知るために手がかりとなり得る資料の分類です。一応、1が一次史料と呼ばれる信憑性が高いもので、下にいくにつれて執筆者の主観の割合が高くなるように配置しました。

ここで思うのは、数字が大きくなって創作の度合いが高くなると価値が下がるかというと、必ずしもそうではないということです。家康に興味があるからといって最初から家康自筆の書状を読もうとする人は少ないと思います。それよりは、大河ドラマや歴史小説を鑑賞する人のほうが圧倒的に多いと思いますし、それが一番楽しいだろうと思います。また、コメディはとてもおもしろいので、そこが歴史にハマる入口だったという方も多いのではないかという意味で、コメディもとても重要な要素だと思います。
アイドルの推し方についても、案外、これと似たようなことが起こっている気がします。わたし自身、KPOPはBTSのDynamiteから好きになりましたが、当時KPOPのことも韓国語も何も知らなかったので、1に相当するコンテンツよりは、11に相当する布教動画と呼ばれるものをひたすら見ていました。布教動画とは、ファンが公式のコンテンツからここぞと思うシーンを勝手に切り張りしてつくった編集動画のことで、主にyoutubeにアップされています。これは、著作権的にはだいぶグレーというか厳密にはアウトなんでしょうけど、なにしろ、短時間でアイドルの魅力がばっちり伝わってくるのでとても人気があります。
ちなみに、TXTの1にあるWライブは、本人によるトークがその名の通りライブ配信されるので、全世界で時差なしで楽しめる最強一次史料コンテンツです。しかしながら、当然ですが、韓国語で行われています。なので、字幕がつく前にその動画を見ても、古文書の知識が何もない状態で家康の書状を見ているのと同じ状態です。一次史料だから何よりもいいのだ!なにはなくともまずは一次史料に当たれ!とは言えないこのような点もちょっと似てるなと思います。
8~11は個性が出てとっても楽しい
TXTの8、9、10、11については、それを書いている(語っている)MOAのタイプがもろに出てくるのでとても読むのが楽しいです。
たとえば、音楽に詳しいMOAなら、専門用語を用いながら彼らの曲を分析したり、実務に詳しいMOAなら、推しが勝てる投票方法や、本国イベントへの参加の仕方などを教えてくれたりします。こういうのは8に該当すると思います。あるいは、8と9のハイブリッド版みたいなnoteも多いと思います。
ちなみに、安部龍太郎さんは学生時代に工業を履修して、技術やIT産業や都市計画などにお詳しいので、そのような切り口で歴史を考えるそうです。そういえば、テレビでよく見かける磯田道史さんも、経済学の教授についたからか経済や商いの観点から書いた小説があります。このように、同じ歴史を語るにもどのような着眼点で始めるかでぜんぜん違うものが出来上がると思います。これと同じことをMOAもまたしていると思います。文学に詳しいMOA、映画に詳しいMOA、ファッションに詳しいMOA、ヒップホップに詳しいMOA、洋楽に詳しいMOA、ダンスに詳しいMOA、韓国語に詳しいMOA、いろんなMOAがいて、その人なりのとっかかりから書かれるnoteやブログは同じものがなく、読んでいて本当に楽しいです。
やっぱり9が一番盛り上がる
そして、歴史でもアイドルでも盛り上がるのはやはり9だと思います。作家やファンが、対象人物についてどういう思いを持ち、どういう言葉でそれを表したいか、人に伝えたいのかが滲み出てくるのが9です。各種資料も活用しつつ、書く人の人生観みたいなものまでが関係してくると思うので、書くかいも読むかいもあると思います。司馬遼太郎の場合、従軍経験があるので戦における部隊の構造について思うところや、人はどうすればもっとましに生きられるのだろうかという問いへの欲求が強く、作品にも影響しているのではないか、ということを安部龍太郎さんは言っていました。これはMOAにもあてはまる気がします。そのMOAがこれまでどのように生きてきたのか、どんな楽しい経験、つらい経験があって今に至ったのか、直接は書かないにしても、それがベースになって書く内容や言葉が選ばれていると思います。
11については、さきにも述べましたが、案外重要な役割をしていると感じます。
注意点(自戒を込めて)
最後に、歴史でもアイドルでも気をつけないといけない点があると思いました。それは、自分の得た情報はどこから来たものであるかを常に理解しておくことです。表で言う1の知識を持つ人と9の知識を持つ人の話がかみ合わないということはよく起きていると思います。ただし、前提さえ事前にはっきりさせておけば、自分の知らない区分の話を聞くのはとても楽しい経験だと思います。
あとがき
歴史が好きな方の話を聞いていると、歴史を深堀りしていく作業は、たったひとつだけ存在する「事実」を発見するためだけにおこなっているわけではないということがよくわかります。大切なのは、そこを目指してあれこれ調べること、考えることのようです。それに、なにより、歴史の「事実」というのは、原油やレアメタルのように地中を掘って当てれば出会えるようなものではないということを多くの歴史愛好家の方がおっしゃっていると思います。実際の秘宝のようにどこかまだ誰も辿り着いてない場所にひっそりと「事実」が存在しているわけではなく、当然、それを発見することもできないということです。(もちろん新史料などが発見されて、個別のシーンのあらたな解釈が生まれることは多々あるようですが、それひとつで全体の流れがすべて解明されるわけではないです。)
アイドルを推すこともこれと似ているような気がします。カンテヒョンは本当はどんな性格なのか。本当に知性派なのか。本当にあんなにかわいいのか。これを崩しようのないパーフェクトな理論でファンが証明し、結論づける方法は今のところないと思います。だけど、大切なのは、「事実」を見つけることや結論を出すことではなく、カンテヒョンがしゃべったならそれを聞き、カンテヒョンが踊ったならそれを見て、カンテヒョンが歌ったならそれをうっとりと鑑賞し、「やっぱりカンテヒョンかっこいいわあ…好き…」と楽しむことだと思います。
おわり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
