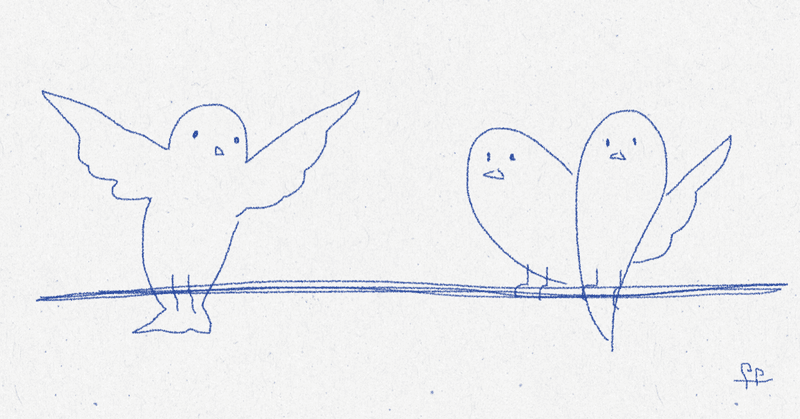
「ご縁と呼ぶにはあまりにも」
もしかして、私は途方もないことをしているのでは、そんなことを思ったのは短大2年生の夏頃だった。
2003年。時はまさに、就職氷河期と呼ばれる時代だった。
出しても出しても通らないエントリーシート、運よく通った書類審査も面接で振り落とされる。大口採用をしているという企業ならどうにか紛れ込めるんではないか、という甘い期待を頼りにかたっぱしから受けて、かたっぱしから玉砕していた。
卒業が迫る中、内定がひとつも出ない。
このまま私はどこへ行くのか誰か教えてほしかった。
差し出した自分を突き返されるたびに、自分が剥がれ落ちていく気がした。自分がどんどんすり減って小さくなっていく。そのうち小さなお豆みたいになって、得体のしれないなにかにぱくんと食べられてしまいそう。
焦る気持ちでドアをたたいた大学の就職課で職員さんに勧められるまま、とある小さな出版社に履歴書を持参したのが8月の下旬ごろ。
就職課というのは社会で言うところのハローワークみたいなところ。書棚には求人票がぎっちり詰まっていて、カウンターには職員さんが鎮座している。
これまでも就職課へ求人票を見に行ったことはあったけれど、職員さんとお話をしたことがなかった。空っぽな私に対する的を得たダメ出しを頂くような気がしてどうにも恐ろしかったし、なんかこう、人見知りしちゃうところってあるじゃない。
*
呼び止められて就職活動の進捗を聞かれた。
あまりうまくいっていない旨伝えると、「まあ座って」と職員さんと対峙する形になる。
アルバイトはなにをしているのかと尋ねられて、当時やっていた家庭教師の話を少しすると、「そのことを履歴書に書いてみたら?」と言われた。
胸を張れる資格や賞でもないそんなことを書いてもいいのかと驚いたけれど、「そういうことでいい」らしい。
あとは、句読点の書き方が少し大きいからもっと小さく書くように言われた。そんなところを見るのか、と驚いた。
「ここは初任給がいいから、とりあえずここを受けてみたら? 締め切りが近いから、電話で問い合わせて、受け付けてもらえそうなら郵送しないで直接履歴書を持っていきなさい」
非常にひねくれた考えかもしれないが、就職課でそんなふうに具体的にどうこうしてくれるとは思っていなかった。内定がもらえないのは自分に責任があって、それは私の問題だから、自分で何とかしないといけないと思っていた。こうして誰かが手を引いてくれるなんて想像もしていなかった。
そんな運びであれよあれよと、くだんの出版社へ履歴書を持っていくことになったのだった。
*
その日はとても暑い日で、地下鉄を降りたら日差しがあまりに強くて、日傘をさした。
閑静な街の一角にある小さな社屋の小さな出版社だった。建物の周囲を背が高くて尖った植樹がぐるりと囲んでいて、なんだか要塞みたいだなと思った。
少し不気味だなと思いながらも、なぜだろう、ふと「ここで働くような気がする」と思った。
ことごとく不採用通知を受け取っていたのにどうしてそんなことを思ったのか自分でもわからない。けれど後日、筆記試験を受けた時には、それが確信に近くなっていた。ではその筆記試験が抜群にできたかと言われたら全然そんなことはなく、「ルネッサンス期の三大発明を書きなさい」という設問に苦肉の策で「じょうききかん」と平仮名で書いたと記憶している。せめて漢字で書いたらどうか。そして、後日、家庭教師の生徒に「活版印刷と、羅針盤と、火薬だよ」と教えてもらった。こんな先生で生徒がかわいそう。
どういうわけか、そんな筆記試験も通過して、後日面接の案内が届いた。
*
静かすぎるロビーの椅子に座って呼ばれるのを待った。
改めて見ると、要塞の中は清潔だけれどお世辞にもおしゃれとは言えなかった。置かれている観葉植物は銀行や役所にあるような、どしっとした緑が濃いあれだし、床にはグレーのみっしり目が詰まった不愛想な絨毯が敷き詰められている。装飾らしいものはなにもなく、あるのは白い壁と、小学校みたいな白い蛍光灯と、白い長机と私だけ。まるで無機質で白い箱の中にいるみたいだった。
ぼうっと座っていると一度だけ、台車に本をたくさん載せた女の人がロビーを横切って行った。
ありていに言えば、総じて地味な雰囲気。オープンなオフィスでカジュアルスタイルの女性社員がコーヒーを片手に談笑する、そんな都会の会社からは程遠い。
それでもなぜだろう、確信は強まっていく。自信ではなくて、願望でもない。「ここで働く気がする」という思いが頭の中にふわふわとまとわりついていた。
名前を呼ばれて面接室のドアを開けた瞬間に、「知ってる人たちだ」と思った。もちろん、全員初対面に違いない。
彼らはそう、私が今まで出会ってきた中年男教師を集めて捏ねて、等分したみたいな、平均的な男性教師のような風貌をしていた。
今日まで面接を受けてきた会社では、ポロシャツや、カンパニーカラーを前面に出したユニフォームを着た、若い社員が出迎えてくれた。もちろんスーツの方もいらしたけれど、みんなはつらつとした、活気ある若者という感じだった。
だけど、今目の前にいる彼らは確かに私が見たことがある、既視感しかない中年男性。古文の先生と数学の先生と化学の先生と教頭先生を混ぜて慣らしたよう。
にこりともしないし、頭髪が少し薄いし、四角い眼鏡をかけていて、こんなの安堵しかない。
そんなわけで、緊張することもなく、よどみなくぺらぺらと面接を終え、すっきりとした気持ちで帰宅した。
後日、呼ばれた役員面接では先の面接と同じ面接官の男性数名に挟まれて、いかにも「社長です」といった風情のおじいちゃんが腰かけていた。
こちらもまた、「どこかで一度お会いしたことが」と思わせる、なじみある風貌をしていた。
おじいちゃんは履歴書を一瞥して「東大阪に住んでるんか」と言った。
いたいけな就活生の私は元気にはきはきと「はい!」と答える。
「てえことは、大学が○○にあるから~……京阪電車に乗るんかな」
と路線の話を始めるおじいちゃん。
もちろんいたいけでフレッシュなので
「はい!学研都市線に乗って、京阪電車に乗っています!」
と答える。
おじいちゃんは「いやでも、こっち回りでいけば乗り換えが△△駅になって近いではないんかな」
と、指をくるくる動かして路線の説明をし始めた。
このあたりで私はなにが始まったのかわからなくなっていたのだけど、おじいちゃんは「こう回りではなくて、こっち回りで通学してるんやな。こっちじゃなくて、こっち」とさらに指を大きくぐるぐる動かした。
こっちがどっちで、どっちがこっちなのか分からないし、なんとお返事していいのか困ってしまった。
なにかしらの力を試されているんだろうか、と思ったけれど、おじいちゃんの両サイドの眼鏡をかけた面接官の方たちが「そろそろやめてくれないかな」という雰囲気を隠す様子もなかったので、相槌を打ってなんとかその場をやり過ごした。おじいちゃんがご機嫌なことだけが救いだった。
そのあと、「目、悪い?」と聞かれて、いたいけな就活生は「はい!コンタクトレンズをつけています!夜は眼鏡です」と答えることになる。
入社して知ったのだけど、ほとんどの先輩がその質問をされているらしい。理由はいまだにわからない。
後日、最終面接を通過した旨の通知が届き、無事内定をいただいた。
あんなに内定をもらえずに苦労したというのに、感慨もなく「やはり」と思ったので図々しいにもほどがあると思う。
*
憧れたのは、現代的なおしゃれなオフィスだった。一人一台ノートPCをもっていて、「座席は決まっていません。その日の気分で好きな場所で仕事をするんです」みたいな会社だった。
理想とはかけ離れた、総じて地味な会社だったけれど、なぜか居心地がよくて、結婚して三重に引っ越すまでの5年と数か月お世話になった。
入社してみて、想像をはるかに超えるほどの保守的さに驚かされることになるのだけど、そのことに関してはまた次回。
理想とかけ離れたからって別に不幸になるわけでもがっかりすることもなかったし、日々はそれなりに憂鬱でそれなりに愉快だった。
初任給だけに釣られて、ふらふらと入社試験を受けたけれど、空調の温度設定が夏も冬も極端に低いこと以外、恐ろしいほど不満もなく、そこそこ健やかに働いていたと思う。
私が優秀な社員だったかは別として。
それもまた次回。ひどい有様だったということだけ書いておく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
