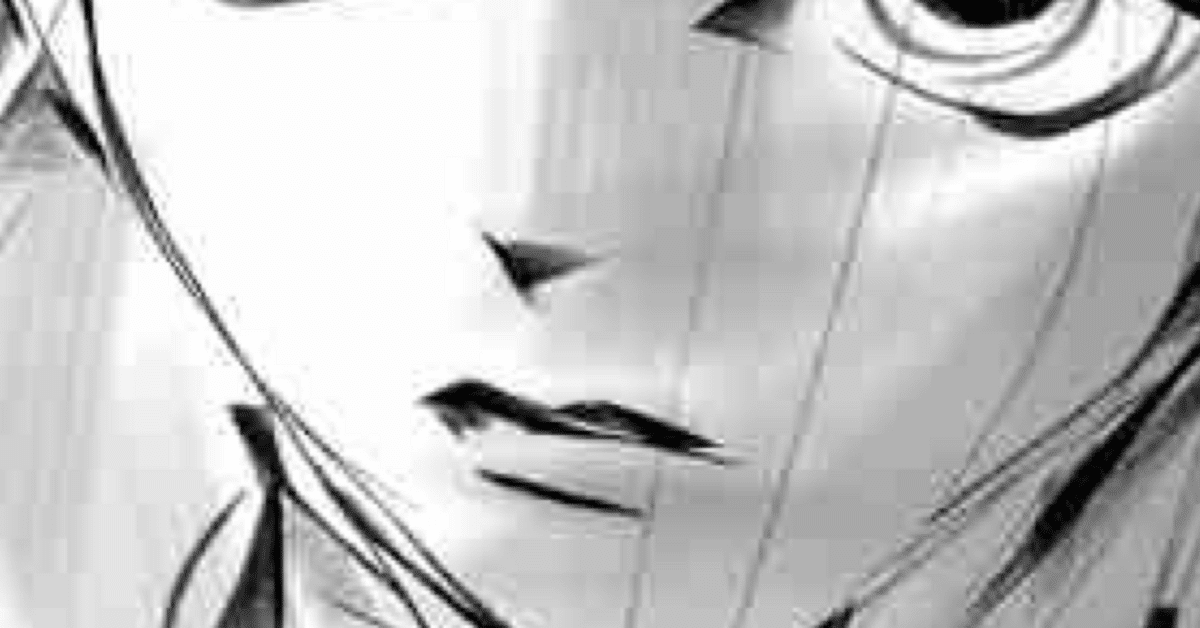
普段アニメや漫画をほとんど見ないので自分の偏見かと思ってたらどうやらそうじゃなかったらしい話
漫画系イラスト描いてるのにアニメはほとんど見てないし漫画もそんなに見てないんですよ。
私が自分の絵を描くのに基本漫画もアニメも不要なもので…(滅多にやらない二次創作以外では)
自分のテリトリーに近い競合ジャンルを自分の作品のインスパイアの元にしてるとなんというか「(表現したい自分オリジナルの脳内)イメージの『縮小』再生産」になってくのを過去感じたもので…。
てことはどんどんイメージ貧困になってついには消滅してしまいそうで。
描きたい自分のイメージがね。
インスパイア元の影響で自分要素が減ってくというか。
自分要素がないなら自分が描く意味ないので、近しいジャンルのものはあまり摂取しすぎないようにしているのだ。
そんな風に、ほぼ見てないにも関わらず、昨今の漫画やアニメに対して感じていた「ある感慨」が私の中に実はあった。
しかしさすがに「見てもいないのに決めつけるのはただの先入観か偏見かもしれないからまあ、あまり考えないようにしておこう」と思っていた。
…んだけど、それが実はただの偏見でもなかったようで。
というのはこちらのnoteを拝読させていただいたのですが。
あれ、わたしが先入観や偏見かもしれないので脳内の隅っこに押しやってたことがそのまま書かれてる!
のだった。
ちょっと長くなるがその部分を引用してみる。
端的に言えば、昨今は「絵はきれい(作画レベルが高い)」し「よく動く」、手間とお金のかかったものであるにもかかわらず、案外「つまらない(面白くない)」作品が少なくない、というようなことだ。
(略)
たしかに「そこだけ」見れば「すごい作画だ」と言えるし、それだけでアニメオタクなら喜ぶのだろうが、しかし、この作品では、そこだけが、良くも悪くも「不自然に浮いていた」のだ。まるで「ここ、上手い原画家に描いてもらいました」と言わんばかりに。
無論、良いシーン、良いカットというのは、良い作品を作るためには必要なのだが、いくら「優れた(動かせる)アニメーター」を集め、さらにそれを「絵の上手い(美しい絵の描ける)作画監督」に修正させたとしても、それだけでその作品が「1本の映画として」傑作なるわけではない。
山下清悟の言う『作品という水準で考えたとき』とは、そういう意味なのだ。
事実、本書の対談を読んでいて引っかかるのは、あれは良かったこれはすごいとかいう話は、もっぱら「パーツとしての作画」に限定されていて、「作品そのもの(総体)としての出来不出来」には、ほとんど触れようとしない点で、(略)
いずれにしろ、作品というのは、山下清悟も言っていたように、作画レベルの問題だけではないのである。
(略)
例えば、昔のテレビアニメに比べると、昨今のテレビアニメの「作画レベル」の高さは、比較を絶したものがある。にもかかわらず、昔のほとんど動かない(作画枚数の少ない)「電気紙芝居」の方が、面白い作品が「多かった」とは言わないまでも、面白い作品が「少なくはなかった」という現実は、いったい何を意味するのか?
そのことを、「作画」という「セクト的なこだわり」からいったんは離れて、考えるべきなのだ。
現在のアニメ界を取り巻く情勢では、「デコボコはあっても、面白い作品」つまり「当たって傷んでいる部分はあっても、そこ以外は甘くて美味しいリンゴ)」は許されず、「見かけだけはピカピカだが、実際に食べてみると、さほど美味しくも甘くもないリンゴ」を作らざるを得ないという「現実」があって、その現状そのものを否定する(突き崩す)のは容易ではないのだろう。
だが、だからと言って「見かけを磨き上げるシステム」の構築を目指すだけでは、良い作品は生まれない。
「金と人材をふんだんに注ぎ込んだ作品」は、たしかに「見栄えがして、作画的に圧倒される作品」にはなるだろうが、それが「映画としての名作」になることなど、めったにないのだという現実を、今の現場にいる井上にも、そして「方法論」の問題に興味が集中しがちな高瀬にも、もう一度「一般的な映画ファン」の目線にまで立ち戻って、考えてみてほしい。
あーびっくりした。
私が感じてたこととほぼ同じだった。
しかも自分の偏見だろうと思ってたので掘り下げもしないでぼんやり保留にして隅に押しやってた感慨なので、こうもはっきりと鮮烈に言語化されると、すごいインパクトである。
うわあ、めっちゃ目が覚めたー!みたいな感じ。
たまたま眼にした漫画やアニメの情報に切れ切れに接するだけなので中身も知らずに断言はできなかった感慨だが、印象でだけはそう感じていたのだ。
ちなみにこのnoteの方の映画監督としての安彦良和先生評も私の感覚にかなり近い。
ただ安彦先生のイラストに対しては監督としてのそれとは私は完全に分けている。
さすがのレジェンドだなーと思うし、そもそもペンが苦手で筆描きというところに私は敬しつつも最大の親近感を持っている。
閑話休題。
そんなわけで、昨今のアニメや漫画に対してなんとなく抱いていた印象がそう間違いではなかったらしい、ということを理解した。
そうは言っても特にアニメは、というか映像や動画などは視聴に時間が明らかに取られるので、本当に見ない。
なので、私の印象の根源は主に漫画だとは思う。
が、昨今のアニメは漫画かラノベの原作付きが多いように見えるし、ラノベはというと「文字で書いた漫画」と私は捉えてるので、結局どのジャンルでもそんなに差異はないのだろうと思う。
そしてぶっちゃけ身も蓋もないことを言うと、要は「絵は綺麗で見やすいけど、お話はなんか平板だなー」と感じることが多い。
漫画は例えば試し読みとかは時々するのね。
そういう時の印象。
もっと言うと、「絵は綺麗だけどどっかで見たような似たようなのが多いし、お話もある種の類型が多いなー」という印象である。
そりゃ世の中のアイデアは全て過去の焼き直しであり、完全なオリジナルというものは存在しない。
だけど例えば漫画はアイデアだけでできるものではない。
漫画には少なくとも
絵
アイデア
ストーリー
が必要である。
さらに贅沢を言うなら
感動
哲学
なんてものもほしい。
ええと、「感動」は本当は「絵、アイデア、ストーリー」の最低限必要セットに入れたいのだが、事実上感動まで盛り込める人ってそんなにいるもんじゃないので最低限セットではなく贅沢セットの方にした。
あ。なんか最低限セットと贅沢セットに分けてみたらなんかわかってきたぞ。
最低限セットは「漫画としての格好というか体裁を初心者でも最低限保てるセット」である。
贅沢セットは「数多ある漫画の中で読者に強く訴求し並み居る作品群の中から頭ひとつ抜け出すのに必要な必殺技オプション」である。
で、最低限セットを身につけるのはある意味そう難しいことではない。
なぜならハウツーが無料でネット上にたくさん転がっているからだ。
なんなら有料も視野に入れたら本当にたくさんの教科書が手に入ることだろう。
じゃ贅沢セットはというとハウツーでは身につけられない分野になると思う。
というのは、「感動」「哲学」は人に教えられて得るものではないからだ。
言い換えると、創作してて一番羞恥心を掻き立てられる分野と言ってもいいと思う。
「感動」を感じるには自己の感情に素直になる必要がある。
自分を騙してる人が感動を感じることはありえないし、もちろん自分が感動してないのに他人に感動を与えることもできないからだ。
そうすると、自分の自尊心やプライドより他者のなんらかの言動や作品に対して無防備にならなくてはならない。
これは、ある種の殻にこもってる人間(例えば私)などには大変難しいことである。
自分を護る盾や甲冑を脱ぎ捨てねばならないからだ。
そして自己の哲学の確立は難しい。
哲学は表面ではなく隠された(簡単には覗けない)物事の深奥を辿るという、ある意味めんどくさい作業が必要だからである。
しかもそれを整理整頓し「自分オリジナルのセフィロトの樹」を作らねばならないからだ。
目に見えることを言うのは簡単なことである。
でも目には見えない哲学を育てるのも、語るのも大変難しい。
視覚情報から87%の情報を得る人間という生き物は、目に見えないことを無視しがちだからだ。
なので、「贅沢セット」には自己開示という羞恥プレイと上っ面に騙されず物事の奥を見通す目が必要になる。
私のような小物ではとても無理な難題である。
というかそこまで兼ね備えてる作家は少ないと読者としても感じている。
アニメオタクが作画にこだわるのは「目に見えるから」で、全体の作品の質は「視覚情報として明らかではない」のでカスタマーたるアニメオタクでは認知もしづらいことだろう。
さらにそれを「作り手として作品の質を上げる」という抽象的な課題としてクリアするのは一朝一夕ではできないと思うのだ。
というわけで、自分の偏見と思ってた感想は案外的外れじゃなかったらしくて驚いた、という話。

横着なイラチなので
秒で描き上げちゃうから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
