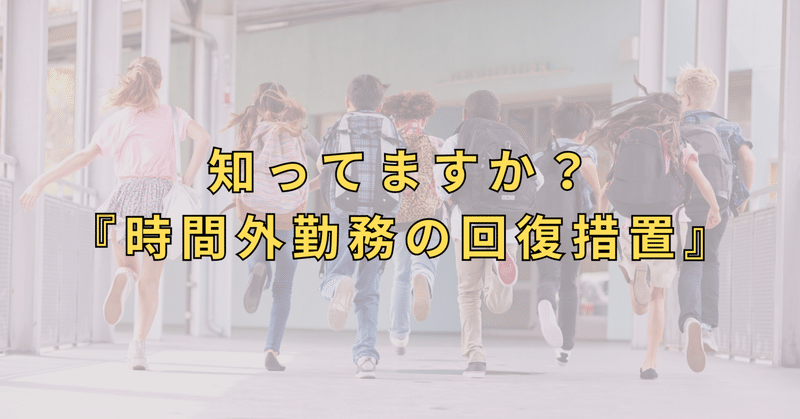
『時間外勤務の回復措置』について
はじめに
ぼくたち教職公務員は、基本的に残業は認められていません。しかし、例外もあります。今回の記事では、法的根拠を踏まえて、残業が認められる場合と、その残業が発生した時の対応についてまとめています。ぜひご覧ください。
超勤4項目とは?
ぼくら教員は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」もとで、原則として時間外勤務を命じられることはないとされています。しかし、例外があります。それが超勤4項目です。以下、少し長いですが大事な法令なのでお読みください。
教育公務員は、勤務時間の割振り等により、原則として、時間外勤務が生じないようにする必要があり、勤務時間外に業務を命ずる時には、超勤4項目について臨時又は緊急のやむをえない場合に限られている。
1.教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
2.教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
また、教員はこのように時間外勤務は原則認められていないにも関わらず、時間外勤務が発生することがあるため、その部分も包括的に評価するために『教職調整額』というものがあり、基本給に4%の上乗せがあります(※この学を引き上げるという議論もありますが、それは別の話題なので割愛します)。これを、残業代が支給されない代わりにしているという解釈でだいたい合っています。
教職調整額=残業OK、ではない!
さて、ここからが今日の本題です。
こうした法令をまちがって解釈する先生は非常に多いです。ぼくも勘違いされている先生をけっこう見るので、その際は「それは違いますよ」と説明することにしています。
よくあるのが「教職調整額(残業代のかわり)があるから、超勤4項目の場合は時間外勤務させてもしょうがいよね」とか「教職調整額があるから、時間外勤務の振替はしなくても問題ないよね」というな法的解釈です。
ただ、この解釈は全く違います。
カギとなるのは『時間外勤務の回復措置』というものです。そこで、まずは以下の文科省HPをご覧ください。
ここを読むと、まず「原則として、時間外勤務は命じないものとした上で~」とあります。つまり、教職調整額とか残業代の有無にかかわらず、時間外勤務を命じることは基本的にNGだということがはっきりと示されているのです。ここは絶対に押さえておいてください。もし仮に、管理職から「これは超勤4項目に該当するから、職務命令だよ」という超レアなお言葉をいただいたとしても、それは本当に緊急なのか、やむを得ない場合だったのかを検討することは、非常に意義のある事です。
そしてもう一つ。仮にやむを得ない場合だったとしても、原則禁止のはずの時間外勤務を命じて、その後の措置はどうするのか問題があります。それに対して「教職調整額があるから、そこで補填している」というのは、アウトとは言わないまでも、かなりグレーだと個人的には考えています。その根拠となるのが「時間外勤務の回復措置」という通達です。
給特法施行通達(昭和46年7月9日)では、教員の時間外勤務に関する基本的態度として、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として、時間外勤務は命じないものとした上で、実施に当たっての留意点として、次の3点をあげている。
1.長時間の時間外勤務はさせないようにし、やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること。
2.日曜日又は休日等に勤務させる必要がある場合には、代休措置を講じて週一日の休日の確保に努めるようにすること
3.時間外勤務を命ずる場合は、学校の運営が円滑に行われるよう関係職員の繁忙の度合い、健康状態を勘案し、その意向を十分尊重して行うようにすること
上記を見ると、例えば「1、長時間の時間外勤務はさせないようにし、やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること」とあります。これをどう解釈するのか、という問題です。
これをお読みの先生方は『長時間』というのはどのくらいの時間を指していると思いますか?30分くらいならセーフ?1時間以上からが長時間?おそらく、個人によって解釈に幅があると思います。そして、それでかまいません。要するに、数値が示されていない以上、これは「読み手の解釈に委ねている」と考えるのが自然です。この措置を講じる権限があるのは、職務命令権を有する管理職(つまり校長先生)なはずなので、校長先生が「30分でも長時間だから回復措置を講じよう」と解釈してもいいし「1時間くらいなら短時間だから回復措置なんていらないでしょ」と解釈するのもアリだと思います。
ただし、その場合においても「3.時間外勤務を命ずる場合は(中略)その意向を十分尊重して行うようにすること」とあることから、管理職は関係職員に対して、上記のような解釈と回復措置の講じ方についてはしっかりと説明し、理解を得られるよう努力すべきだと考えます。
さいごに
まとめると、まず教育公務員は時間外勤務(残業)は基本的にNGで、例外的に超勤4項目に該当する場合での時間外勤務を命じる場合においても、管理職はその回復措置について適切な配慮や説明責任があるよ、ということです。
ただし、あくまでも上記したことは、法律をもとにぼく個人が解釈したことです。もしかしたら、どこかに穴があったり、間違ったりしているかもしれません。その際は、ぜひご指摘ください。ただ、こうした法律の知識と言うのは、間違いなくぼくら学校教員を守るための武器になります。
また、ぼくはこうした法律の知識を提供したり、個人・そしきでの働き方改革を推進したりするコミュニティ『定時退勤がちサロン』というものを運営しています。もし、こうした内容に興味があれば、ぜひぼくのXアカウント(こちら)までご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
