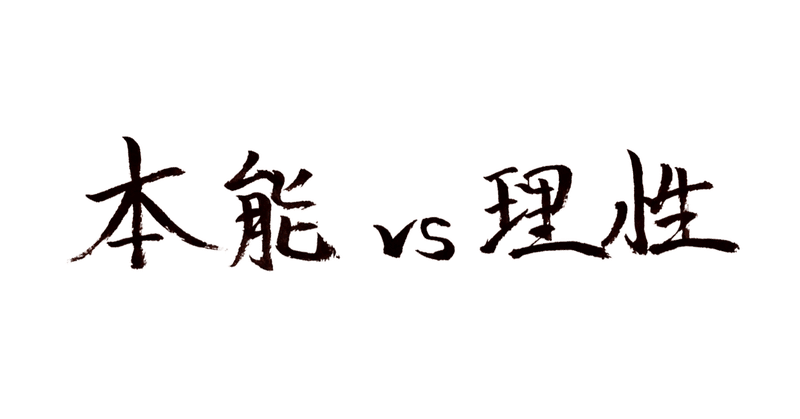
「教育の矛盾」①
こんにちは、みちおです。
今日は、3/1。学生生活も残すところわずか1ヶ月となってしまいました。
3月は、いろいろなところへ旅行に行ったり、初めての1人暮らしの準備をしたりと、これまでの生活に区切りをつけつつ、新たな生活へと移行するクッションのような1ヶ月になるのではと想像しています。
わたしもついに社会人となり、これまで「もらう」側に徹していたものを「渡す」側へと変わっていかなければならない。そのような思いが沸き始めています。
この4年間、わたしは特に「教育」について学んできました。人に何かを教え、人を育てる。4年間の学びを通して、「教育とは何か」という問いに現時点でのわたしなりの答えを考え出すことが一つの目標でありました。そして、それは今頃もうとっくに見つかっているんじゃないかなと思っていました。
しかし、わたしにはまだその定義をみつけることができていません。「教育とは何か」に対して明確な答えを生み出すことができていないのです。
ただ、手がかりは1つあります。
2020年の5月ごろ、外出できなかったことで何かについて考える時間が増えたわたしには、「教育」についてわからなくなっていました。そして、それがとても気分が悪く、何かを考え続けなければならない起きている状態がとても嫌だったことを覚えています。
そこで、わたしなりの教育に関する様々な問題意識を二項対立化し、「教育の矛盾」として挙げました。今見返すと「そうだな」と思うことばかりではありますが、霧の中にある「教育」を様々な方向から切り刻もうとしていたわたしには、それを行うことでむしろわたし自身が「教育」から解放されたような気分になったのです。
今回の記事ではその二項対立を全て提示していき、そこから2年弱経った今の思いもつけて、大学生のわたしが残す「教育観」としたいと思います。今書いている時点でどのくらいの長さになるのかはわかりませんが、少しでも面白いと思っていただけたら幸いです。
①本能と理性
しょっぱなからものすごく大きいテーマが出てきました。「本能」とは、人間の動物的衝動、「理性」とは、その衝動に対する制御のことではないかと考えます。他者との関係について考えるという意味においては、「社会性」と言い換えることができるのかもしれません。本能が強い人は自分自身の思いにのみ従って生きようとし、それが周囲に及ぼす影響についての考慮ができない。反対に理性が強い人は、社会的に見れば「いい人」ではあるけれども、自分の内なる声を聞かないフリをしてしまう。そのような対立があります。もちろん、どちらかに振り切っている人を見たことはありませんし、ほとんどの人はどちらの性質も持っていると思います。
教育の場面では、「本能」と「理性」について深く考られることは少ないのではないかと考えます。なぜなら、そもそも教育とは「本能」を持つ「ヒト」に「理性」を与え、「人間」にしていく行為であるからです。そういった意味で、より「理性」を持った子どもが「おとなっぽくて偉いね」と言われ、やんちゃな子どもは「悪ガキ」なんていう言葉を付けられるわけです(「悪ガキ」には可愛らしさも含んでいるとは思いますが)。
全ての人に「本能」は必要ないのでしょうか。人間は「本能」から解放され、社会の中で「いい人」になることが必須であるといえるのでしょうか
この問いに対する答えが各個人の教育の方向を決定する1つの大きな要因になるのではないかと考えます。
わたしは、「欲」が存在しない社会ほどつまらないものはないと思います。人間が持つ3大欲求を含め、様々なものを「手に入れたい」という気持ちが社会全体をより大きく、より豊かにしていくのではないかと思います。しかし、最近の教育にそのような「欲」が顔を出すことは少ないと思います。教育する側も、される側も、秩序立った教育体系の中で安心して「人間」になっていく。それがよいことであるのは間違いありませんが、果たしてそれ「だけ」でよいのでしょうか。
今回の記事は、ここまでにしたいと思います。次回からはできれば2つは書こうと思っています。
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
