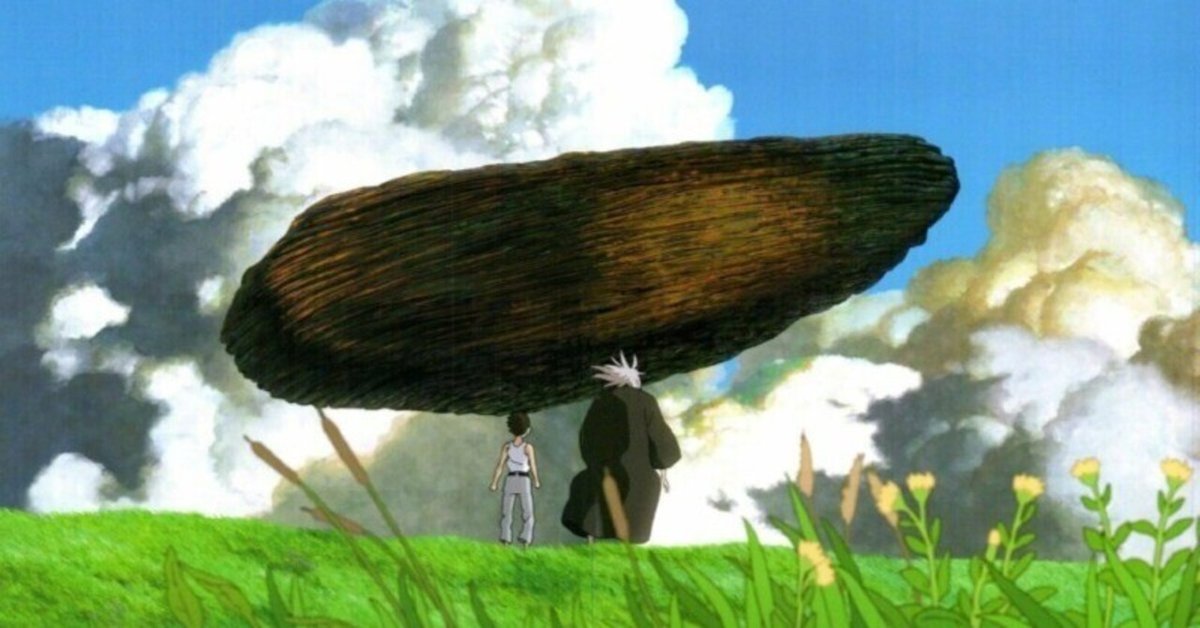
#91 [君たちはどう生きるか]#2 その時代の生活感の持つ意味
憧れの世界
この本、当時田舎に住む中学生の読者からすると、経済的・家庭的・知的にも、あこがれの世界かもしれない。そういう主人公の生活が本の中にある。
時代背景
出版は昭和12年(1937)。時代は戦争・軍国主義へ転落する。当時は家電などほとんどない、穏やかな生活が描かれる。生きた人間としての中学生や家庭が息をする生活がある。
主人公の周辺
中学一年生の主人公(コぺル君、本田純一)は、おそらく当時の旧制中学生であろう。その主人公の日常生活の出来事について、「おじさん」という人物と語ることで、主人公の世界観が作られていく。
主人公は東京に住む。
東京、それだけでも十分に向こうの世界。
「女中、女学校、ロシア菓子、国電、闘球盤、停車場、自動車(タクシーのこと)、(友人の父親が)陸軍大佐」だった、などの文中の言葉の端々から、ある程度の中産階級以上の家庭が設定されている。主人公の母は父を亡くした女学校卒で、父のいない分、大学卒と思われる「おじさん」がコぺル君の近くにいる。
再読版
私が再読したのは昭和44年発行で昭和31年版である。この本が世に出たのは日中戦争の盧溝橋事件のあった7月とある。吉野源三郎の「あとがき」のよれば、その後この本は(日本少国民文庫 全16巻の16巻目)自由主義的であるということで発行が禁止されている。
おそらく、私が40年以上前、中学時代に読んだのも、この版である。
発刊の理由
「あとがき」にある「せめて、少年たちの無垢の心を、この悪い影響から守りたい」という吉野源三郎のことば。あこがれの世界が必要であり、日本の各地の、貧しいかもしれない少年が読むことでそれが特別ではないことではないのだ、ということに賭けることを想定しているように見える。
時代の危機感から未来への希望
その読書さえままならない家庭や少年も多くいる時代であろう。しかし、なおその上でも、である。いまそうした世界があるのだろうか。大人にとってもである。
もし彼らが生きていたら
コぺル君とその友人の北見君、浦川君がもしも生きていればと仮定してみた。
1937年に13歳だとして、1945年には21歳となる。とすると、学徒動員・兵役の時代にどのようにかれらは生きたのか。そもそも生きて行けたのか。その後の「君たちが、どう生きたか?」はわからない。
君たちってだれ?
ふと、その君たちとはだれか、と、考える。もし3人が生きていなかったとして、その君たちとは、私たちではないか。その後の未来ではないか。未来を描くには、今を描くしかない。
想像力と哲学の問題
それは、想像力の助けを得て、ゆるぎない哲学の世界を描くことではないのか。だから、この本にはさりげなく、パスカルとゲーテが引用されている。これは中学時代に読んだときには気づかなかったことである。
