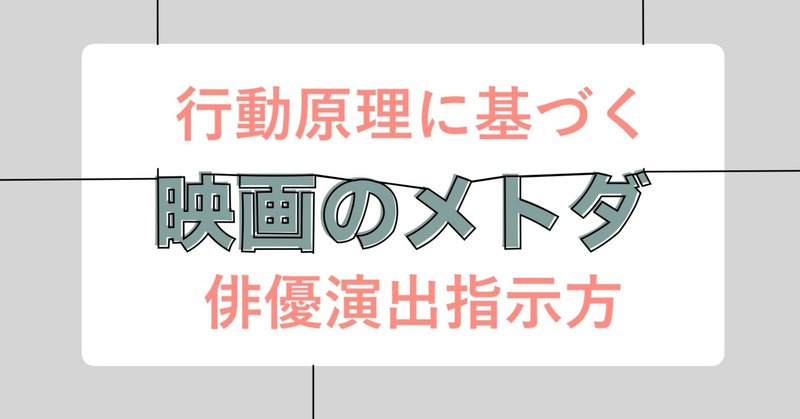
俳優演出【入門】:【オブジェクト指示】
【オブジェクト指示】
さて、以前に【オブジェクティブ】と【スーパーオブジェクティブ】の話をしました。
実はこのオブジェクト指示というのはシナリオを分解して指示を細かくしていく過程にも有効です。その為にはまずは、この2つのオブジェクトをきちんと設定する必要があります。その上で、その2つに沿うような指示を細かくしていく必要があります。
感情を代表する『泣く』という行為を一つとっても、多くの種類があります。
悔し涙、嬉し涙、 悲しい涙、笑い泣きetc...
しかし、どの涙も共通することがあります。
それは "理由と対象" があること。
悔し涙→馬鹿にされた
嬉し涙→大切な人が無事に帰ってきた
悲しい涙→裏切られた
笑い泣き→笑わせられた
このように、必ず原因があり、その全てに『誰から受けたものか?』という対象がいます。
実は感情には "なんとなく" は存在しません。
実生活においては原因を"あえてはっきりさせない”という自己防衛が働く場合があります。
その場合は原因がないのではなく、原因を認知していないだけなのです。
しかし、役者に対してその防衛本能を含めた指示与える事はできません。なぜなら、役者はまず、根源である感情を表現しなければならないからです。感情の沸き立つ元には必ず原因があって、それを起こした"対象" がいます。この理由と対象が曖昧なまま役者は感情を作る事は出来ないのです。
その為、役者は 『誰に』『何をされたことによって』『何を求めるのか』を明確に理解する必要があります。特に大事なのが『何を求めるのか』です。
『何を求めるのか=オブジェクト=目的』をはっきりすることによって、役者はその目的に向け行動できるようになります。
例えば
悔し涙→馬鹿にされた→復讐してやりたい
嬉し涙→大切な人が無事に帰ってきた→一時も離れたくない
悲しい涙→裏切られた→相手の心を取り戻したい
笑い泣き→笑わせられた→もっとこの人と一緒にいたい
これらのオブジェクトは役者の行動形成の助けになります。
それではオブジェクト指示とはどのようにするのでしょうか?
前回の例を使って表してみたいと思います。
⚪️Aの家 玄関/午後10時頃/内
鍵を開けてAが入って来る。手にはカップラーメの入ったコンビニの袋。
(一刻でも早く休みたい)
うっすら開いたキッチンの扉から灯りが漏れている。驚くA。驚て静かに
様子を探る。(状況の確認、身の安全の確保)
B「お帰りなさい!」
キッチンの扉が開き駆け寄ってくるB。(相手を観察する)
A「びっくりした…。今週は仕事で忙しいんじゃなかったの?」(追求する)
B「ちょっと手が空いたから。(Aの荷物を引き取り、キッチンに戻りながら)どうせ、あなた、忙しさにかまけてロクな物食べてないんじゃないのかと思って、作りに来ちゃった。」
⭐️
A靴を脱いで、Bの後についてキッチンへと向かう。(感謝を伝えたい)
さて、カッコで書かれた太字が【オブジェクト指示=目的指示】です。
(一刻でも早く休みたい)という目的は、登場人物が如何に疲れているかという登場人物の置かれた状態も表しています。しかも、この目的は必ず全ての人が経験したことがあります。
この指示だと、役者が自分の経験から登場人物の状況をイメージしやすく、再現しやすいのです。
以前にも言いましたが、人間は経験したこと以外は出来ません。
役者への具体的な指示の目的は、役者の経験を呼び起こし、そのシーンに合った感情を当てはめることです。
もし、この目的指示で役者がうまく機能しない場合は言い方を変えます。
(一刻でも早く休みたい)→(今すぐベッドに横になりたい) etc...
大切なのは、監督が常に何を表したいかを明確に持っていること。
ここでは "如何に彼が疲れているか" を表現します。
(感謝を伝えたい)
目的指示の基本は『〜たい』という願望を表す言葉で行います。
この時点で、すでに俳優とは『登場人物がどのように世界を見ているか?』 というのを確認済みですね。それを考慮して役者は"感謝を伝える"という目的をありとあらゆる方法で試すことができます。
それは役者がバリエーションを提示できるというのと同義語です。
例えば【嬉しい】→【なぜ嬉しいか?】→【どの様に嬉しいか?】
といった様な指示(解説)の仕方をすると、どんどん状況が限定され選択肢が減っていきます。
以前にも言いましたが、この様に状況を限定してしまった場合、役者は自分の経験から答えを見いだそうとします。"自分が同じ状態だったっら"という思考に無意識に引きづられてしまうのです。
何度も言いますが、同じ状況でも人によって感じることも行動も違います。
役者が本人として感じることが、役に合っているとは限りません。
そうなった場合、バリエーションが提示出来ない状態は方向性を探ることすら出来なくなってしまいます。逆に言うと、役者はその目的達成のために常に幾つかのバリエージョンを想定しておく必要が有ります。幾つかの選択肢の中から監督がこれだと選び、それを詰めていく事になります。実はむやみに初めから限定された状態から始めるより、過程を経て限定されていく方が役者は監督の意図を取り込みやすくなります。何が無駄で何が必要なのか明確に見えてくるのです。
また、1シークエンスの中で登場人物のオブジェクトを1度変えることができます。
シナリオの中に記した⭐️印がありますが、いわゆる【チェンジング・ポイント】です。何かの過程を経た結果、登場人物の目的=心境に変化が現れる部分です。
このシナリオの場合 "疲れて休みたい→相手に感謝をしたい" と、行動の原理になる欲求が180度変化します。
さて【オブジェクト指示】が理解できたところで、次回はカッコで書かれた他の指示について解説していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
