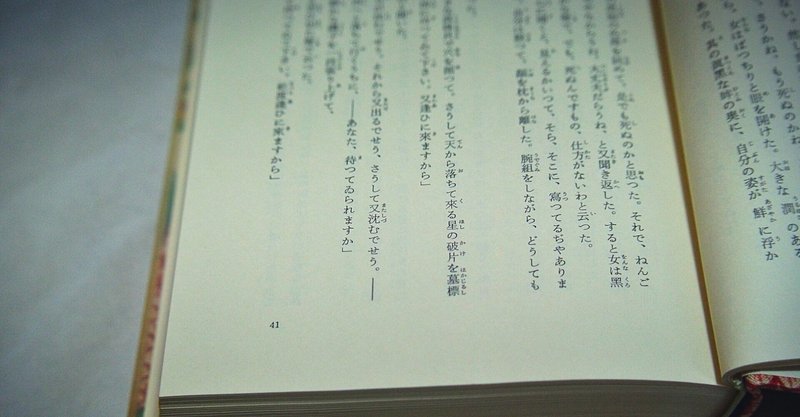
【詩を紹介するマガジン】第1回, アイヒ
詩を紹介するマガジンを始めました。気になる作品や昔から気に入っている詩、現代作品まで、幅広くご紹介できたらと思っています。詩を紹介したあとで、自分の見解など書いていけたら。初回の本日ご紹介するのは、アイヒの「たなおろし」です、どうぞ。
******************
ギュンター・アイヒ「たなおろし」
これは僕の帽子、
これは僕のマント、
ここに僕の髭剃り用の道具一式
亜麻布の袋に入って。
缶詰の缶:
僕の皿、僕のコップ
ブリキに
名前を彫った。
彫ったのはこの
貴重な釘、
僕はそれを隠している
物欲しげな目から。
食糧袋の中にあるのは
毛糸でできた靴下一足、
それからいくつか
誰にも教えてないものたち、
枕として使うんだ、
夜には僕の頭を載せて。
厚紙はここに
僕と地面の間に置かれている。
鉛筆の芯、
僕が一番愛している:
昼にはそれが僕に書いてくれる
夜に思いついた言葉を。
これは僕のメモ帳。
これ僕のテントの布地、
これが僕のタオル、
これが僕のより糸。
どこにも悲惨な描写はないのに、なんだか不穏な雰囲気の詩だ。作者のアイヒはドイツ人で、1907年に生まれ、72年にその生涯を閉じた。
この詩にはたくさんの疑問符が浮かぶ。どうして、数えられるだけの持ち物しかないのか。なぜ釘がそんなに貴重なのか。どうして厚紙を枕にするのか。なぜ缶をお皿にしたり、コップにしたりしなければならないのか。なぜ夜に思いついた言葉を、昼になってから書きつけるのか。
もう一度書く。アイヒは1907年に生まれ、1972年に死んだ。つまりその間に2つの世界大戦があった。2つともヨーロッパが舞台となり、彼はドイツ人だった。
詩にそんなことは何も書かれていないのに、「戦争」の暗い生々しさが伝わってくる。夜に電気が使えないこと、釘を欲しがる人、テント暮らし、物資が十分になく互いに疑心暗鬼に陥っていること……。これが前線のリアルなのだろうと思う。銃を持って撃ち合うだけが、戦争ではないのだ。
第二次世界大戦以降のドイツ語作品は、こういう独特の暗さが垣間見える。戦勝国ではないせいもあって、戦争を美化しない。捕虜や収容所、現実の重みと向き合おうとする言葉が紡がれる。
少しドイツ史に詳しい人は「ドイツ文学はやっぱりゲーテよ。疾風怒濤(シュトゥルム・ウント・ドランク)の時代は素晴らしい」と言うかもしれない。ゲーテも嫌いじゃない。すごく勢いがあって、感情を高らかに歌い上げる。こっちが赤面するレベルの愛の歌もある。あれはあれで、おおらかでいい。
だけど自分が好きなのは、このあたりの時代の「不穏なドイツ」。感情をぐっと抑え淡々としていて、だからこそ生々しい。名言されてはいないものの、背景に暗い何かがあり、読者の想像力を掻き立てる。
「芸術の神髄は想像させることだね、全部しゃべってしまったらいけないんだ」
むかし彫刻家がそんなことを言っていた。「暗示するのがいいんだ、はっきり見せてしまったら、見ている側が想像する余地がない、そんなのはつまらない」と。そうかもしれない。だとしたら、この詩のシンプルさは芸術的だと言える。何も説明せず、ただ事実を連ねているのにこんなにも不穏で物悲しい。
作者のアイヒは、実際に軍役に就いた人だ。詩を書いていたが、ナチス・ドイツの時代に筆を折った。それからアメリカで捕虜となり、捕虜収容所の中で再び詩作を始めた。これはその頃の作品になる。捕虜収容所、一体どんな場所だったんだろう。決して明るい場所でなかっただろう、とは思うけど。
戦争は、文学青年まで戦地に駆り出してしまう。人が亡くなるだけでなく、生まれるはずだった作品が生まれない、そんな側面も戦争にはある。
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
