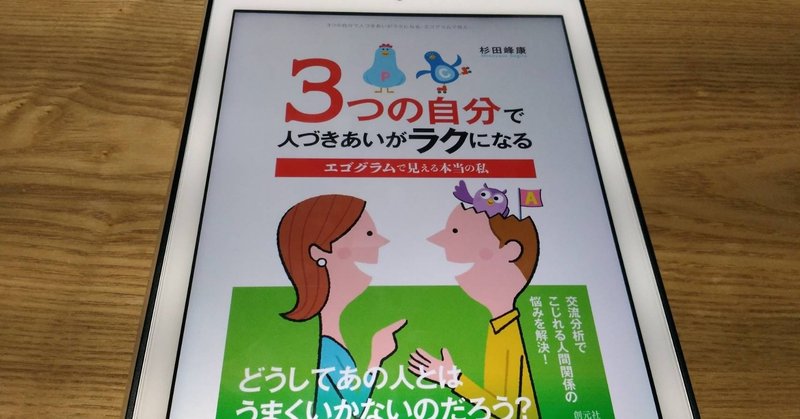
【書評】3つの自分で人づきあいがラクになる: エゴグラムで見える本当の私 杉田 峰康
私は交流分析に関しては、最近かじりはじめたばかりだったので、エリック・バーンが創始したTAと交流分析は同じものだと思っていた。この本を読んで初めて、米国式TAが日本流にアレンジされて「交流分析」と呼ばれるようになったきっかけも知ることができた。
そもそも、エリック・バーンの弟子デュセイが開発したエゴグラムも、今のような質問紙法ではなく、直感的に皆で意見を出しながら作るグラフだったようだ。日本人向けにアレンジされての今があるのだ。日本の場合は、心療内科の臨床で、交流分析が使われてきたこともあり、ぐっと臨床的(すぐに使える情報が多い)であるのが良いところだ。
交流分析のベーシックな点を抑えつつ、実践家ならではの新鮮な視点も盛り込まれているのが、この本の特徴。発行年も2018年で、なかなか新しい発展がない?(本がない)交流分析の中では珍しい本だと思った。
交流分析の初心者に最適
タイトルにある3つの自分はP(親)・A(大人)・C(子供)である。5つに分けるよりも分かりやすい。初学者に説明する方法を学べる。図解も多く、どれだけ基礎知識がなくても、挫折しない交流分析本だ。
ということで、最初はさらっと読み飛ばしてしまって、どうにも刺激が足りないと思っていたのだが、再読すると、なかなか深いことがさらっと書いてあったりして侮れない。
さすが、日本に交流分析を広めた第一人者だけある。
いくつもの視点で自分を見る
エゴグラムを書くときに迷うのが、職場では、こんな風にふるまうけど、家では違うよな~とか、場所とか状況によって自分の行動が変わること。この本では、自分の状況ごとに合わせてエゴグラムを書いてみることが勧められており、この視点は新しいと感じた。
場所によって変わるエゴグラム:例えば「家庭」「職場」「旅行中」「家庭外」「休日」「接客」などの場所によって、自分のエゴグラムがどう変わるか。私の場合なら「ネット上」での自分と「対面」している時の自分では、ずいぶんFC・ACの値に変化が出ることが分かって面白い。ネット弁慶タイプか(涙)
年代の変化によって変わるエゴグラム:さらに、自分のライフサイクルに合わせたエゴグラムを書いてみる。「小学校時代」「思春期」「結婚前の数年」「結婚後5年」「結婚後10年」「その後」。半日くらいかかったけれど、徹底的に様々な角度から見た自分を分析できた。
思い出して書くしかないけれど、幼少期~青年期までは、CPやAがぐっと低い。社会に出てからCPやAは育ってきたのだということが分かる。振り返ると、一番、自分らしくできていたのは、この時期だったかなという発見もあった。
理想の自分のエゴグラム:そして、もうひとつ書けるエゴグラム。それは、自分の「理想」のエゴグラムである。今の自分と、理想の自分のエゴグラムを重ね合わせ、どこをどうやって変えていけばよいのかを考えるのだ。
この一連のエゴグラムを書いてみた。私の今までの人生がグラフになった。有料ノートにしたので、関心のある方はどうぞ。
さらに、対人関係から自分を見るということで、
両親のエゴグラムと自分のエゴグラムを比較すること、うまく行かない人とのエゴグラムを比較することなど、具体例満載。これほど、様々な観点から自分を見て分析することはなかった。単に色々考えるだけではなく、やはりエゴグラムにする(視覚化する)のがポイントだ。
対人関係を変化させるエゴグラムの力
この本を見て、最近、ぎくしゃくしている同僚のエゴグラムを丁寧に書いてみた。その人になりきってみて、こういう時は、こう応じるだろうという徹底的に書いてみた。そうすると、信じられないくらい対照的なエゴグラムができた(笑)。
そりゃ合わないはずだと分かる。
しかし、同時にある部分は共通しているところがあって、その共通ポイントを軸にして話し合いを進めれば一致するのではないかと気づきがあった。そして、エゴグラムを書いているうちに、すっかり嫌な気分はなくなった。冷静になるには、良い効果だった。
エゴグラムに関しては、すでに10冊近く読んでいるので、コツコツ書評をアップしていくつもり。
私のエゴグラムは下記の記事を参照
大人のADHDグレーゾーンの片隅でひっそりと生活しています。メンタルを強くするために、睡眠至上主義・糖質制限プロテイン生活で生きています。プチkindle作家です(出品一覧:https://amzn.to/3oOl8tq)
