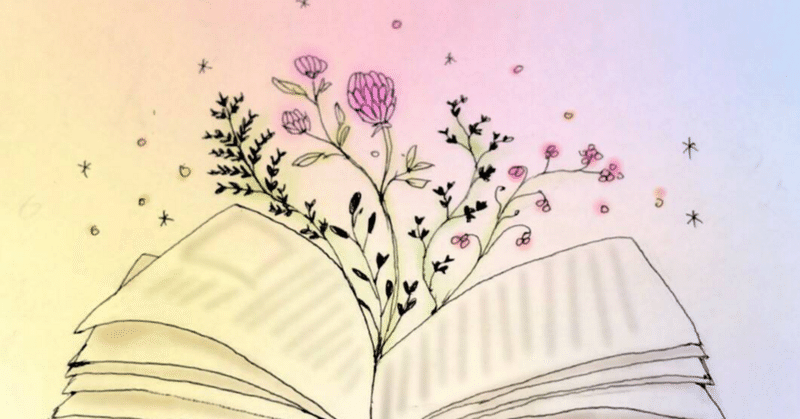
小学校で開き読みをしていました(2)開き読みをした本の紹介
神奈川の小学校に在籍していた4年間(2014年から2018年)参加した、絵本の開き読みの話を書きます。全5話です。
イラストは「みんなのフォトギャラリー」から使わせていただいています。ありがとうございます。
実際に読んだ本の中で、覚えているものを紹介したいと思います。

男の子のやんちゃさと、お母さんのあったかい優しさが心に残る作品です。

シロクロの絵で描かれている絵本で、市主催の開き読み講習会に参加した友達に勧めてもらった絵本。聞いている子ども達の頭の中で色を想像することで、脳に良い影響を与えられると教えてもらいました。

いもとようこさんの絵、小さい時から大好きなので選びました。読んでいて自分が癒されます。

昔、自分の家にあった絵本が図書館にあったので読みました。大きなタンポポを目の前にすると、人はどうなるのか。子ども達もとても楽しんでくれました。

色んなマメについて書かれた科学の本。福音館書店の科学の絵本は図鑑が好きな子も手に取りやすいのでおすすめです。

魔女が大きなカボチャの種をまきました。ハロウィンの時期に読んだ「おおきなかぶ」をパロディにした絵本。おおきなかぼちゃの収穫にどう挑むのかが面白いです。次男がお気に入りでした。

長男が幼稚園の時にこの作品を少しアレンジした劇をしていたので思い出深いです。動物たちの一生懸命さが可愛い作品です。

言葉遊びが面白いので子ども達に喜んでもらえました。

色んなパンツが出てきて面白い作品です。

小学2年生は学校に慣れてきて交通事故も多いという報道を見て、楽しく学んで気を付けてほしいと思って読みました。

ワニとして怖い存在でいなくてはいけないと思い込んでいるアランの頑張っている姿が面白い絵本です。課題図書なので、知っている子がたくさんいました。

女の子の一生懸命さ、それを受け止めるお父さんの一言で涙腺が弱くなってしまう作品。
夏の課題図書のひとつでした。以前の記事にも書きましたが、課題図書は良本なので開き読みがしやすい作品の場合は積極的に読むようにしていました。

大型絵本で読むと迫力があります。植物の成長が音として表現されている楽しい絵本です。

色んな巨大なものが出てくる絵本。ちょっと想像できないようなものが巨大化したりする楽しい絵本です。開き読みがしやすい絵本で年に一度の「お楽しみ会」ではよく読まれていました。

泉から始まると思いがちな水の旅。だけど、花の雫から始まり、最初は空へと上がります。構図が良くて、絵が素敵な本。

秋らしい一冊。植物がたくさん出て来ます。

絵がとても綺麗な作品です。最後のお父さんの言葉が耳に残ります。

読んでいる方がちょっと泣きそうになる絵本。小さなきょうだいのいる子どもの気持ちが丁寧に描かれています。

「ながいよる」はダイナミックな絵で夜が明けていくまでの様子を描いた作品。「あなた」は自分と他者との違いを様々な表現で書いています。
学年が上がると選ぶ本も変わっていきます。

鳥との共存のためにすばこを設置したドイツの男爵の話。やがてそれが森を守ることに繋がります。大人も考えさせられる絵本です。
覚えていたいことは言葉で残していきたい
開き読みで読んだ絵本は忘れないと思っていても割と抜け落ちるものだなと書いていて気づきました。
noteの中で、読んだ本とその時の感想、お子さんの反応を書いている記事をお見掛けすることがありますが、後から思い返すのにとても良いなと思います。
我が家の子ども達がそうなのですが、小さかった時から好きなことや、気に入っていたことは将来の進路を考える上でもヒントになっています。
今後読んでいきたいなと思っていた本
うちの子が5年生と3年生に上がって1か月後に引っ越しをしました。引っ越しをしていなければ読みたいなと思っていた絵本を、当時の自分のFacebookの記事を引用して紹介します。

105歳まで現役でお医者さんだった日野原先生が、95歳の時、4年生に向けて授業をした内容が絵本になっています。
お医者さんである先生が考えるいのち。
まず、子供達にそれぞれ友達の心臓の音を聞いてもらう。そして、おじいちゃんである先生自身の心臓の音も子供達に聞いてもらう。
子供達が命に対して自然と向き合っていく。
でも、先生が考えるいのちとは、生きている時間のこと。
これから先、10歳のこども達が使える時間のことだと話します。
その話を聞いた時、子供達は生きていることの喜びを感じたり、これから先、命をどう使うか考え始めます。
95歳の先生が自分の命を使って、子供達に命の大切さを伝える姿に、私はすごく感動して読んでいて泣いてしまうのですが、長男は読んですぐよりも、あとから読み返したりしながら、自分の中で命と向き合うとはどういうことか、答えを見いだしているようでした。
もうひとつは、我が家の絵本の中でも紹介した「地球をほる」の作家、川端誠さんによる落語絵本シリーズです。
中学になると、古文を学んだり古い時代のお話に触れる機会が増えます。
少しでも楽しく面白いなと思ってほしいので、落語の絵本を読みたいなと思っていました。うちの子達は「じゅげむ」「まんじゅうこわい」「はつてんじん」が好きです。
最後までお読みいただきありがとうございました。次回は学年末に1時間のプログラムで開催ささていた「お楽しみ会」の話を書きます。
よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
