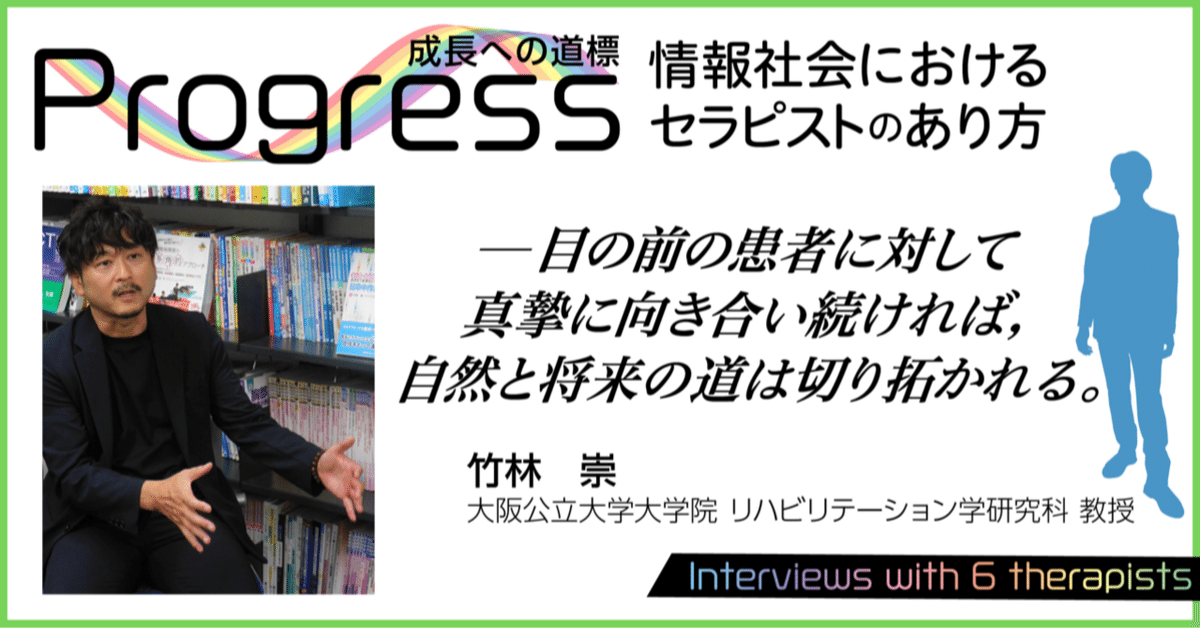
【竹林 崇先生:インタビュー第2回】科学的思考とエビデンスがセラピストにもたらすもの
情報が氾濫する時代に自己研鑽を積む極意について,リハビリテーション分野のエキスパートにインタビューする本企画。6人目は,脳卒中リハビリテーションの専門家として,さまざまな媒体を通じてセラピストに有益な情報を発信されている,大阪公立大学大学院 教授の竹林 崇先生にお話を伺いました。
全4回シリーズの第2回では,セラピストが科学的思考に基づきエビデンスをどのようにとらえて臨床に落とし込むべきか,ご意見をいただきました。
エビデンスの構造と臨床におけるEBPを理解する
——科学的思考に関連して,研究によるエビデンスと臨床での介入との関係について,セラピストの間では話題になることも多いかと思いますが,先生はどのように考えていますか。
竹林:
両者の関係性を理解するには,まずエビデンスというものの構造を正しくとらえる必要があります。
エビデンスといえば,絶対的な正答を示すという印象を抱く方も多いですが,実際には限界があって,そこが曖昧な部分となっています。
ガイドラインなどで示されているあるエビデンスの限界を知るためには,そのエビデンスの元となった論文などを読みながら,まずは研究デザインの正確さを批判的に吟味する必要があります。さらに,どのような対象者,どのようなアウトカムに適応されるエビデンスなのかを考える必要があります。
そのうえで勉強して,得られたエビデンスが正確なものか曖昧なものか,自分の頭の中でランク付けをしていきます。
さて,これらのエビデンスを臨床において,本人の嗜好性や環境因子といった個別性を考慮しながら,患者さんにとって利益が最大になるように介入方法を医療者と患者さん自身が協議・合議しながら取捨選択し,アプローチしていくのが,EBP(編集部注:科学的根拠に基づいた実践)です。
——エビデンスやEBPの考え方について,セラピストが学ぶ機会はないのでしょうか。
竹林:
本当は,臨床現場に出る前の養成校で教えないといけない内容だと思います。
ただし,現状の養成校における教育課程では実習自体もCCS(編集部注:臨床参加型実習)になっており,EBPに関する実践まで行える時間的余裕は少ないかなと感じています。
ですから,ただ考え方を伝えても,すぐに利用できるとは思いません。
実際には,免許取得後の卒後教育のなかで,自身で実践しつつ,EBPを身に付けていく形になると思います。
日本は,皆保険制度によって誰しもがリハビリテーション(以下,リハ)を受けられる世界的にも稀有な国です。
公的資金でリハを提供するのですから,可能な限りどこでも,誰でも公平なリハを受けることができるようにするために,EBPによる標準治療は非常に合理的だと思います。
今後もさまざまな形で,誤解なくEBPの重要性についてセラピストの方々に発信していけたらと思います。
セラピストの技術に対するエビデンスが示すこと
——エビデンスを語るうえで,ベテランのセラピストの技術というのも話題になるかと思います。後世に伝えていく際,どのように注意すべきでしょうか。
竹林:
ベテランの技術や知識はその方がセラピストとして過ごすなかで培われた尊いものです。
それと同時に,その技術や知識は,『そのベテランの経験の範疇を超えないもの』であるという負の部分も孕むものです。
こういった汎用性,ほかの経験との比較といった観点も含めて,お話を進めていきましょう。
まずは多様に学ぶこと,そして,先行研究の知識を参考にする,という視点です。
例えば,一昔前の自己研鑽のデザインとしては,リハにおいて,1つの手法を極めるというものであったかなと思います。
これは,入職した病院で多くの方が使用している『○○療法』と呼ばれる特定のアプローチで患者さんのすべてに対応しようとするものです。
ただし,1つの手法やコンセプトで患者さんの多種多様な症候に対応するのはとても難しいことですし,近年では複合的に各々特徴がある手法を併用し,患者さんの症候に当たることが一般化してきています。
こういったトレンドのなかで,EBPを進める際に大切なことは,患者さんに世の中で効果があると言われている手法にどのようなものがあるかについて紹介したうえで,医療者はどの方法がよいと考えているかを伝えることです。
例えば,推奨されているほかの手法があるにもかかわらず,医療者が確認を取らずにある手法で介入をし,結果が伴わなかったとします。
退院後,医療者が提供した以外に推奨されている手法があったと知った患者さんは,どれだけ後悔するでしょうか。

加えて,医療者が患者さんに利用する手法を検討する際に必要なのが『比較』に関する意識です。
例えば,われわれセラピストは,過去に診療した患者さんの結果から,『こういった特徴をもっている患者さんにはこの手法がよさそうだな…』といった経験は誰しももっているものだと思います。
ただし,この経験には落とし穴があります。
その落とし穴は,過去の経験において『同患者に同時期に複数の手法を導入し,比較検討することは不可能である』という視点の欠如です。
つまり,自身が過去に提供した手法は確かに効果的であったかもしれない。
ただし,そのほかの手法を用いた場合にはよりよい回復を導くことができたかもしれない,といった視点です。
この点においては,医療者自身の経験,もしくは先輩から教えてもらった経験だけでは,対応が不十分です。
ですので,多くの患者さんを対象にした『比較試験』であるRCTの結果やシステマティックレビュー,メタアナリシスの結果を参考に取捨選択をする必要があるかもしれません。
次に,患者さんにとって効果があると感じた(体験した)手法については,きちんと疫学的な手法を使って,後世に残していく必要があると思います。
リハ領域には,効果があると先人が考えている,臨床的にも利用されているにもかかわらず,エビデンスが不十分な手法が多くあります。
ざっくり言うと,エビデンスは正確なデザインの研究数が多いほど確立されていきます。
研究数が多ければ十分,少なければ不十分となります。
また,十分エビデンスが確保されたうえで,その手法の効果があるのかが問われることとなります。
つまり,エビデンスが不十分と言われる手法は,正確な研究デザインを用いた比較研究が少なく,効果を検証するまでに至っていないということになります。
ですから,エビデンスが不十分と言われる手法にかかわる臨床家や研究者は手をとって協力し,その手法の効果を検証できるように,まずは臨床研究を積み上げる必要があります。
医療保険下のリハと遜色ない自費リハのシステム確立に向けて
——先生は自費リハにかかわっていらっしゃるかと思いますが,コンセプトはありますか。
竹林:
自費リハには安全性・公共性・妥当性・再現性が必要だと考えています。
ですから,まず医師や地域の医療機関との連携は必須だと感じています。
私の実践では,提携した地域の医療機関の医師から指示書をいただきます。
そのうえで,それらに則り,リスク管理,手法の決定をEBPによって実施していきます。
また,自費リハ内における体調不良などに関しても,地域の医療機関と提携し,オンコールで医師の指示を受けられる体制を整え実施しています。
われわれの自費リハは,慢性期の脳卒中患者さんにサービスを提供する際,まずガイドラインは何かというところから説明を始めます。
ガイドラインについて知ってもらったうえで,患者さんの個別性に応じてエビデンスが十分で効果が検証され,推奨がなされたアプローチを中心に提供しています。
もちろん,患者さんがそれらの議論を通じて,それ以外の手法を求められる際は,その理由についても議論・合議のうえで,個別性に従って採用することもあります。
つまり,自費リハといっても従来のリハとの違いは保険適応の有無のみで,現状のルールを厳しく遵守しつつ,実施しています。

——先生が今後挑戦したいこととして,全国どこでもリーズナブルに正確性の高いリハを受けられる自費リハのサービスの確立を挙げていましたが,どのような構想なのでしょうか。
竹林:
昨今医療費が高騰していくなかで,現在は疾患別に算定されている診療報酬が医療費削減のために包括的に算定がなされたり,リハの単位数が減少するような未来が来るかもしれません。
一方で,高齢化がさらに進めばリハのニーズが高まるにもかかわらず,回復期を含め,十分なリハを受けられない患者さんが増えてくる可能性があります。
そういった状況のなかで,自費リハがそのような方々に適切なリハを提供できるいち選択肢になればと思っています。
従って,公的保険外に当たる自費リハであっても,医療との連携やEBPに基づく質の高いサービスを提供する必要があると思っています。
また,社会のインフラとして安定した運営を継続するためにも,行政や企業などにもこの必要性をアピールしていく必要もあると感じています。
仕事を通じて実感した自分の役割
——そのような考えの変化には,何かきっかけがあったのでしょうか。
竹林:
これまではリハ領域のなかで,脳卒中後の手の麻痺に苦しむ患者さんやそのリハにかかわるセラピストのお役に立てればと専門分野である上肢に関することのみ仕事の依頼をお受けしていました。
でも,昨年くらいから自身の成長を継続しなければならないと考え,新しいことにも積極的にチャレンジしていこうと思っています。
また,そのチャレンジ自体も作業療法をアピールする機会にもなると思い,今までお受けしていなかった部類の依頼であってもお受けするようにしています。
ありがたいことにさまざまな方に声をかけていただき,仕事の幅も広がり,大変なこともありますが,楽しんで仕事ができています。
——仕事の幅が広がったことで心境の変化はありますか。
竹林:
いろいろな仕事に取り組むことで,さまざまな業界の方とお話できて,非常に刺激を受けています。
自分自身の了見も狭かったなと実感していますし,まだまだ知らないことばかりだと感じています。
また,そういったかかわりのなかで,自分にしかできない仕事・役割もみえてきた気がします。
ただし,色々なことにチャレンジするなかでも,自分の本分については,蔑ろにしてはいけないとも感じています。
私にとっては,大学における教育活動と研究活動です。
特に後者のなかでも,世の中の問題を解決するための研究を行い,論文を執筆することについては,疎かにしてはいけないと感じています。
この軸足をはずしてしまうと,すべての活動が音を立てて崩れ去る気もしています。
ほかの仕事も広くチャレンジしつつ,論文執筆を高いレベルで実施するということは,プレッシャーでもありますが,この点はぶれることなく継続していきたいなと思っています。
第2回では,臨床における科学的思考の重要性とエビデンスの位置付けについて伺うことができました。第3回では,先生自身の取り組みと根底にある想いについてお話しいただきます。
【竹林 崇先生プロフィール】
〈略歴〉
大阪府生まれ。2003年川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科作業療法専攻卒業後,同年兵庫医科大学病院リハビリテーション部入職。2018年兵庫医科大学大学院医科学専攻高次神経制御系リハビリテーション科学修了後,博士(医学)を取得。同年大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科准教授として着任し,2020年4月より同大学院教授(2022年4月より大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科教授),現在に至る。専門分野は脳卒中後上肢麻痺に対するアプローチで,関連する論文・書籍を多数執筆。X(旧Twitter)をはじめ,YouTube,Instagram,noteなどのSNSやオンラインサロン,Webセミナーを通じてセラピストに情報提供を精力的に行っている。
【主な著書】
行動変容を導く!
上肢機能回復アプローチ -脳卒中上肢麻痺に対する基本戦略(医学書院)
上肢運動障害の作業療法 -麻痺手に対する作業運動学と作業治療学の実際(文光堂)
作業で創るエビデンス -作業療法士のための研究法の学びかた(医学書院)
PT/OT/STのための臨床に活かすエビデンスと意思決定の考えかた(医学書院)
作業で紡ぐ上肢機能アプローチ -作業療法における行動変容を導く機能練習の考えかた(医学書院)
作業で語る事例報告 第2版 -作業療法レジメの書きかた・考えかた(医学書院)
PT・OT・STのための臨床5年目までに知っておきたい予後予測の考えかた(医学書院)
急性期・回復期でおさえておきたい脳卒中作業療法の心得(メジカルビュー社)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
