
「松の木の物語 ~ (その1)唐臼山の大きな松」
平成4年(1992年)12月。
広告代理店A&Aの堀内さんから電話あり。
仕事の依頼かと思って受話器を取ったが、そうではなかった。
「こないだ預かった同人誌、さっそく読ませてもらったよ。なかなかいいねえ。君らしい感性が感じられて面白かったよ。そこでねえ、君に会わせたい奴がいるんだよ」
彼に渡した同人誌に掲載されていた作品は、ある1本の木にまつわるエピソードを記したエッセイだった。
3歳のころから10年間住んだ常盤町にあった自宅のそばに立っていた梅の木。
幼稚園では、その木を貼り絵として描いた。
18歳のときには自作の歌の題材にした。
20代のときには大学のサークルの文集に、30代のときには同人誌にエッセイとして書いて投稿した。
紹介したいと言ってきたのは、彼と同い年の幼馴染み。1本の木にこだわっているのだが、そのこだわりが周囲の人々から理解されず、動きがとれなくて困っているという。
詳しい事情は簡単に説明できないので、とにかく1度実際に会って、直接話を聞いてもらえないかと言われた。
「君だったら、彼の気持ちが理解できるんじゃないかと思うんだよ。なんとか力になってやってほしい」
** ** **
その人、村山隆さん(当時46歳)と初めて会ったのは、翌年の正月。知り合いの方のご自宅での新年会の席だった。
紹介されてすぐ、彼は口を開くなり堰を切ったようにその木について語り始めた。
子供のころから、その周りで遊んだりキノコを採ったりと、親しんできた大きな松の木。下之郷にある村山さんの自宅から近い、唐臼山と呼ばれる里山の頂上に立っている。
その枝ぶりを見ると、明らかに人の手が入っており、村人から大事に管理されてきたことが分かる。そばに雷避けの祠や、古墳があることから、そこはかつて神聖な場ではなかったかと思われる。
熱っぽく語られる彼の口調から、どれだけ、大切に思っているかが伝わってきた。
新年会から遡ること3ヶ月。平成4年10月。
キノコを採りに唐臼山に行った村山さんは、その木の枝葉が枯れ始めているのを見て、ショックを受ける。緑の部分は、残すところあと僅かで、ほぼ枯死寸前という状態だった。
どうやらマツクイムシにやられたらしい。マツクイムシ被害に遭った木は、幼虫が羽化する前に、根こそぎ切り倒して処理しなければならない。市の条例でそう決められている。このまま何もしないでいたら、跡形も無く消え去ってしまう。
そこにあって当たり前だと思っていた。だが、枯れている姿を見て初めてその大切さに気付かされた。頂上に大松の立っていない唐臼山など、考えられない。
少年時代の様々な思い出が頭を巡った。竹で自作したスキーでの沢すべり、刺されながらの地蜂捕り、藪の中に造った基地、探偵ごっこやチャンバラ遊び、マツタケを競い合って採ったこと…、そんな原体験が、松とともに消え去ってしまう。そんな空しさが胸に迫ってきた。
彼は、すぐさま地元紙の信濃毎日新聞に手記を投稿した。それは、約1ヶ月後に掲載され、彼のもとに、同調する手紙や葉書が送られてきた。記事を読んで、初めて老木の枯死を知った地域住民も多かった。
大松が、下之郷第10班=旧新田村(しんでんむら)にとってどんな存在だったかを、より詳しく知るために、村山さんは、地元で生まれ育った年長の人々を訪ねて回った。そんな中で、最長老の声が殊更胸を打った。
「あの松は、昔から新田村の象徴木だった。村の宝だった。ただ灰にしてしまってはもったいない。何とか村中でお別れして、永遠に残せないものか。若い衆に動いて欲しい」
唐臼山は、今では、上田女子短期大学付属幼稚園の敷地の一部になっている。かつて、地域が大学を招致した際に、住民が唐臼山に出入りしても良いということを条件に、土地を安価で売却したという経緯があった。
そこで、村山さんは、地区の有力者に相談し、短大側に松に対する住民の気持ちを伝えてもらい、市の農林課に、伐採を待ってもらうように働きかけた。
年が明けて、元旦に開かれた下之郷第10班の新年総会で、旧班長からの発議という形で、老松が枯れた原因調査と供養祭を提案した。
ところが、彼の予想に反して、住民の反応は実に鈍いものだった。
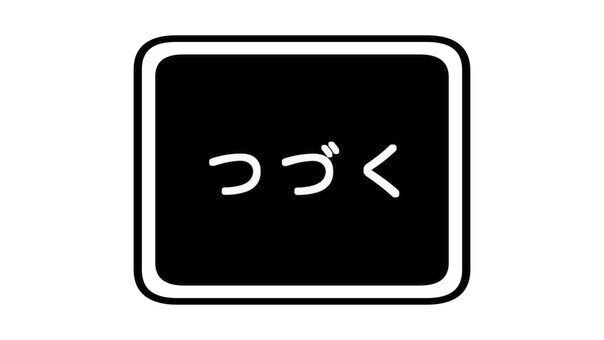
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
