
故障を防ぎつつ運動能力を劇的に向上させる方法:出力順序マネジメントと潜在運動系
今回はボディワークについての記事です。
私は医療系の研究所で心身に関わる研究してきた経緯から、身体の専門家でもあります。これまでに武術・気功・ヨーガ・整体などについて研究してきました。
今回は、故障を防ぎつつ、運動能力を向上させる方法である、
「出力順序マネジメント」
と言う概念について述べたいと思います[潜在系用語]。現代の運動学は間違っている可能性があります。そうした意味で、読み物として、知識として、運動を専門としない方も読んでいただければと思います。
⬇️PDFからもご覧いただけます。
出力順序マネジメントとは?
ざっくりと言うと、運動の正しい順序とは、内側から動き、そして外側が動くと言うものです。
内側からの動きとは、以下のような感じの動きです。
私(佐藤)によるヨーガ(ナウリ)のデモ⬇️
私(佐藤)による太極拳のデモ⬇️
出力順序マネジメントとは、内側を先に動かし、後から外側を動かしていくという、力の出し方のマネジメントを行う概念なのです。
軸と出力順序の関係性
内側から動くというのは、先にインナーマッスルから出力し、アウターマッスルが後から出力する、ということです。
なぜインナーマッスルから動かなければいけないのかと言うと、インナーマッスルが軸を形成するからです。この軸が形成されないと、正しい運動ができなくなり、パフォーマンスが落ち、故障の原因になります。
インナーマッスルとは正式な解剖学用語ではありませんが、ここでは比較的内側にある深層筋群として捉えていきます。
例えば、肩のインナーマッスルですと、棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の四つの筋肉です。これをまとめてローテーターカフ(回旋筋腱板)と言います。これが上腕骨を体幹と繋ぎ、軸を形成しているのです。
肩の場合、三角筋などのアウターマッスルが過緊張し働きすぎると、軸から外れた運動を行ってしまうため、肩の故障(インピンジメント・シンドローム)が起こるとされています。

ですからまず、トレーニングとしては、三角筋をなるべく弛緩させて、肩の軸を形成してから動くことが重要となります。
運動指導の場合、
「肩の力を抜いて」
とアドバイスを受けますが、これは言い方を変えると、
「軸を形成してください」
ということなのです。
野球選手でもメジャーに行ってムキムキになると肘を故障する方が多いですが、これはアウターマッスルが主導され、出力順序マネジメントが上手く行われていない可能性があります。
プロとアマの出力の違い
野球のピッチングにおいて、プロとアマチュアの選手の比較のデータがあります。ここでも三角筋はリラックスしているのです。

そしてインナーマッスルはバランスよく働いています。これは軸の形成を意味すると考えられます。つまり、プロとアマの違いは、
「軸を形成できるか、できないか」
の違いとも言えます。
現代の運動学の間違い
多くのネット記事を見ると、アウターマッスルは主に動作時に力を発揮し、インナーマッスルは関節を安定させて補助する役割であると書かれています。確かにインナーマッスルは関節を安定させますが、前述のデータを見ると出力にも参加していると思われます。もちろん、回旋筋腱板のそれぞれの筋肉には作用の機能があります。その作用は、名前の通り、回旋運動です。そして、その回旋運動を行う時に軸が形成されるのです。
動物の進化を見ると、インナーマッスルが先に発達し、その上にアウターマッスルが形成されています。
例えば、四つ足の爬虫類・哺乳類は手足が細いです。
それに対して、ゴリラのような霊長類は手足が太いです。
前者はインナーマッスル的、後者はアウターマッスル的な身体と言えます。
この進化の順序通りに筋肉を出力させていくのが、自然の理に合った運動ではないか、と考えられるのです。
ですから出力順序マネジメントにおいて、インナーマッスルが補助筋ではなく主導筋であり、補助するのはアウターマッスルの方になります。すなわち、まずインナーマッスルが働き、インナーマッスルが支えきれないような重い負荷が身体にかかった場合は、アウターマッスルが補助をする、という順序になるはずです。
というのも、私の身体がそのようになっているからです。
このことの詳細は拙著、『東洋医学と潜在運動系』(たにぐち書店)で書きました。
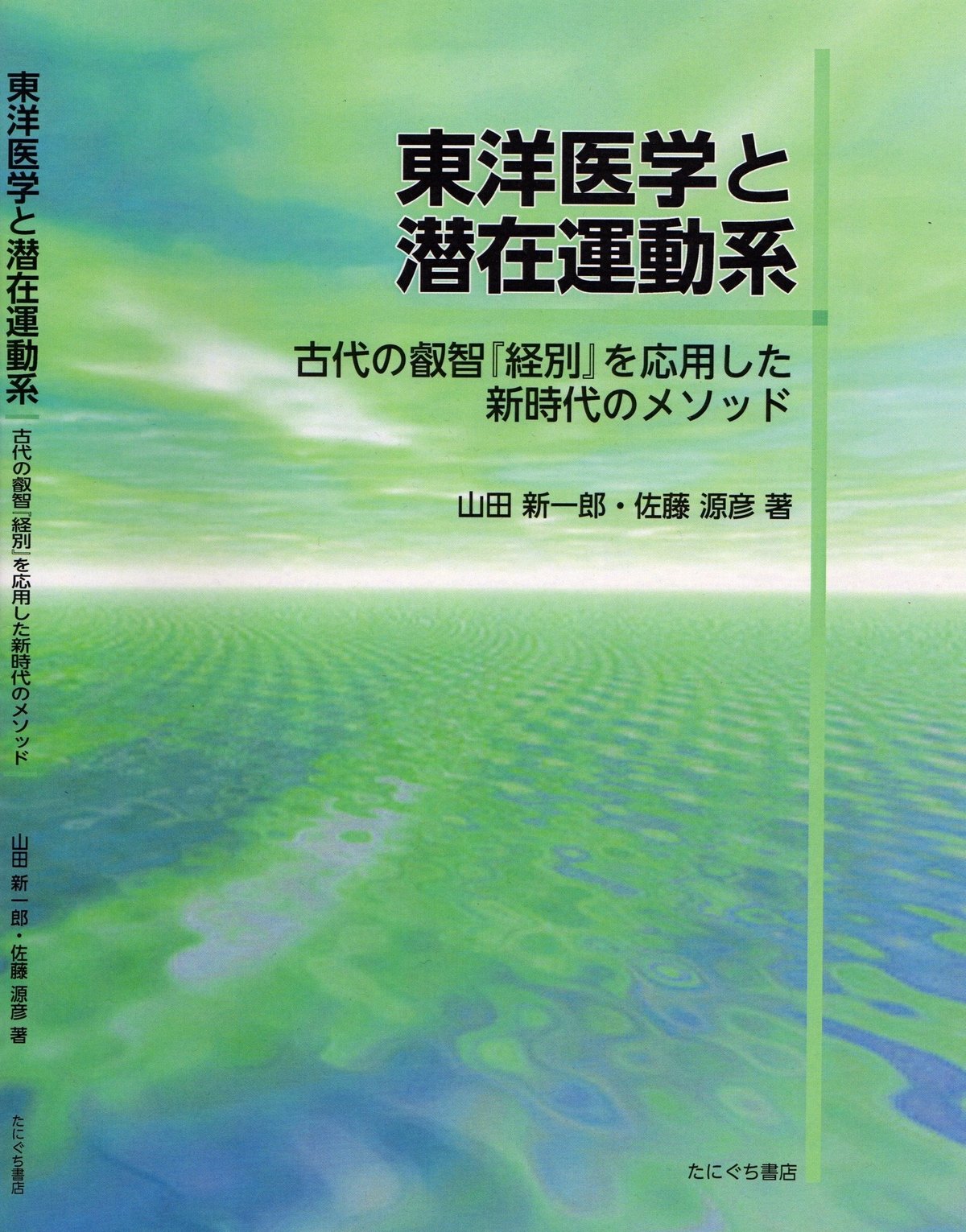
出力順序マネジメントの実践
ここで問題なのは、アウターマッスルは表層にあり、大きな筋肉であるため、認識がしやすく、そのため力が入りやすいです。それに対してインナーマッスルは、深層にあり小さい筋肉なので、認識がしにくいところがあります。そして、重いものを持ってトレーニングしてしまうと、すぐにアウターマッスルが出力してしまいます。
先行してインナーマッスルを出力させ、軸を形成するには、ダンベルなどの負荷をかけずに軸運動を行うことです。
以下のように腕を肩の高さまで持ち上げ、そして、肩口の筋肉である三角筋を触れてください。

多くの方は、この状態にすると三角筋が緊張してしまいます。
これを様々な方法を駆使して完全に弛緩させていきます。
この純粋なインナーマッスルの単独出力ができていれば、非意識でもインナーマッスルが先行して働き軸が形成されます。
この純粋深層筋運動を行うのが出力順序マネジメントの第一歩です。
純粋深層筋運動が非意識で行うことができてから、その次にアウターマッスルのパワーを乗せていけば、正しく強い運動パフォーマンスが発揮されます。
大学の研究室での実験
ちなみに私は、ダンベルを持っても三角筋は一切緊張しません。

これは大学の研究室で、バイオメカニクスの専門家(教授)二名と多くの学生の協力を得て実験したことあるのですが、筋電図でも、三角筋の反応はありませんでした。
その教授は、私に向かって
「不思議な身体をされていますね」
と言われたので、骨格とインナーマッスルで保持しています、と説明した記憶があります。これは20年程前の話になります。
三角筋の作用は外転なので、これが弛緩しているということは、働いているのは棘上筋と棘下筋の上部です。私の感覚では、棘下筋の上部が働いているように感じます。
潜在運動系と出力順序マネジメント
更に出力順序マネジメントを深めるためには、脳の使い方にもフォーカスをした方がよいです。
「ああしよう、こうしよう」
と、意識的に身体を動かしてしまうと、外の筋肉が過緊張してしまいます。ですから何も考えないようにして、無心で身体を動かすようにします。
昔の剣豪が技術に限界を感じ、禅を行うことで更なる高い境地に達したとされます(剣禅一致)。これも禅によって脳が最適化され、出力順序マネジメントが正しく行われるようになったからだと考えられます。
ですから運動時のメンタルマネジメントは「無心」です。
しかし、いきなり無心になるのは難しいので、その中間地点をいくつか設けます。それがイメージです。
イメージを用いることで論理的な左脳が休息し、理性の坐である大脳新皮質が休息しだします。どのようなイメージを用いるかは、また、どこかでお話ししたいと思います。
最終的には、このイメージも消していき、無心となり、非意識的な軸運動が体現されます。そして、その上でアウターマッスルのパワーを乗せていけば、高いパフォーマンスが発揮できるはずです。
出力順序マネジメントは、もちろん、肩だけではなく他の部位にも適用されます。そして、それを行うには動物時代の脳身体システムである潜在運動系を用いると、非意識的に行いやすくなります。
潜在運動系に関しては、初級講座を随時開催しています。
一般の方から施術家・運動指導士などの専門家など、様々な方からの申し込みがあります。
次回は2024年5月25日にワンデーセミナーをしますので、よかったらご参加ください。
潜在運動系講座
https://note.com/mbbs/n/nb79b58f1afa8
申し込みは公式ホームページの「お問い合わせ」からどうぞ。
もしくはフェイスブックからも受け付けております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
