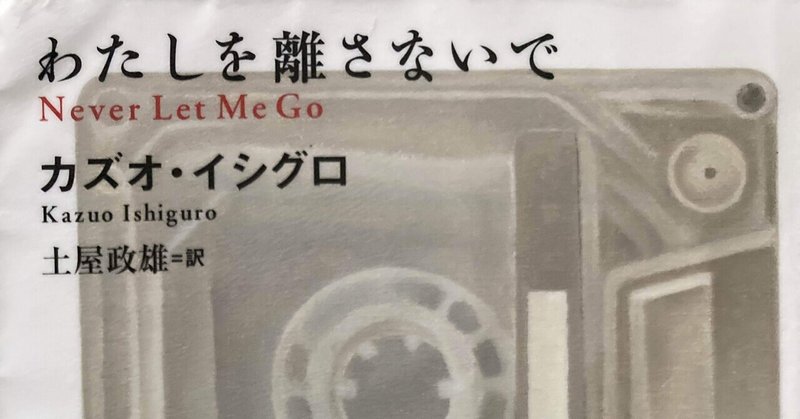
「わたしを離さないで」を読んで、救いようのない「リアル」と対峙する
「わたしを離さないで」、挑戦は二回目。
昔、高校時代に一度挑戦したけど、何故だったか読まずに返却した思い出がある。なんでやったっけ。時間が無かったのか、読み進める気力が無かったのか。まあそんなことはどうでもいいけど、数年の時を経てリベンジ果たした。もっと早く読んどきゃよかったな、と思うのと同時に、あの時読まなくて正解だったなとも思う。今やからこそ読破出来たんかもしれんね。
ネタバレをしない程度の感想を書くとしたら、おすすめポイントは「精密さ」やと思う。主人公の人生の出来事がかなり精密に、会話は勿論、会話している場所から見える物や匂いや音まで想像できるくらい細かい描写が多い。描写をやたらめったら増やしてしまうと、普通は長ったらしくて回りくどくて読めたもんじゃないんやけど、ここではその描写の全部が意味を帯びていて、それゆえに淡泊にすら感じる。描写が多いからこそ見えてくる登場人物たちの癖とか性格があって、すぐに愛着も湧いてしまう。出てくる人物名が多い気がして最初は圧倒されたけど、実際にキーとなるキャラクターは絞られているから頭の悪い私でもすぐ理解できる。
読後感が何かに似ていて、この気持ち何やっけって考えてたら、おそらく夏目漱石の「こころ」を読み終わった時の感覚。「こころ」は「人生で読んでおいて本当に良かったと思える小説ベスト5」に間違いなく入ってくる本なので、もしかすると「わたしを離さないで」も後々ベスト入りを果たすことになる小説なのかもしれん。
個人的に、「自分の持っている感情にぴったり重なる描写が出てくる小説」が「面白い小説」と定義できると勝手に決めつけてる。だから往々にして「自分と同世代の登場人物が出てくる小説」とか、「自分と境遇が似ている登場人物が出てくる小説」とか「自分と全く同じ悩みを抱えながらも生きている主人公が出てくる小説」を面白いと思いがちなのね。
でも、「こころ」と「わたしを離さないで」に関しては違う。なんていうか、全く自分と境遇が重ならない上に同世代でもなく、同じ悩みを持っているわけでもないのに、何故か主人公に感情移入させられてしまうのよ。それはさっきも言うたように「精密さ」が関係してくるんやと思う。主人公の生まれた環境、周囲の人々の反応、それに対する主人公の感情、感情とは裏腹な脳内の考え方、そういうのが詳細に描かれてるからこそ、自分の頭を主人公の頭と取り換えているような気分になれる。主人公の頭の中で組み立てられている色んな考え方に、自分もいつの間にか賛同して、同じように主人公と一緒に悩み始めてしまう。だからこそ、主人公の身に何か変化が訪れる度に同じように反応してまうのよね。言うたら、体内に手をそのまま突っ込んで心臓を取り出して、無理やり主人公の体内に入れこまれる感じ。……説明がドヘタ。まあそんくらい登場人物と一体になれるってことよ。分かってくれ。
▼▼▼以下、読んだことがある人にしか分からん話をします。ネタバレも含むので注意▼▼▼
これを読んで何を思うかって、「希望は無理に持たん方がいい」ってことかな。頭が悪いので踏み込んだ深い話は出来そうにない。ごめんやで。
何せこの小説、頭空っぽにして読む分には面白いエンターテインメント作品としても読めるんやけどさ。深く読もうと思えばいくらでも掘り下げることが出来てしまうと思うんよね。めっちゃ頭がええ人はこんな薄っぺらい感想を述べへんと思うんやけど、私は途中で考えることを放棄しました。
長くなってるので一番好きなシーンを一つだけ。
最後の最後、クライマックスもクライマックスのシーン。キャシーとトミーがマダムに会いに行って、そこでエミリ先生に会い、全ての真相を聞かされるあのシーンでキャシーが尋ねるこの台詞。
「どのみち提供を終えて死ぬだけなら、あの授業は一体なぜ?」。
これは読みながらマジで思ってた。結構早い段階で「提供」の意味するところが理解できるような仕組みになってたからこそ、じゃあなんで夢を持っても仕方がないような授業をしたんや? ってのはずっと疑問に思いながら読み進めてた。これも作者の意図したところなんかもな。読者にもずっとその疑問を漠然と持たせておいて、ここであえてそのまま聞かせる。そこでさらに登場人物との一体感を深めさせる。勝手に言うてるだけやけど。
で、その質問の後にエミリ先生が長々と答えるんやけど、最後の最後に一番シンプルな答えを言うてるんよね。
「あなた方にも魂が—―心が—―あることが、そこに見えると思ったからです」
……こんなにも救いようが無くて残酷な答えがあるかいな。もっとオブラートに包め!
ていうか、実際に登場人物たちは全員色んな人生を経て感情をぐちゃぐちゃにされてるんやから、心はあるやないか。しっかり育ってしまってるやないか、魂が。
でも、結局は心が育った上にそれが公に世界からは認められず、未来は何も変わらず進んでいくんやから一番残酷な終わり方。ヘールシャム育ちの生徒たちは、「提供者」の中でも恵まれた環境で育ったって先生たちは言うてたけど、ほんまにそうなんか? 授業にしろ噂にしろ、変な期待ばっかさせて、最終的にはそれ全部叶いません、貴方たちは特別ではありませんでしたって言われる残酷さ。こんな無慈悲な世界があるかよ。
さらにその無慈悲さを増幅させにくるのが、帰り際のキャシーとマダムの会話。「わたしを離さないで」を聴きながら踊っていたキャシーを見て、どうしてマダムは泣いたのかを直接聞いたシーンね。
「新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、効率もいい。……すばらしい。でも無慈悲で、残酷な世界でもある」。
今思ったら「無慈悲」も「残酷」もここの台詞で使われてるワードやったな。くどくて申し訳ない。
でもこの台詞も悲しくない? やっぱりマダムやエミリ先生のような「普通の人」と、「提供者」の間にはデカすぎる溝があんのな。結局「提供者」のことを「人ではない何か」だと思ってしまってるんよね。同じ人間としては認めてない、可哀想な子たちだと思っている。登場人物たちは「普通の人」と全く同じように考えて悩んで決定して生きてるのに。でも埋まらんのよ、どうしてもこの溝が。
なんかすごいさらっと書かれてたけど、エミリ先生もマダムも、生徒たちのことが「怖くて仕方がなかった」って書いてあったしね。私が追って読む分には、そんな怖い存在じゃなかったのに。
この本の魅力、「何を書くか」や「何を書かないか」がめちゃくちゃはっきりしてることやと思う。あんなに匂わせていたのにキャシーのポシブルは出てこなかったし。ていうかどういう仕組みで彼らが生み出されてるのかとか、技術面のことは全く触れられなかった。はっきりせん謎の部分もあるけど、それが謎だからこそリアルというか。全部語られてたら、逆に不自然な気もするしね。普通はポシブルは見つからない。普通は技術面のことなんて生み出された方は気にしない。希望は断たれる。思い通りにいかないことばかりで諦めも必要であるってところをちゃんと書いてある辺りが、「リアル」に繋がってるんかもな。
私もあれかな、将来どうなっていくかはもうこのまま変わらんのやろか。それとも「提供者」じゃないから変えていけるんやろか。ポジティブな捉え方も出来るけど、この小説を読んでポジティブな捉え方をするのはこの小説に出てくる「普通の人」と同じ人間になってしまう気がする。それが果たして正しいことなのか、馬鹿な私には見当もつかんな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
