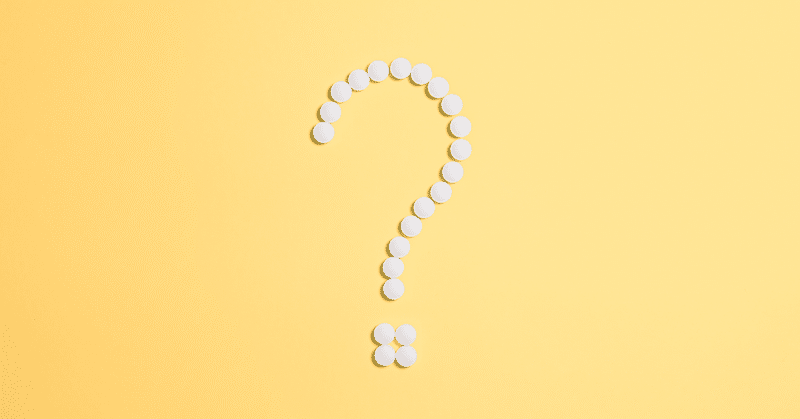
【737/1096】行動変容のための問い
メタファシリテーション®という手法の基礎講座、ステップ3まで修了した。
メタファシリテーション®はムラのミライの和田信明さんが使っていた対話の方法を、中田豊一さんがそばで見て、体系立てて、他人が使えるようにした手法で、「なぜ?」「どうして?」を使わずに、事実を質問していくという手法である。
この手法を学んで思ったことは、聞き手が相手と信頼関係を築きながら、事実のみを質問していくというのは、日常でほとんどしていないし、これをしてくれる人もいなかったということだった。
課題(悩み)を具体的に解決するとき、行動を変容させるときにどのように問い立てをするか?
Whyを3回、というのはよくある。
これが功を奏する場合もあるのだが、きつく感じるときもあり、またWhyは責められていると感じることも多々ある。
この事実質問は、Whyを禁じていて、さらに、聞き手側がアドバイス(提案、提言)をしないという手法で、話すほうも話しやすいし、すごく聞いてもらった感じがするのだ。
私は、気持ち、感情を丁寧に聴き、その先のニーズをとらえるという聴き方をカウンセリングで学んできたので、この課題解決のための事実質問による聞き方はかなり新鮮で驚きがあった。
そして、実際に行動を変えるときには、事実質問をされて自分で導き出した答えを持って行動を変えるほうが、圧倒的にしやすいというのが自分の経験としてある。
気持ちを聴くのはいったん置いといて、今の現実をどう変化させるか、問題はなにか、などをつぶさに聞いて、明らかにしていくのがとても面白い。
ステップ3は、行動変容のための問いかけ方を練習したのだが、これは本当にけっこう自分の価値観が邪魔をすることがあるなと思った。
この人はこういう人かも?と推測して、問いを立ててしまうと、事実を聞いているようで、自分の推測にそったことを聞いてしまう。
事実質問は、相手の自己肯定感に配慮するというのが大前提としてあるので、話しにくそうにしていたら、そこはパッと手放す必要がある。聞き手の聞きたいことを聞くのではない。
理想と現実の距離感が離れすぎていると、人は行動しない。
ただ思い描いて終わってしまう。行動するために、理想と現実の距離感を詰める質問を重ねていくというところが、なかなか難しいが、面白かった。
質問することで、相手の情景がありありと浮かんできて、その情景を共有しながら問いを重ねていくので、お互いの誤解が生まれにくいし、思い込みが減る。
最初(2017年頃)にこの手法に出会って使い始めた頃は、質問にすぐ行き詰まったし、問題を解決したい自分の想いから質問していることに気づかず、事実質問ではなく、その体を装った相手を追い詰める質問をしてしまったり、具体的につめるよりも曖昧に散らばしてしまうことも多かった。
でも、今日は、そのときよりはかなり上達したかも?!と自分の実感が持てたので、諦めないで続けてきてよかったなと思った。
子どもとの対話にもすごく役立つので、どんどん練習して使いこなしていきたい。
メタファシリテーションの本↓
答える側は、答えやすく、自分が答えを発見するのですごく面白いのだけれど、問いかける側はかなりの技術力がいるなと思う。
でも、できるところから使っていけるので、日常でも使えるところで使っていこう。
では、また。
1096日連続毎日書くことに挑戦中です。サポートしてくださるとものすごくものすごく励みになります◎ あなたにも佳いことがありますように!
