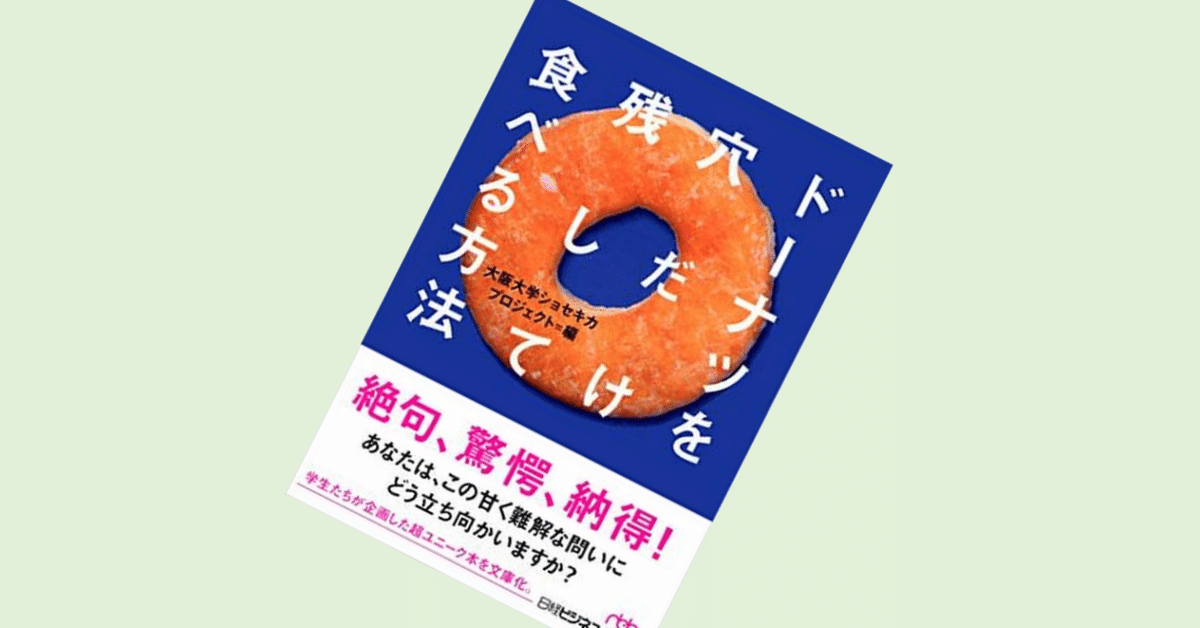
【本】ドーナツを穴だけ残して食べる方法
サブタイトル 越境する学問ードーナツの穴からのぞく大学講義
著者:大阪大学ショセキカプロジェクト(編)
出版:日経ビジネス人文庫
読んでいた「問いのデザイン」という本の中で紹介されていて、手に取りました。
”問題を捉える際の「道具」の重要性についてよく分かる”
”同じ問題であっても、どのような専門性を通して眺めるかによって問題の解釈の仕方が変わってくる(ことが分かる)”
と言う紹介は、仕事に活かせそうという興味。
それ以外のこんな紹介ワードには、持ち前の好奇心が反応しました。
・越境する学問
・一風変わった問題に、様々な学問領域の研究者達が自分の専門分野に基づいて解決しよう試みる
・エンターテイメントとして楽しめる
本を開くと、へぇ~へぇ~の世界でした。
いろんな学問領域の先生方に阪大書籍化プロジェクトの学生さん達がお題を持ち込み、自分の専門性の知見を駆使して考察してもらう、という知的かつ
面白すぎる話の展開の数々。
ドーナツの穴問題は以前から時々持ち出されては人々を引きつけてきたみたいですね。でも、この本は随分違ったアプローチでまさに「ドーナツの穴から覗く知の世界」という感じでした。
13の話が出てきますが、私が特に面白く感じた話(先生)を3つ紹介します。
工学の視点から、如何に削るか、削るとは、を解説してくれる先生
削る、切るってそういうことか!
はさみや包丁で何故、物が切れるのかも知れました。
大真面目に、でも丁寧かつ愉快にドーナツを削る方法を論じ、最後には発想を転換してしまう方法に行き着きました。
最後に発想を転換するところに、こうやって工学は不可能と思われた物事を可能にしていろんな物を改良開発してきたんだろうなぁと感心。
意表を突く展開でうならせてくれた美学の先生
美学ってそういう学問なのか!と知れたことと、イメージとはかなり違った話の展開が興味深かったです。
説明の仕方やたとえ話がとても面白くて、「ふむ、なるほどねぇ」と思いながら話に引き込まれました。
最後は先生の仰る「ドーナツは家である」という結論に思わずうなずいてしまいました。
たまに美学の視点で物事を見るのはとても新鮮でいいけれど、毎日こんな風に考えて暮らしていたら大変かも。。。と思ったり。先生の日常生活はどんな感じなんだろうと想像が拡がりました。(笑)
四次元空間を持ち出して可能であると大真面目に立証する数学の先生
分かりにくい四次元空間での事象のありさまを、自分の指とドーナツを使って確認しながら話しについて行けるように工夫してくださっていて、ほんまかいな?!と思いながらも、楽しく四次元空間の世界に思いを馳せました。
繰り返し、突拍子もない感じだが数学において論理的思考は自由、何でもあり、と数学の面白さを話されていて、高3で無限∞の入った計算が出てきたときに抽象的すぎて自分の想像力がついていけなくて親近感0になった数学にも、改めて面白そうだなぁと感じさせてもらいました。
出てくるどの先生も、大真面目に、でもとても愉快に分かりやすく話を進めてくれていて、本当に賢い人って難しいことを易しく楽しく話せるという例を並べてもらった感じ。
こんな楽しい話を学生時代にいろいろ聞きたかったなぁ~
そして、確かに、どういう軸を持ってどんな視点で物を見るかによって
感じ方や発想も全く違った展開になることを実感。
日頃から、自分に馴染みのない分野の話を聞いたり、自分とは違う世界で生きている人の考えを聞いたりすることって、やっぱりとても大切、
と改めて感じさせてくれる本でした。
先生の話と話の間に出てくる、世界各国のドーナツ事情も楽しかったです!
最後までお読み頂きありがとうございました ♪
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
