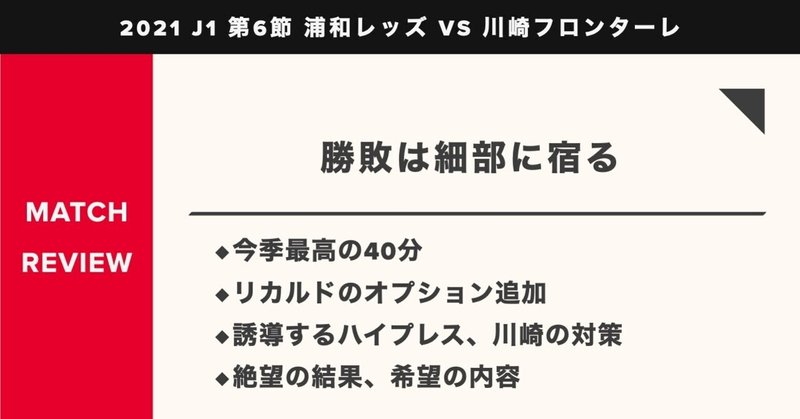
【レビュー】勝敗は細部に宿る - 2021 J1 第6節 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ
この記事でわかること
・今季最高、前半のパフォーマンス
・飲水タイムのオプション追加
・狙い通りのハイプレス、川崎の対策
・試合を壊した細部の甘さ
・絶望の結果と希望の内容
「メンタルが弱いから連続失点する」
悪夢の4分間で試合が壊れてしまった川崎戦。近年の課題である連続失点による大量失点がまたも繰り返されました。こういった試合の時は、一気に崩れたポイントからメンタル面に原因を求めがちですが(実際にそうである可能性は高いが)、同時に試合内容を冷静に振り返ることが重要です。
日程面などの不利を考慮して現実的な選択をした札幌戦を経て迎えた、王者・川崎戦。開幕から続いた厳しい連戦も最後となり、次の試合を考慮する必要もない中でリカルドが選択したのは、真っ向勝負。
自分たちがボールを保持し、相手の出方を伺い、あるいは相手を動かしてダメージを与える場所を取って前進する。キャンプから継続している本流のやり方で挑みました。
公式戦7戦目となる新生・浦和が、王者である川崎相手にどこまで自分たちの強みを表現できたのか、足りない部分はどこだったのか、解説していきます。

狙い通りに相手を外した前半
日程などの面で"現実主義"なゲームプランを選択した札幌戦。力量差は確実にある王者相手にどうするか注目していましたが、今節は真っ向勝負。
後ろから繋ぐことを厭わず、川崎からボールを取り上げて主導権を握り、相手を引き出して空けたスペースに人を置いて前進するサッカーを目指して試合に入りました。
そうして生まれたのは今季最高の前半。ボールを持って主導権を握りたいのは川崎も同じで、浦和がボールを持つと前から嵌めてボールを取り戻すためのハイプレスを仕掛けてきましたが、それに対して浦和は論理的な前進に成功します。
横浜FM戦で不足が見られる場面もあった浦和最終ラインの立ち位置についてもこの試合では良好。何度もポジションを取り直し、岩波や槙野が西川の高さ、ともすればゴールラインまで下がるような場面も目立ちました。
川崎のプレスは3トップ+IHを上げる形が基本構造。これに対して浦和はアンカー脇を中心に狙いを定めて関根と汰木を中央気味に配します。
西川も組み込み、最終ラインの立ち位置から得た優位を活用しながら相手のファーストディフェンスを掻い潜り、相手のライン越えを何度も実現します。
前半飲水タイムまでによく見られた形としては、宇賀神を起点とした右サイドからの前進。岩波を捕まえに前に出る長谷川の裏、かつIH脇坂と距離を取る位置に宇賀神が立つと、そこを起点に相手が空けるスペースを次の選手が取っていくのが基本構造。今季の原則を表現できていたと思います。

また、今節再びトップ下に入った小泉のビルドアップを助ける降りる動きは健在。川崎の中盤は3枚で、IHが積極的に前にいく場面や脇坂が宇賀神へアプローチする場面も多いため、後方から降りてくる小泉をシミッチがケアせざるを得ない状況を作り出します。その結果として、健勇や関根がアンカー脇、脇坂の裏のスペースでビルドアップを助ける立ち位置を取ることができました。
また、19:00は横浜FM戦で課題として挙げた最終ラインの立ち位置が改善されていたシーン。西川がボールを持った時点で岩波と槙野が幅を取り、同じ高さまで下がります。
それを活かして岩波自身が時間とスペースを獲得すると、宇賀神を起点に右サイドから相手の密集を突破するビルドアップを見せました。この過程でボールを狩りにきたシミッチも外し、中央のオープスペースを獲得。その場所で小泉が前を向いてボールを持つことに成功しました。

しかし、相手を外すことができてもその先になかなか進めないのがこれまでの浦和。この場面でも、健勇や関根がビルドアップに参加したため、相手最終ラインと勝負できる状態なのは汰木だけ。
オープンスペースを獲得して前を向きますが、残念ながらそれを次の局面、つまりゴールへ迫るフェーズへ活かすことはできませんでした。その2分後に飲水タイムを迎え、リカルドは次の一手を打ちます。
加速を試みるリカルド
相手のハイプレスをかわして第1ライン、第2ラインを越えることはできていた浦和。しかし健勇のボレーシュートを除けばゴールに迫っているとは言い難い状況でもありました。
その状況下で、リカルドは飲水タイムを境に、よりゴールへ近づくために配置に変化を加えます。具体的には、ボランチの敦樹か金子が右に降りるパターンを追加すること。
これにより宇賀神を外側かつ高く押し出して立ち位置の高さを確保。金子が降りた分は小泉が補いますが、健勇と関根をビルドアップから解放して汰木と1トップ2シャドーのような形で相手のDFラインと対峙させます。また、相手のMFラインを越えれば、大外を宇賀神と山中が取って5レーンを埋めます。

最初の前進に関わるフェーズから関根と健勇を解放して前に残し、同時に4バックに対して5枚を関与させて相手DFラインをブレイクしようという狙いだったと推測します。
29:10のシーンはその狙いがもう少しで結実しそうな場面でした。金子を右に降ろしたことで長谷川とダミアンの間を広げると、関根がSBである旗手に与えている影響を利用して中間ポジションを取る宇賀神。
川崎としては、宇賀神に対してIHの田中がケアに向かわなければ行けないので動きますが、その瞬間に開いたパスコースへ岩波が縦パス。宇賀神の位置的優位が次のプレーに優位を与えた瞬間だったと思います。
パスを受ける健勇が後ろからアプローチする谷口を背負いながら小泉へのレイオフ(落とし)に成功すると、谷口が空けた裏を中に絞っていた関根が狙います。

しかし、ここで小泉がパスを出すことはできず。横から見ただけではコースがあったかはわかりませんが、最終的にチャンスにはなりませんでした。
追加した別の配置により川崎の中盤を動かして縦のコースを開け、その配置の貯金から最終ラインに対して有利な勝負を仕掛ける人員を配置してブレイクする。リカルドが加えたオプションが決定機に繋がり得た場面でしたし、試合の展開を考えれば繋げて得点まで結びつけたい時間帯でした。
誘導と規制、川崎の対応
前半のボールを支配率は54%を記録。王者相手に上回ったということは、良い攻撃だけでなくボールを回収する守備もできていたということです。
特に前半飲水タイムまではハイプレスを敢行してサイドで窒息させたり、川崎の苦し紛れのロングボールを回収する守備ができていました。
それぞれの選手が高い技術を持ってボールを支配する川崎は、主に2CB+アンカーでビルドアップをする形でした。前から奪いたい浦和が主に狙ったのは、谷口の左足。
右利きの谷口は長いボールや運ぶドリブル、縦パスなどの武器を持っていますが、彼が利用できるスペースを狭くして左足でボールを扱わせる状況に追い込めば精度は落ちます。
浦和は健勇と小泉からボールを右側に誘導して谷口に持たせると、関根も予測を持って旗手にアプローチ。こちらも右利きなので中央への経路を封鎖するように寄せる経路が基本でした。
また、アンカーのシミッチやIHの脇坂には健勇のプレスバックと金子が前に出ることでケアしていたので、そのままサイドで追い込めたら宇賀神や岩波が前向きにアタックできるシチュエーションを整えられていました。
また、中央は敦樹が絞ることで旗手から中央へのパスを回収するという守備もよくできていました。18:10の場面はわかりやすい例だったと思います。

川崎の対策
しかし、川崎もそのまま素直に受けてはくれません。飲水タイム前後からシミッチか田中を明確に最終ラインに降ろすことが多くなります。
それにより、最終ラインの幅が確保されることになります。谷口へ追い込んでプレスをかけたい浦和でしたが、横に広がった3枚に対して2トップが物理的に間に合わない場面も徐々に出てくることになりました。

20:30では田中が明確にCB間に入っていますし、その後も29:50、34:00など序盤では2+1で行っていたビルドアップを3+2にして浦和のプレスを回避するようになります。
しかし、その分前線からは人を降ろすことになりますので、浦和としては前から激しく追い込むことはできなくなったものの、そこから決定的な場面を迎える場面はなかったと思います。
勝敗は細部に宿る
自分たちの志向を愚直に表現する真っ向勝負を挑み、保持や非保持の局面において、互角以上の展開を見せていた前半。しかし、トランジションから生まれた一瞬の隙から失点し、試合を不利にしてしまいます。
これまでの試合展開を考えると、かなり痛い失点となりました。始まりはスローインからのロストですが、失うこと自体はあり得ること。問題はその後のトランジションで逆サイドへの展開を許してしまったことです。
川崎のスピードが早かったことなど、相手のレベルが高かったのは事実なので難しい局面ではありますが、せめて同サイドで閉じ込めておかないとこうなってしまうよね、という場面でした。
細かいところですが、敦樹が逆サイドへのコースを消すことや、金子が田中への落としをケアする立ち位置を取れていたら結果は変わっていたかもしれません。
とはいえ、小林悠の決定力、トランジションを意識した一歩目が誰よりも早い山根を見ると、主導権を握られていながらこの一瞬で得点を取ってしまう川崎の強さが出たシーンでした。
2失点目は西川がボールをキャッチしたところからスタート。すぐに敦樹へボールを渡してプレーを始めますが、素早く始めようとしたのはこの2人だけだったように思います。
敦樹がボールを持って前へ前へと運びますが、周囲を見ると反応はあまりありません。正直、まだ準備中といった感じで、一旦ボールを持って落ち着けてやり直す認識だったのかもしれません。
ハーフタイムの指示などはわからないので、素早く始めようとすることを良しとしているなら周囲の反応が不足していますし、そうでないなら西川や敦樹の判断が急ぎすぎたということになります。いずれにしろ、チームが全体で同じ方向を向いていない瞬間でした。
その中で敦樹は川崎の密集したプレス隊から中へ誘導されながら前に運んでいますので、必然的に相手が近くなっていき、苦し紛れの縦パスをカットされます。
さらに、その瞬間の切り替えは浦和が致命的に遅く、川崎の方が単純に早かったです。山中や汰木は五分かそれ以下の状態であるボールに対して、攻⇨守の切り替え、ネガティブ・トランジションへの準備はできていませんし、最後の部分はコミュニケーションも不足しているように見受けられます。
トランジションの遅れによって小林悠がフリーになり、するすると上がってくるダミアンに金子が行くのか岩波が行くのかも曖昧。もちろんスーパーなゴールですが、これほどまでに緩慢なトランジションで遅れを取った挙句、プレッシャーと呼べるものが何もかかっていない状況を王者相手に容認すれば、結果がこうなるのは必然です。
リカルド監督 試合後会見 抜粋
「こういう相手と戦うときには少しの時間でも集中を切らすことはできません。集中を切らした瞬間、少し隙を見せた瞬間に、今日の試合のようになってしまうので、我々としてはそういったところを次の改善点としなければいけません。」
その後は足が止まってやられ放題で、試合として体を成さなくなってしまいました。筆者は今節、ピッチに近い席で見ていましたが、こういった状況の時に声を上げているのは槙野だけで完全に気持ちが切れてしまっていた印象です。
精神論を語るのはあまり好きではありませんが、こうなってしまうと修復は不可能でしょう。リカルドは最後まで声を張り上げ、選手の大幅交代も行いますが、ゲームを軌道に戻すことはできませんでした。
まとめ - 絶望の結果と希望の内容
終わってみれば0-5の大敗で後味の悪い試合となりましたが、冷静に振り返ってみると、前半は今季最高のパフォーマンスと評価しても過言ではない内容だったと思います。
立ち位置で優位を取り、相手が動いた・相手を動かした結果として得られるスペースを利用して前進する。ゴールへの道筋が遠ければ、新しい配置を導入してゴールに近づこうとする。
立ち位置の取り直しをしっかり行うことや、本文では触れませんでしたが、西川を使って後方まで相手を引き込む勇気と継続など、パーフェクトではありませんが、狙いとすることを王者相手に存分に出せていたと思います。
だからこそ、一瞬の隙と称されてしまうような、ディテールの部分での詰め、90分間を通しての強度や切り替えの不足、原則や共通認識をチームで維持することを怠ってしまう瞬間から結果を落としたことは、もったいないの一言に尽きます。
前半の内容を見れば0-5で負ける試合ではありません。ですが、結果を分ける細部を詰められないのであれば、「良い試合」をしても安定して結果を残すことは難しいでしょう。
また、メンタルの部分についてはプロの舞台でやっているプロの選手たちにしかわからない部分もあると思うので何とも言えませんが、近年はこういった展開になってしまう傾向にあるので、サポーター側からしたら改善してほしいのが本音になります。
いわゆるメンタルが強いと思われている選手たちがいた時代を知っているからこその不満も出てきますが、過去を事実より美化するのは人の性質なので注意したいと思います。
リカルド体制への期待は持てるか
さて、開幕連戦がここで終わりました。ルヴァン杯が1週間後にありますが、Jリーグは2週間の休みに入ります。やっとトレーニング期間を取ることができ、ここまで出た課題や更なる改良へ時間を投じることができます。
大敗を喫した今節を経ても、個人的にはリカルド体制の内容については期待を持っています。結果がついてきているとは言い難いですが、上積みは確実にされていますし、やりたいこと、相手の出方を見て利用するサッカーを発揮する場面も多くあります。
目指している内容が再現性高く、かつ安定的に発揮できるようになれば、自分たちが主導権を握りながら相手に合わせることができるので結果も安定してくると考えています。
しかし、結果は常に相手との比較で決まる相対的なもの。いくら自分たちの絶対的な積み上げがあっても、結局は相対的に相手を上回らなければ勝てません。
また、リカルドは1年目であることや日程面や怪我人で不利があったことなど、現状から差し引いて考えても良い要素があっても、トップチームが3年計画という期間を打ち出している以上、その期間から逆算した進捗を求められるのもまた当然の原理でしょう。
流れの中のゴールなど、何かひとつきっかけがあればと思わなくもないのですが、早く結果が出ることである種の安心感を持って上積みをしていける状況になれば良いなと思います。
今回もレビューを読んで頂いたこと、感想や意見をシェアして頂いたこと感謝です。ありがとうございます。
大敗という結果と、前半の手応え。レビューを読んでの感想や意見はぜひ下記Twitterの引用ツイートでシェアしてください!
📝【戦術分析レビュー】
— KM | 浦和戦術分析 (@maybe_km) March 23, 2021
勝敗は細部に宿る - 2021 J1 第6節 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ
◆今季最高の40分
◆リカルドのオプション追加
◆試合を壊す細部の差
◆絶望の結果、希望の内容
🧑🏼🎓川崎戦RV書きました。感想・意見ぜひ引用ツイートで!#urawareds #frontale https://t.co/uOaA0TOSLk
音声配信
アプリ、stand.fmにて浦和レッズを深く応援するための音声配信を行っています。レビューの音声版や、レビューに収まらなかったこと、普段のニュースに対する解説やライブ配信も行っているので、ぜひフォローしてください!
おすすめコラム
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
