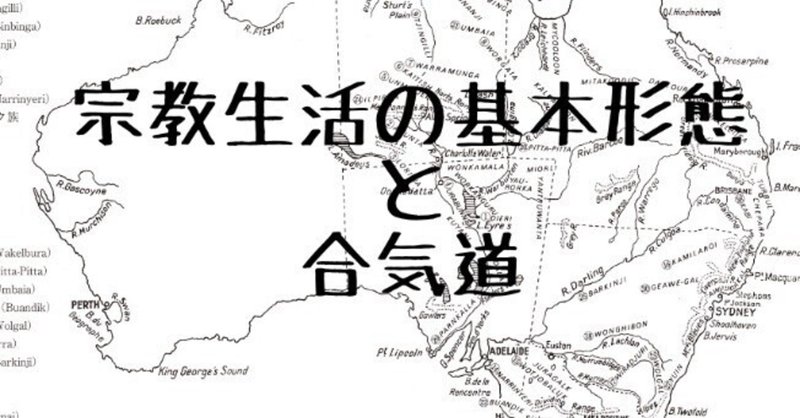
武道と宗教の「同じ」と「違い」【宗教生活の基本形態と合気道⑦】
こうした本を読んでわかったことは、合気道の中にも人類普遍の型が入ってるってこと。
宗教も武道も人間社会という集団生活の中で成り立ったものであり、宗教は思想から武道は肉体から同じものを追求しているとも言える。
儀礼
宗教生活の基本形態では「悲しみの儀礼」というのが紹介されていた。
人が死んだ時にアボリジニーは大げさなまでに悲しみを表現し、時には殴り合いや自傷行為にまで発展する。
それは悲しまないと死んだ者に呪い殺されると言われているからだ。

とはいえこれはそんなにおかしな話じゃなくて、小さな集団では特に仲間を失った時に悲しんでないやつがいると話がややこしくなるから形式的にでもやっておいた方がいい。
信じようが信じまいが集団としてはやったほうが得なのだが「神の教え」と「生で食ったら腹を壊すという科学的な証明」のどちらが楽かというと神様に任せたほうが楽なのだ。
概念
デュルケームは宗教というのは正義が行われる完全な社会を目指すものであるとしていて、それはある意味では「フェイクから真実を生み出そうとする情熱」だ。

真面目な時のラーメンハゲ
この世に完全な正義はないが、それを目指そうとする矛盾。
そのためには神とか、解脱とか、何かしらの道しるべが必要だったのだ。
現代でも陰謀論者やらフラットアーサーやら、スゴイ角度から加速する人類がいるように信じるパワーそのものの方が合理性なんかより遥かに強い。
稽古
武道では練習のことを稽古と呼ぶけど、これは古事記の「稽古今照」から来てて、意味は「古(いにしえ)を考えて今を照らす」ということ。

過去から学んで今を照らした結果、インフルエンサーがオンラインサロンでお布施をもらったりしているわけで、実のところ形は色々と変わってはいるけれど型そのものは変わっていない。
むしろ応用という意味では見事な方向に変わっているとも言える。
武道
合気道も宗教とそこまでかけ離れてはいない。
ひとつ違う部分があるとするなら、それは肉体か思想かと言ったところにあると思う。

合気道は肉体から人とのぶつかり方、そしてそれをなくす方法を学べる。
宗教は社会に人を適合させるためにあり、合気道は個人を社会と適合させることができる可能性があるというわけだ。
宗教が良い思想を説いたとしても現実社会に適合できなければうまくいかないし、武道でどんなに個人が強くなっても強硬な考えのままでは意味がない。
宗教と武道というのはどちらも一方だけでは成り立たないし、また最終的には双方の領域に入る分野だとも言える。
宗教と武道も表と裏のように両儀的なのかも知れない。
転換
合気道の「転換」という技法は相手と一体になることで行うことができる。
これは要するにどれだけ他のものを「同じ」にできるか?ということでもあると思う。
デュルケームは後にレヴィ=ストロースの構造主義によって先住民に対する偏見が目を曇らせたと批判を受けることになるけれど、彼を含めた先人の研究成果がなければ構造主義も生まれなかった。
反対に先住民も現代人も同じだとする視点さえあればもっとはやく「構造主義」は産まれていたかも知れない。
そんなわけで「同じ」を見つける視点は忘れないでおきたいし、それこそが合気道なのである。
おわり!
関連記事
マルセル・モースの『贈与論』と考える合気道と贈与
レヴィ=ストロースの『野生の思考』から考える合気道と人類の構造
エミール・デュルケームの『宗教生活の基本形態』から考える合気道と宗教
マツリの合気道はワシが育てたって言いたくない?
