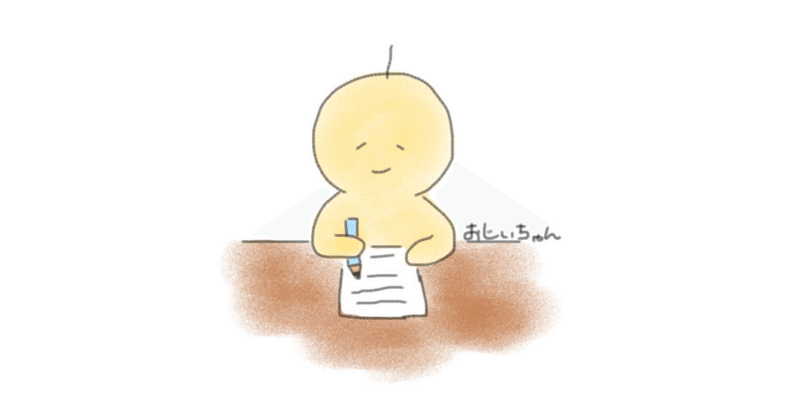
10 「構え」のチカラ
テレビを付ければ五輪のニュースが花盛りである。開催に反対の論調であった局からでさえメダル獲得のニュースに沸く声が聞こえて来る。一方でアスリートたちの力闘にエネルギーを貰っている人も多いに違いない。
卓球混合ダブルスでの水谷・伊藤ペアの決勝では、第1、第2ゲームを落としたあとの水谷から伊藤への耳打ちが印象的だった。具体的な戦術についての話であったのだろう。その後の3ゲームを連取し、最終ゲームで相手を圧倒して勝利を得た。
ゲームは相手あっての勝ち負けであるが、突き詰めれば一人自らの在り方を熟成させる戦いでもある。第2ゲーム後の水谷・伊藤の短いミーティングで、2人の在り方に変貌があった事を感じる。在り方とは、逐次変貌する世界へ適応しゆく「構え」のことである。仏教では「随縁真如の智」と説かれる。一見静かに座って瞑想に耽っているイメージが強い仏教であるが、実は、説いている内容といえば変貌する世界へ立ち向かうための構えと実践法であり、ある宗教家は仏道修行を剣豪の修行に例えている。つまりそれは武道やスポーツにも大いに通じるものなのである。
微妙な構えはすべての戦いに影響する。構えは自ら一瞬で変えられるものであり、環境に影響されて知らず知らず崩されてしまうものでもある。いかに自らの構えを成熟させ崩れざるものとするか。それが生の要諦であり、もちろんスポーツ・武道でも同じことだ。
こんな状況の中、奄美大島では26日、世界自然遺産登録決定のニュースに沸いた。2017年に政府が登録を推薦したがユネスコは18年、登録延期を勧告。19年に再推薦ののち、20年の決定予定であったはずがコロナ禍により委員会の開催が見送られ、今年度の決定となった。
知人のホテル経営者は観光客の増加を見込んでレンタカー事業を開始していたが、コロナ禍と登録延期、オリンピックの無観客開催のトリプルパンチで本業のホテル事業まで苦しい日々が続いていたようだ。島の振興を志す若者は、島外からの営利業者の流入で島の文化が脅かされるのではないかと恐々とした心境をSNSに綴り、ワンキャ(私たち)の島はワンキャで作って行こう、と呼びかけて島の多くの若者たちから賛同を得ている。
「日本の国論は外圧によって沸騰する性質を持っている」と語ったのは司馬遼太郎である。「日本の現代の開化は外発的である」と語ったのは夏目漱石である。上滑りな外発的開花を脱して内発的開花を、と漱石は語った。少なくとも奄美大島のいまの状況は漱石が『現代日本の開化』と題して和歌山県で講演をおこなった110年前とあまり変わらない。振り子の揺れのように、適切なバランスを得ていつかは静かなリズムを刻み始めるのだろう。
不要な対立軸に立脚した構えは脆く弱い。しっかりと現実をみつめながら、目的にそって全ての縁を力へと変えていく在り方を不動の構えとして熟成させて行くこと。混迷する社会で問われているものはその一点である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
