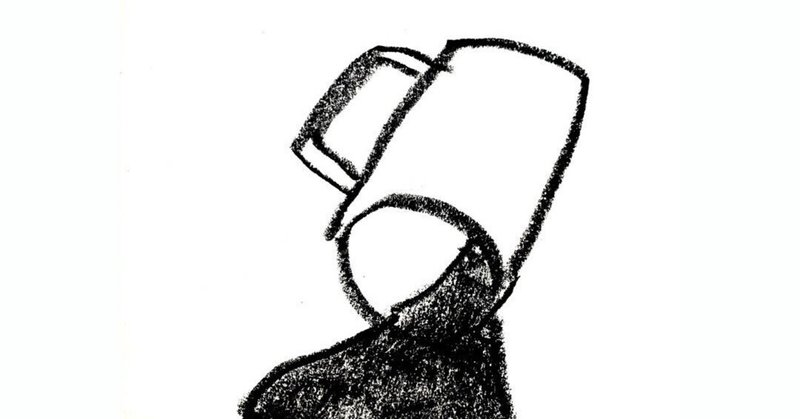
12 コーヒーの話から
先日、大切に使っていたコーヒーカラフェが割れてしまったので、この際、気分を変えてコーヒーメーカーでも買ってみようかと思い立った。島内のヤマダ電機でメリタの手頃なものを購入し、さっそく馴染みの焙煎屋で煎りたての豆を買って来て淹れてみた。出来上がったコーヒーはコーヒーには違いなく、豆だって上等の豆なのだが、やはりこれまでのハンドドリップとは何かが違う。物足りない。
いちど、ダスキンの交換スタッフがわが家に来た際、玄関を開けるなり「あら、コーヒーの香り!」と言ったことがある。ハンドドリップでコーヒーを淹れると、湯を注いだ瞬間から香りが立ちのぼって部屋に満ちる。泡立ちで豆の鮮度を確認し、豆の状態に応じて湯の温度や注ぐ速度を変える。コーヒーメーカーでは立ちのぼる香りも無く、微調整の楽しみも無かった。私は知らず知らずコーヒーを淹れる過程をも味わいとして楽しんでいたのだった。それは登山のようなもので、登頂だけが目的ならヘリコプターで山頂まで行けば良い。しかしそれでは登山の楽しみは無い。
私は現在、NPO法人奄美食育食文化プロジェクトという法人で事務局業務を担っている。そのミッションは要するにスローフードの達成である。スローフードとは何かについて、スローフード協会の副会長・シルヴィオ・バルベーロは次のように語っている。
「すべては関係性の問題なんだ。人と人、人と自然のね。他者といかにコミュニケーションをとっていくのか。大地からの恵みをどうやって口まで運ぶのか。そういう根源的な関係性の問題の根底に食というものがあるんだ。だからそれは、とてつもなく重要な文化なんだ。そこにぼくらは〝スロー〟という言葉をあてがうんだ」【島村 菜津. スローフードな人生! -イタリアの食卓から始まる- (Japanese Edition) (Kindle の位置No.338-340). 新潮社. Kindle 版.】
腹を満たせば良いのであれば、そのへんの安い工業製品を口に入れれば済むのだろう。しかし「生」の根本たる「食」の本質は、誰によって、いかにして作られ、いかにして運ばれ、いかにして調理されたかといったコンテキスト〜文脈にこそある。
心理学者のアドラーが、2種類の生き方について語っている。ひとつは「キーネーシス的(動的)な人生」、もうひとつは「エネルゲイア的(現実活動態的)な人生」だ。キーネーシス的とはヘリコプターで山頂までたどり着く生き方、ゴールを目指して突っ走る生き方であり、その途中過程は「達成していない状態」であり、不完全な状態であると言える。エネルゲイア的とはダンスを踊るような人生であり、瞬間瞬間が見せ場でありゴールでもある。たとえ早逝したとしても充実した人生である。
アドラーは、人生はエネルゲイア的であり、はなからゴールなど設定できるものでは無いと言う。一歩進めば環境は変わる。目指していた学校に行けなかったからと言ってそれで人生の失敗が決まるわけではない。環境の変化に応じて「じゃあどうするのか」と反応して行く中にこそ独自の文脈が生まれ、その人だけの人生が出来上がって行く。文脈、過程こそが自分自身であり人生である。
現状を受容し、自分はどうありたいのかを見極め、じゃあどうするのかを考える。状況が変化すればそれもまた受容し、対応する。人生が登山や旅に例えられることには意味があるのだ。旅も登山も人生も「連続する刹那」である。生とは刹那の中にしか存在しない。それがアドラーの出した答えだ。
コーヒーの話から、とんだ大きな話になったもんだと呆れる向きもあるかも知れないが、家族や故郷や友人、吹く風や道端の草木、巡りあうすべてのもの、病気や怪我でさえ自らを支える文脈であり背景であり、それこそが自分自身だ。それら背景にどんな意味を与えるのか、意味を与えるのも、また自分自身である。
ヘリコプターで辿り着いた山頂で見る朝日と、自らの足で登頂して眺める朝日は決して同じではないはずだ。安物のコーヒーメーカーで淹れたコーヒーに感じた物足りなさは、きっとそんな所にある。学生時代、私に仏教を教えてくれた友人が言った。「結局は生き様の問題だよ」と。コーヒーを飲みながら、そんな事を思い出した。
*今週の参考図書
・『スローフードな人生! -イタリアの食卓から始まる-』島村 菜津(著) 2010年/新潮社
・『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』岸見 一郎 (著), 古賀 史健 (著) 2013年/ダイヤモンド社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
