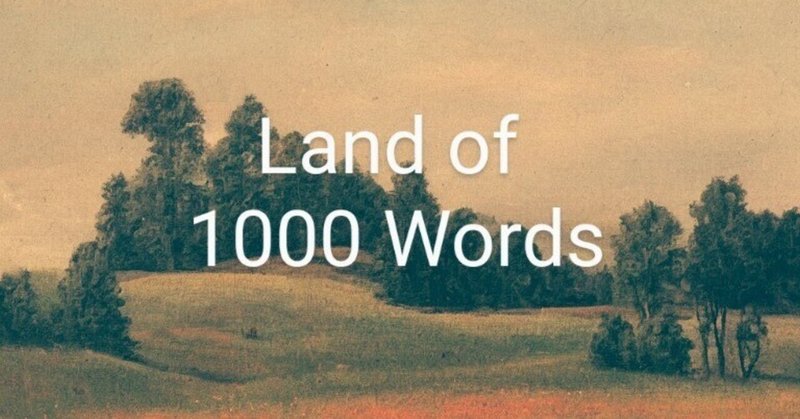
【1000字】ムーン・ガール
ルルンはそれまで月面コロニーで暮らしていたという。親の離婚で、母方の実家があるこの町に越してきたらしい。
町には月育ちの子なんていなかったので、転校生の彼女の名はたちまち知れ渡った。重力の違いのために背丈が大人並に高く、それと引き換えに筋力はほとんどない。肌は日光を知らない白色。隣席の僕は彼女のかわりに重い荷物を運ぶ役目をしばしば任された。それは少し恥ずかしく、どことなく誇らしい仕事でもあった。
夕方、月が東に昇ると、ルルンは指をさして「あそこはこれから朝になるよ」と教えてくれた。彼女が月を見上げるたび、僕は不思議な気持ちになった。たとえば、ブラジルやエジプトといった国々をここから眺めるのは不可能だけど、その何倍も遠い月は眺められるという位置関係が、僕にとっては世界の神秘のひとつだった。
ある日の昼休み、ルルンは倒れた。
みんなで鬼ごっこをしているときだった。彼女は極端に体力がなく、遊びに夢中になるとすぐ酸欠になってしまう。保健室で目を覚ましたとき、「体が重い」と彼女は呻いた。地球はルルンにとって重すぎる惑星のようだった。
月面病と診断され、彼女は入院生活を余儀なくされた。ほとんどの友達はルルンを忘れていったけれど、僕はなんとなく日々の習慣として放課後にルルンを見舞い続けた。秋になれば、病室の窓からでも絶好の角度で月が眺められ、それが僕たちの沈黙を埋める話題にもなってくれた。
「月に帰りたいって思う?」
「どうかな」彼女は首を傾げる。「わたしね、あっちにいた頃は毎日ずっと地球を眺めていたの。なんて綺麗な星なんだろうって。絶対あそこに行ってやるぞって、ずっと思ってたの。だから、いまのほうが幸せなはずなの」
「病気になっても?」
「病気になっても」
「でも、僕は、月のほうが綺麗だと思うよ」
僕が勇気を振り絞ってそう言うと、ルルンは嬉しそうに微笑んだ。
それから間もなく、ルルンは亡くなった。月面病がそんなに重い病気だったなんて誰も教えてくれなかった。ルルン本人だって知っていたかわからない。棺の中のルルンは冬の月の白銀にも劣らぬほど綺麗で、それが僕にはかすかな救いだった。
あの頃のルルンと同じ背丈になったいまも、僕は月夜に必ずルルンを思い出す。
生きる者にとって、死者は限りなく遠い世界の住人であるはずなのに、月はいつでも目の届く空に輝き、幼い日々の透明な温もりを地上に注ぎ続けてくれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
