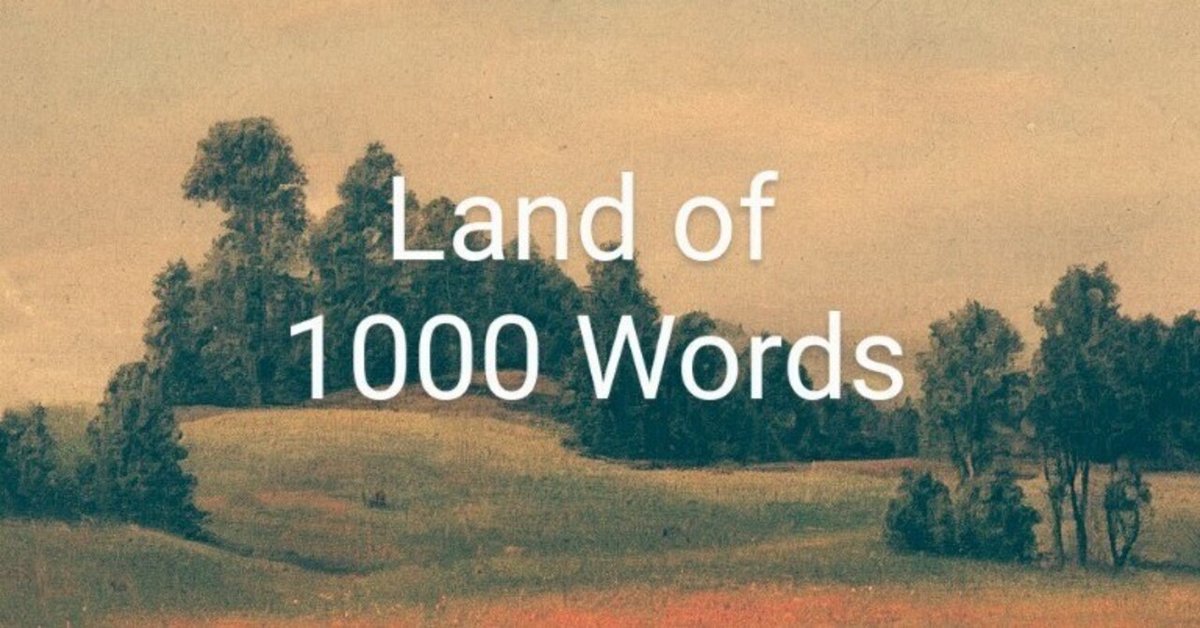
【1000字】同じ虚空
この町には罪人の首を刎ねる習慣が残っていて、しかもそれは見世物として観光客に人気があるという。ガイドに誘われ、私は首切り広場へと出かけた。大変賑わっている。菓子や酒を売るテントが並んでいて、その光景が私に故郷の祭を思い出させた。
「皆、人の死ぬところが見たいのか」
「まぁ、首切りを公に見られるのは世界中でもここだけですから」ガイドはなんともいえない笑みを浮かべた。「見物にはお金がいりますが……」
「わかった、払うよ」私は苦笑して頷いた。
今回首を刎ねられるのは女だという。罪人が女であると観客も湧くらしい。そういうものなのか、と思って眺めていると、丸太組みの壇上に手枷をはめられた当人が現れた。髪の長い、まだ少女と呼ぶべき娘だった。
湧くどころではない。私はのこのこ見物にやってきたことを後悔した。私には、あの少女と同じ年ごろの娘がいるのだ。
太鼓と笛の演奏が止んだかと思うと、執行人の振りかざした大斧が、少女の首を音高く断った。少女の生首は弾けるようにして虚空へ跳ねた。その表情が涙で歪んでいたのを、私は永遠にも等しい刹那に視認した。カメラのシャッター音があちこちで響いていた。
その夜、私は酒を奢られたが、とても飲める気分ではなかった。なにを見てもあの苦悶の顔がフラッシュバックして参った。
「そういえば、あの子の罪はなんだったんだ?」
「窃盗と売春、それから親殺しです」ガイドは答えた。
「親殺し?」
「虐待されていたそうです。窃盗も売春も親にやらされていたという話です。家族を養っていたのでしょうね」
私は絶句した。
「心が痛まないのか?」
「今日のショーの収益の半分は、あの女の家族に充てられます。相当な金額になるはずです」ガイドは微笑んで私を見る。「彼女の弟たちはまだ幼いそうです。学校へ通えるようになるでしょうね」
大きな天秤に載せられている気がして、私は足許がぐらつくのを感じた。首刎ねなどという習慣が残るこの町で、なぜ未だに犯罪が絶えないのか、その理由の一端を垣間見たように思った。
帰国の日、私は空港で娘へ土産を買うことにした。人形を手にとり、娘がそんなもので喜ぶ歳ではないと思い出すのに数秒かかった。その気になれば、親も殺せる年齢だった。
飛行機が地上を離れていく。
その間、私は窓に映る雪の軌跡をずっと眺めていた。
娘の顔を思い出せない。
私はまだ、あの生首と同じ虚空にいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
