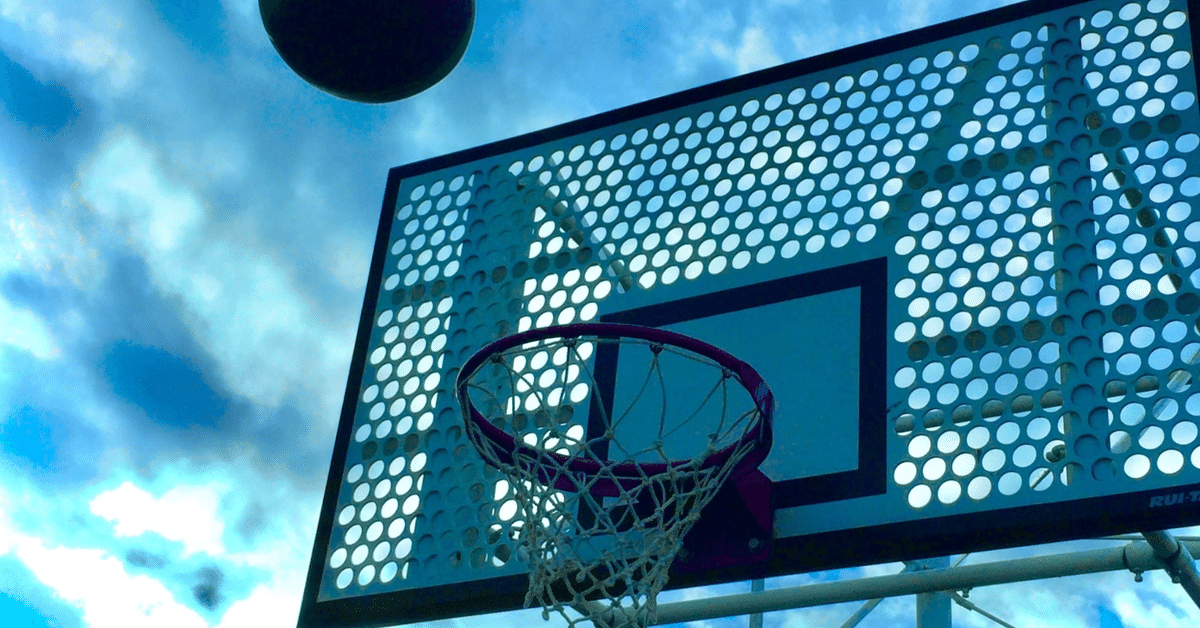
そうだ!大学院にいこう![リカレント教育実践編その6]
🔲末は博士か大臣か
こんにちは、まっつんです。
某教授の教えによると統計学的には同年代の子供の+2標準偏差(上位2.5%)以上がIQ130以上と言われるらしいので、単純計算で40人に一人の割合で出現するそうです。つまり、クラスに1名の割合でIQ130の子供が存在することになる。
子供の頃に神童と言われたとか、成績が抜群だったと言っても、ひとクラスに1名いる確率であれば、私たちに日常においてかなりの高確率で、天才くんと遭遇していることになりますね。最近は、そんな高IQの子供たちは、ギフテッドと言われ注目を浴びています。
そして、昔はそんな高IQの子供に対して、周りの大人は言ったものです。
「末は博士か大臣か」と・・・。
この流れで言えば、日本は博士号取得者や大臣経験者が大勢存在することになります。しかし、多くの隣の天才くんたちは、学校教育の賜物なのか、成長とともに凡人と化したのか、少なくとも大学院の博士課程後期には人がいないのが現実です。
今回は、そんな中で、博士号取得のために博士後期課程に進んだらどうなるのかを書いてみたいと思います。いつもの通り、まっつんの周辺での事例から引用しているので、全ての博士課程後期に該当する内容ではありませんので、ご注意ください。
🔲日本の博士はなぜ少ない
D論必勝講座が人気のYouTuber Dr.クラゲさんではありませんが、博士課程後期に属する院生は、なんとかD論を通して、博士号を取得したい。と切に願っているわけです。しかし、日本は博士が少ないと言われています。
特に文系は、理系のように博士号が、研究者としてのパスポートのようなものといった扱いとは大きく異なり、一昔前は、研究を一生懸命やった大学教授が退官前にご褒美として戴ける称号(と、まっつんは主査から説明を受けました)と、例えるなら針の穴に駱駝を通すよりも難しいとされてきました。(本当に博士号は、神の国なのかもしれない)
世界比較で見ても人口100万人当たりの博士号取得数は低いことが分かります。
世界各国で博士号取得者が増加する中において、日本だけが日本は漸減傾向となっています。

まっつんの所属したゼミでも最終的に同期で博士号を取得できたのは、まっつん一人でした。本来は、課程博士は3年でのプログラムにおいて研究者として独り立ちできた証として博士号を取得できるはずなのです。しかし、日本の博士号は、特別な称号のように扱われている場合が多く、「世界的発見をした論文でないと博士号を授与させない」と言われている教授が実際にいたりもします(実際にそう言われました)。たった数年研究しただけの学生に世界的発見を求めること自体が、そもそも無理ゲーだと思うのですけど。課程博士と論文博士を取り違えているのは?と思ってみたりもします。
因みに、まっつんの所属していたゼミの同期たちはどうなったのかというと、①研究が進まず自主退学、②研究は進んでいたのに時間切れで博士論文を書くことなく自主退学、③博士論文を書いて提出したにも関わらず、審査を受けられずに自主退学(これはヒドイ)をしていました。
このように文系では、折角、博士課程後期に進学しても、思うように主査の指導を受けられずに、自主退学となる人もいるのです。主査、副査の指導方法も、丁寧に指導して博論を仕上げていくタイプと、全く指導をせずに学生側がぐいぐい行かないと博論を見てくれないタイプと様々な方がいらっしゃるようです。確かに、博士は自身で研究を進めていく能力が求められるため、誰かに手伝ってもらうとか、手取り足取り教えてくれるということはないのです。当然ですけど、自分で書き切るしかありません。
🔲博士課程に進学する際の注意事項
たまに博士課程後期に進んだ後に主査をどうやって決めたのですか?と聞いて来られる方がいらっしゃいますが、本来は入学前に自分の研究を指導していただく教授に連絡をし、研究内容などをすり合わせてから、主査をお受けいただき、博士課程後期に進学するのが良いと思います。
万一、入学後に自分の研究を指導できる主査が存在しなかった場合どうするのだろうかと人事ながら心配になってしまいます。
大抵の場合は、修士号を取得した大学院の博士後期課程に進むことになるので、研究内容を変えない限り、主査の心配は要りません。(多分・・・)
まっつんは、実は修士と博士では大学院が異なります。修士の研究をより発展させて博士号へと昇華させると考えるならば、修士と博士で異なる大学院へ進学することはあまり良いとは思いません。
まっつんの場合、修士課程の2年間、裏番組として某大学院の博士後期課程のゼミに、教授の好意で、参加させていただいてました。そのため、博士課程後期の2年目でキャンディデイトの資格をゲットできたのです。(しかし、その後、教授が定年で退官されゼミは解散、引き取られた新しいゼミでしばらく研究を続けましたが、分野の違いから結局、修士課程でお世話になった大学院に逆戻りして博士論文を仕上げました。今思えば、それも随分と失礼な話だと思います。)
自ら研究を進めていくという点において、修士課程の学生としての過ごし方と、博士課程の学生としての過ごし方には大きな違いがあるのです。
そして、主査をお願いする教授が博士課程の途中で定年退職するとか大学を変わられるとかは、自分が博士号を取得するまでの予定期間に計算しておく必要があります。
🔲博士後期は実は、あっという間に過ぎ去ってしまう
大学院への入学するには、普通、試験があります。まっつんは、研究計画書の提出と、英語の試験、研究のプレゼンを兼ねた面接があったと記憶しています。主査をお願いする教授と研究の擦り合わせができていれば、ここで落ちることは無いと思いますが、大学によって微妙に異なると思いますので、この点も自分の望む大学事務局へ要確認ですね。
博士課程後期は、ゼミ以外は授業を取らなくてもよい大学院もあれば、修士の時ほどではなくても良いが一定の単位の取得を求められる大学院もあります。そして、他大学での単位をスライドして認めてくれる大学もあります。忙しい社会人にはその分、研究に時間を割り当てられるので助かります。気になる方は大学の事務局に一度確認してみてください。
いよいよ博士課程後期に入学が決まると、理系のように定期的な実験などがない文系博士の卵たちは、主査と擦り合わせをしたテーマを地道に研究をして論文として完成させていきます。
博士論文は、修士の時のようにいきなり研究結果を書くとは違い、学会などに発表した複数の論文を核として、まとめることで博士論文は完成します。ですから、ジャーナルや学会誌に論文を掲載する必要があるのです。(しかも、由緒あるジャーナルや学会でないとだめとか言われる)
そしてその論文も、査読を受けて原著論文として掲載される必要があります。
まっつんの大学院では、単位取得の条件に国際学会での発表という一文が入っていたので、嫌でも英文での学会発表と論文作成がセットとなっていました。(英語でのオリジナルペーパー1本、国内の学会での原著論文1本だったと思います)
仮に博士課程後期を、所定の3年間でクリアするつもりなら、1年目と2年目の夏くらいまでには、複数の論文を査読つき原著論文として学会誌などに掲載される必要があります。3年目は、中間審査対策や博士論文の作成で潰れてしまうからです。(まっつんは実は修士の時に数本査読つき論文の本数を稼いでいました)
某先輩から聞いた話だと某地方国立大学では、論文1本(しかも学内の紀要に掲載されれば良い)というところもあるみたいです。一部の私立大学でも紀要に掲載されれば良いというところもあると聞きましたので、これも条件を大学事務局によく確認しておく必要があると思います。
紀要とは
大学(短期大学を除く)の場合、各学部・研究科ごとに紀要を発行することがあり、毎年数多くの紀要が発行されている。形式的には、各組織が直接の発行元とならず、その組織に所属する者を会員とする学会が発行するという形をとることもある。紀要の学術的水準に関しては、その審査が簡素な査読水準に留まる場合や、査読を行わない場合などさまざまであり、手続き上、掲載される文章の学術水準はまちまちである。そのため、紀要での研究発表を研究上の業績として認めない組織や紀要を発行しない組織もある。
🔲まとめ
日本は国際比較しても博士号取得者は少ない。
学士の卒業証書や、修士の学位記のように、博士課程後期に入学したからと言って必ずしも博士号がもらえる訳ではない。
自身の研究の主査をお願いする教授とは、入学前に研究の擦り合わせを行う方がベターである。そして、学士や修士と違って、研究はあくまで自身で行うのであって、主査が何かを教えてくれる場所ではない。
修士と博士を別の大学院に進学すると研究の継続が難しいリスクがある。
主査が研究の途中で定年退職するリスクは計算に入れておいた方がよい。
博士号の取得には3年間はあっという間に過ぎ去ってしまう。
博士論文は、査読を通った複数の論文を統合して完成させることになる。
各大学院で微妙にルールが異なる場合があるので、必ず確認は必要。
以上、今回は「そうだ!大学院にいこう![リカレント教育実践編その6]「末は博士か大臣か」を書いてみました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
次回もよろしくお願いします。
✅ ↓ じんじーずに興味のある方はこちらもどうぞ!
https://mangahack.com/comics/3165
🟩神童も成長すればただの人!まっつんブログ!
いただいたサポートは選り良い記事を提供できるように有益に使わせていただきます。
