
「アトムより」に関する幾つかの考察、そして人生最高の日についての話
※この記事は、過去のブログの中でアクセスの多かったものを加筆修正したものです。ネタバレあります。
「人生最高の一日なんて/とっくの昔に/終わってしまった/そんな気がする/どうでもいいけど」
(GREAT3『ナツマチ』)
20歳の頃にこの曲を聴いて以来、「私の人生最高の一日ってどの日なんだろう」とたびたび考えるようになった。
間違いなく、結婚式を挙げた日ではない。結婚は、喪失に満ちていた。子どもがいる人にとっては、子どもが生まれた日かもしれないが、私にはよくわからない。おそらく、特別な日ではなく、それは後になってから、もしくは失ってからしか気づけない、普通の一日なんだろうなということだけはわかっていた。
ラーメンズ第12回公演『ATOM』の最後を締めくくるコント、「アトムより」。
ラーメンズのコントは文学性が高いとは言われるが、どちらかといえば優れたエンタテインメント小説のようだと思っていた。SFのようでもあり、ミステリーのようでもある。
が、この「アトムより」だけは、違う印象があった。この作品だけ純文学というか、静かな映画のようだ。登場人物はさして静かでもないのだが、私の第一印象は、圧倒的に心がしんとする作品、だった。正直なところ、よくわからない、とも思った。
『ATOM』は、小林賢太郎の作風が転換期を迎えた公演だと思う。
それまでの彼の作るコントは、ワンテーマ式のものが主だった。「もしもこんな世界があったらどうだろう」という、SF的なひとつのひらめきが、ひとつのコントを作る。その傾向は第8回公演『椿』で顕著だ。「時間電話」「斜めの日」「高橋」など、「もしも糸電話が過去と未来に繋がっていたら」「もしも地面が斜めになる日があったら」「もしもこの世のほとんどの人が高橋姓だったら」という、時にばかばかしい、ひとつのひらめき、新しい発想から生まれた「非日常の中の日常」(高橋幸宏さんのラーメンズ評より)を描いている。
『ATOM』以降、ラーメンズのコントには、複数のテーマを盛り込んだ作品が徐々に増える。基本はひとつの「こんな世界があったらどうだろう」というひらめきありきの舞台設定なのだが、そこに友情や恋愛、師弟愛、親子愛、夢や挫折など、別の普遍的なテーマが絡み合うことで、作品は深みを増し、見る者にわかりやすく共感と感動を与える。すでに『ATOM』に収録されている「採集」では、人間の剥製を作るという奇抜な発想をベースにして、都会と田舎で道を分けてしまった古い友情や、かつてのマドンナとの悲恋を連想させる設定が絡む。表題作「アトム」では、未来を生きるために30年間眠って息子と同い年になった父親、というSF的設定の中にも、生き方の違う父と息子の衝突というテーマが流れている。(これらはラーメンズが一時的に演劇的になりすぎたということでもあり、後の作風はもっと多様になってゆく。「バニー部」のようなおバカコントも逆に増えていく。これはよいことだったと思う。いっぽう、再びそれを盛り込みすぎているのがKKP後期)
が、友情や親子愛のテーマは、ラーメンズのコントの主題かというと、おそらく違う。あくまでも「こういうシチュエーションの世界があったらどう?」という優れた発想、舞台設定、ひらめき、トリックの上にメッセージをのせることで、観る者にカタルシスを与える効果としての採用だろう。歌詞ならば、「2番のBメロになって、ちょっと本質ついた、いいこと言っておこう」みたいなことだ。
その前フリは第9回公演『鯨』の最後のコント、「器用で不器用な男と不器用で器用な男の話」にも見え隠れしている。ラーメンズの中でも最も人気のあるコントのひとつだ。小林賢太郎はあるインタビューでこのコントについて、「最後に感動ものを持ってきたらどうなるかなと思ってやってみた」といったような、確信犯的発言をしている。おそらくこの感動作も、彼の中ではお得意の「会話が噛み合わないふたり」コントのいちバリエーションであり、そこに白い紙の舞う美しいイメージを重ね、ラーメンズの二人にぴったりの観客が喜ぶ友情エピソードをのっけて大成功しているのだが、では小林賢太郎がコントで挫折と友情について最も表現したいのかというと、やはりそれはコントの一部であって主題ではないだろう。彼がコントを作る時、言葉より先にイメージを「絵」にしておく、というエピソードも、そのことを象徴しているかもしれない。
発想が第一。演劇的要素、メッセージはそこに深みを持たせるための付随的なもの。
ほとんどのコントはそう言えるのだが、私には「アトムより」だけが、メッセージと発想が逆転した最初で最後の珍しい作品だと思っている。
登場人物のノスと富樫くんは、友だち同士という設定にはなっているが、現実世界にはありえないほど仲がいい。よく晴れた日、グラウンドの見える部屋。一本の雲の線。「ああ、アトムだ」と見上げるその笑顔。この世界の中では、ノスがバッテリーで動いていることも、アトムが窓の外を飛んでいることも、背景に過ぎない。私はこのコントを見るたびに、「人生最高の一日って、こんな日なんだろうな」と思うようになった。このコントが一番伝えたかったのは、このメッセージなんじゃないだろうか。
「バッテリー、あったかなー」
この最後の言葉は、ノスが実はロボットであった、いうオチをつけるためのものだ。
この言葉と、富樫くんの笑顔を最初に見た時、私はノスがふたたび動くことはないのだと悟った。バッテリーなど、そもそもない。もしくは、ノスはバッテリーでは動かない。換えたところで、ふたたび動くようなものではないのだと。それは、このコント全体に流れる「かけがえのなさ」をどうしても強く感じてしまうからだ。人生最高の一日も、他愛のない話ができる相手も、バッテリーを取り替えて再生できるようなものではないのだ。富樫くんは最初からそれを知っていたのかもしれない。だからこそ彼らは、日常の中の一瞬を切り取るためにカメラを持って出かけ、動くことのないノスにも戸惑うことなく、優しく笑う。何もかもが、そういうものなのだから。そんな瞬間を切り取ったこのコントは、一枚の写真のように美しい。
(2011年11月)
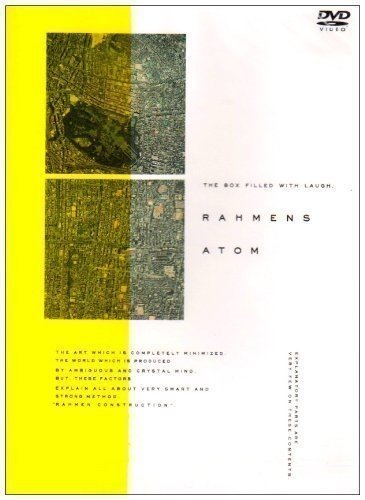
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
