熟練を見せつけるユーフォリックなダンス・ミュージック The Chemical Brothers『For That Beautiful Feeling』
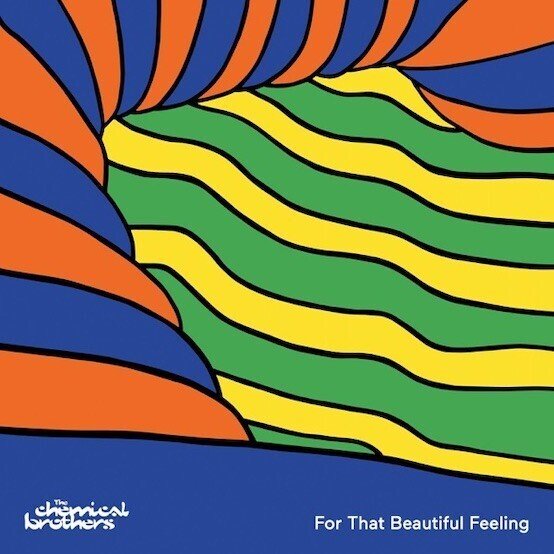
イギリスのダンス・ミュージック・デュオ、ケミカル・ブラザーズは良質なダンス・ミュージックを作りつづけてきた。テクノ、ハウス、ロック、ヒップホップなどさまざまな要素が混在したトラック群は多くのリスナーに愛され、いまもなお聴かれている。
マンチェスターのアンダーグラウンドなクラブ・シーンから出発した彼らの旅を振りかえると、興味深い点がたくさんあることに気づく。ビッグビートというジャンルをメインストリームに押しあげた存在として注目されていた初期の頃は、時代と共に歩む側面が色濃かった。しかし、その側面は作品を重ねるごとに薄れ、代わりにケミカル・サウンドとしか言いようがない独自性が前面に表れはじめた。リズミカルでねちっこいベース・ラインが印象的なブレイクビーツ、ユーフォリックかつサイケなシンセ・サウンドなど、彼らの手法は一貫している。
もちろん、若手のアーティストをゲストで迎えたり、モダンなプロダクションや音色を取りいれたりするなど、同時代性が皆無なわけではない。それでも、基本的に彼らは若い頃に聴いた音楽が軸のトラックを作ってきた。たとえば、彼らの作品から必ずと言っていいほど聞こえてくるヒップホップの要素は、ア・トライブ・コールド・クエストやデ・ラ・ソウルといった、いわゆるゴールデンエイジ・ヒップホップと呼ばれる世代のものがほとんどだ。細かくハイハットを刻むトラップや凶暴なベースが鳴りひびくUKドリルなど、現在のヒップホップにおいて主流の要素は見いだせない。
人によっては、こうした特徴が時代遅れに感じるのかもしれない。だが筆者は、時代に流されることなく、自身の嗜好に忠実な者だけが至る熟練を彼らのサウンドから感じとっている。代表曲の“Song To The Siren”(1992)など、よくよく聴いたら無愛想でストイックなビートなのに、メロディアスで人懐っこいポップ・ソングに聞こえてしまうという魔法は、いまも色褪せていない。
その魅力は最新アルバム『For That Beautiful Feeling』でも輝いている。正直、本作のリリースがアナウンスされたとき、それほど興奮しなかった。収録曲の多くは既発かつライヴで頻繁に披露されていたせいで、新鮮に思えなかったからだ。
しかし、蓋を開けてみると、さすがという他なかった。TB-303風のアシッディーなベースが暴れまわる“No Reason”、トランシーな音像と十八番のブレイクビーツが交わる“Goodbye”といった曲群は、従来のケミカル・サウンドが大半を占めている。流行には媚びず、彼らだけが知る享楽のスイッチを押していく。言ってしまえばそれだけだ。
それでも、筆者の耳が本作を聴いて喜んだのは、相変わらずケミカル・サウンドが独自性を保ってるからに他ならない。既発曲でもアレンジを変え、シームレスに曲を繋げることでトラックの新たな表情を示す技はさすがだ。このスキルに触れると、剣豪の居合術さながらの流麗さを想起してしまう。
彼らがデビューしてから30年以上の時が流れるなかで、数多くのブームやアーティストが生まれた。ビートやグルーヴは多様化の一途を辿り、ジャンルの境界線を溶かした折衷的サウンドは珍しいものではなくなった。
こういった変化に晒されたら、テクノを軸にさまざまな要素で彩った彼らのダンス・ミュージックから独自性は失われ、過去のアーティスト扱いされてもおかしくない。だが、彼らは過去になるどころか、いまも聴き手を踊らせる一線級のユニットとして存在感を放ちつづけている。
最先端とされる初期衝動たっぷりの音楽を貪るのも悪くはない。筆者も仕事柄、そうすることは多い。とはいえ、円熟が際立つ音楽に触れる時間は、初期衝動を浴びたときとは異なる滋味なおもしろさがある。『For That Beautiful Feeling』は、そんな音楽の奥深さを伝える快作だ。
サポートよろしくお願いいたします。
