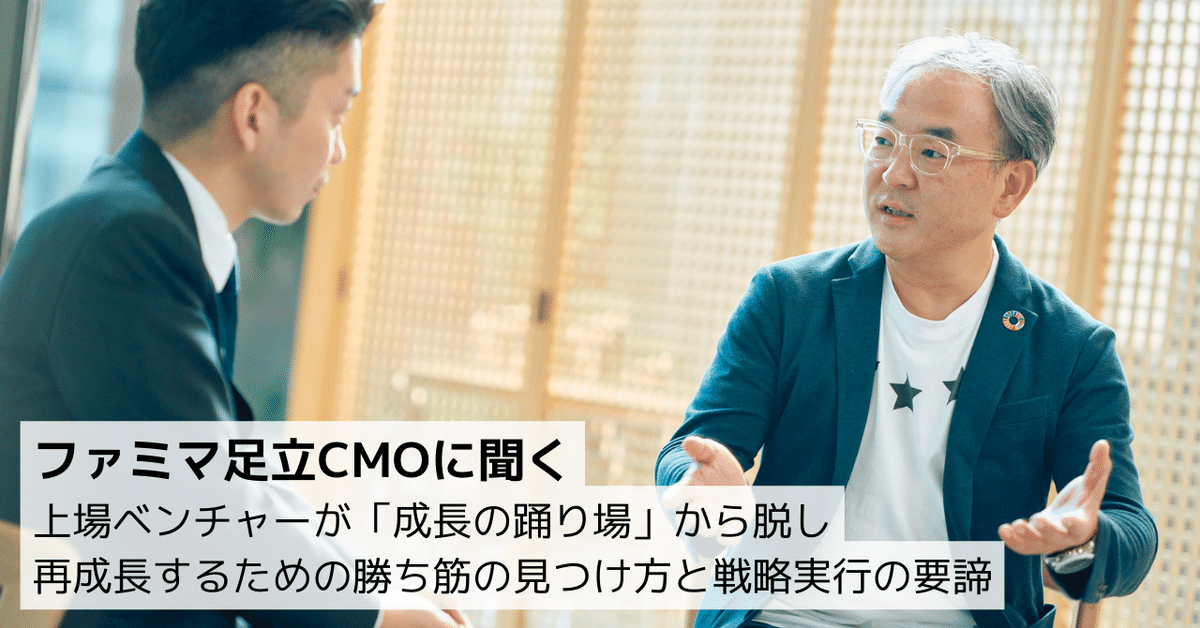
【ファミマ足立CMOに聞く】上場ベンチャーが「成長の踊り場」から脱し、再成長するための勝ち筋の見つけ方と戦略実行の要諦
多くの上場ベンチャーが直面する「成長の踊り場」。
上場前と比べると、格段に増えるステークホルダーの期待に応えるためにも、有効な打ち手、新機軸を見つけ、非連続な成長を実現したいと考えている上場ベンチャーの経営陣は多いのではないだろうか。
今回の対談では、2020年12月より、グロース・キャピタル株式会社のグロースパートナーを務めるファミリーマートCMO 足立光氏とグロース・キャピタル代表の嶺井政人が、成長の踊り場を迎えた上場ベンチャーがさらなる飛躍を実現するために必要な着眼点、さらには勝ち筋の見極め方、戦略実行の際の留意点を語り合った。
■経営陣は「いの一番」に猛省せよ
嶺井:本日は、ファミリーマートCMOであり、当社のグロースパートナーでもある足立さんと一緒に、多くの上場ベンチャーが課題として向き合っている「踊り場からの再成長」について考えていきたいと思います。足立さん、よろしくお願いします。
足立:よろしくお願いします。
嶺井:これまでのキャリアのなかで、幾度となく「踊り場からの再成長」を実現されてきた足立さんに最初にお聞きしたいのは、「再成長を阻害する要因」についてです。そのあたりについてどのようにお考えでしょうか。

足立:さまざまな要因があるとは思いますが、一番の原因は経営者および経営陣にあります。「会社のポテンシャル=経営陣のポテンシャル」ですから、現在、踊り場にあって勝ち筋を見出せていないのであれば、その責任は経営陣にあると考えるべきです。環境のせいでもなんでもなく、自分たちの限界に思い至らなければ何もはじまりません。
嶺井:市場の伸びの鈍化、経済の停滞といった環境のせいにするのではなく、自分たちに責任があることを、まずは認識せよということですね。経営陣には耳の痛い話ではありますが、「再成長に向けて有効な施策を打ち込めないのは自分たちに原因がある」と認識したあとは、どういったことを行うべきでしょうか。
足立:自分たちの限界が会社の限界だと猛省したあとにやるべきことは、今後の成長に必要な人材を外部から引っ張ってきて、経営に参画してもらうことです。
嶺井:足立さんご自身も、日本マクドナルドのCMO、ナイアンティックのシニアディレクター、ファミリーマートのCMO等々、外部からトップに近いポジションで参画されています。踊り場にある上場ベンチャーは、どういう人材を外部から招聘するとよいでしょうか。
足立:ポイントは3つあります。
1つ目は、自分たちが伸びたい方向、分野で「複数回」実績を残している人を選ぶこと。
たとえば、BtoB分野のSaaSが新規市場を開拓しようと考えた場合、新たに進出する分野で実績を残している方が必要になりますし、これから海外展開を視野に入れているのであれば、海外で市場を広げた実績のある方を招聘するのがいいでしょう。あるいは、新規事業の原資を生むためにも既存のビジネスを立て直す必要があるのであれば、日常的にベンチマークしているような企業で実績をあげている方を選ぶことになります。これは一見当たり前のように思われるかもしれませんが、実は目に見える実績を残されていないにも関わらず社外取締役などにおられる方が相当数いらっしゃいます。
2つ目は、仲のいい人を呼ばないこと。
経営メンバーの一員として、社長が間違った判断をした時に「それは違います」と忖度なしでモノが言えなければ、いてもいなくても同じですし、存在価値がありません。だからこそ執行側でも社外取締役でも、社長の耳の痛いことも率直に言えるような人を迎え入れるべきです。
3つ目は、ボードメンバーの人数は最小限に留めること。
踊り場にあるということは、何かしら方向転換しなければならない状況に直面していることを意味します。できるだけ早く、効果的な施策を決定して実行する必要があるにもかかわらず、取締役が何十人といては決まるものも決まりません。スピーディに物事を決めて実行していくためには、社長を入れて多くても6〜7人に絞るべきです。
■50人の組織と300人の組織の違い
嶺井:ここまでは、経営層に焦点を絞ってお話をお聞きしましたが、経営陣が猛省して、再成長に必要な知見をもっている方を招聘したあと、どのような組織づくりを行なっていくとよいでしょうか。

足立:ポイントは1つで、「再現性のある組織」をつくれるか否かにすべてがかかっています。
そのためには、50人でやっていた時と、成長して300人規模になった時とで組織の考え方を変えなければなりません。
50人の時は、全員がお互いの顔を認識しているため、阿吽の呼吸、いわば勢いでなんとかなりますが、300人規模になるとそうはいきません。また、人数が増えていくと、経営陣がすべてに目配せすることも難しくなってきます。
では、どんな組織にすべきかといえば、先述したように「再現性のある組織」、つまりは「自分がいなくても回る組織」「仕組みで回る組織」になります。
嶺井:全部自分でできてしまう「スーパーマン」タイプの上場ベンチャーの経営者としては、自分でやったほうがうまくいくと感じながらも、任せる効用のほうが大きいから、ぐっと堪えるべきということですね。
足立:これからもずっと未来永劫、ご自身が判断するのであれば介入しても構いませんが、そうでないなら「自分がいなくても回る」「再現性のある組織」に舵をきるべきです。
また、企業は社会の公器ですから、さまざまなリスクに備えなければなりません。たとえば、明日交通事故で社長が亡くなったらどうするか。そうしたリスクに対して、しっかりと考えていますかという話です。社長がいなくなったら回らなくなるような会社では、社会の公器とは言えません。
もう1つ補足すると、私の経験上、社長や会長の直轄プロジェクトの失敗率は、その他のプロジェクトよりも高い傾向にあります。理由は簡単で、社長や会長は、実は現場から遠いからです。お客様に近い社員のほうが情報量が多く、お客様や現場の状況がアップデートされているのが普通です。経営者自身の3K、すなわち経験、勘、気合で勝負するよりも、現場を信じるほうが勝率は上がる、そう考えるほうがロジカルです。
■「市場の成長」を「自社の成長」だと勘違いしてはいけない
嶺井:ここまで、成長の踊り場にある上場ベンチャーがやるべきことについて、「経営者が猛省する」「必要な人材を外部から引っ張ってくる」「再現性のある組織をつくる」という3つの観点から解説していただきました。
ここからは、「新しい事業の勝ち筋の見つけ方」「再成長するための戦略の描き方」について伺っていきたいと思います。
足立:まずやるべきは、「自分たちの強みは何か」をしっかりと考えて、人に説明できるレベルにまで捉え直して、再定義することになります。「勝ち筋」を見極めるのは、それからです。
嶺井:スタートアップ、上場ベンチャーの場合、将来的な市場規模、マーケットの成長性を分析したうえで、自分たちが向き合うべき領域を見極めるケースが多いと思います。そういったアプローチに対してはどのように思われますか。

足立:市場の成長にあわせて会社も成長する可能性が高いのは間違いないため、考え方の1つとしてはありだと思います。ただ、それによって成長したとしても、その成長は、あくまで外部要因によるものであり、「企業努力」ではないことだけは忘れないでいただきたいと思います。「市場が成長しているから、業績がいい」というのは、「不況だから業績が悪い」と言っているのとあまり変わらない、ということです。
また、10%成長を続ける市場で、8%伸びている会社は本当に勝っていると言えるでしょうか。8%という数字だけを見れば十分伸びているように感じられますが、「市場」で見れば負けています。
では、成長市場、衰退市場問わず、マーケットで勝つためにフォーカスすべきものは何かといえば、それは「顧客」です。市場で勝つには顧客と向き合うしかありません。他社ではなく、自社の商品・サービスを使ってもらってはじめて「勝った」と言えるからです。
嶺井:市場での勝ち負けを判断する際、足立さんはどのような数字に着目されていますか。
足立:「絶対値」と「相対値」の2つです。
どんな目標も「数値」で測らなければ、勝っているのか、負けているのかの判断すらできませんから、社内や部署で「数値」を設定することは重要です。
ただ、社内目標である「絶対値」を達成していない場合でも、競合他社が数字を落としていれば、相対値は上昇しているわけですから、「勝ち」と言ってもよいでしょう。
たとえば、「昨年対比の客数の伸び率」において、ファミリーマートは業界ナンバーワンの会社を27カ月連続で上回っています(2023年6月末時点)。これは歴史的な数字であり、社内の士気も高まっています。つまり、絶対的な数字も大切だけれど、相対的な数字もまた重要だということです。
■「ポケモンGO」はいかにしてノンユーザーに訴求したか
嶺井:先ほど仰った「顧客」と向き合わなければ市場で勝てないというのは、本当にその通りだと思います。足立さんは、勝ち筋を見出す際、「顧客」をどのように捉えて、どうやってアプローチしているのでしょうか。
足立:「勝ち筋」の意味合いにもよりますが、既存事業を伸ばす場合でも、2つ目、3つ目の柱となる新規事業を考える場合でも、基本的なパターンは2つしかありません。1つは、既存の製品・サービスをよりたくさんの人に広めていくパターン。もう1つは、既存のお客様に違うものも販売するパターンです。
嶺井:パターンを考える際には、これまでになかったような新しい商品・サービスを開発したり、未知の領域に進出する必要があるのでしょうか。

足立:そこまで難しく考える必要はありません。たとえば、BtoBの場合、同じ製品・サービスであっても、別の業界に展開するだけで、まったく違う見え方になるケースが多いはずです。
また、BtoCの場合でも、スポーツクラブの会員にプロテインを販売したり、美容院に来ている方にヘアケア商品を案内したりと、さまざまな事例が存在しています。
嶺井:たとえば、BtoCの場合は、どのような手順を踏んで、勝ち筋を見つけていくことになりますか。
足立:まず、ターゲットになる顧客のセグメントを分析するところからはじめてはいかがでしょうか。「9segs」という考え方ですが、お客様は「商品を知っているし、使っている」「商品を知っているけれど、使っていない」「使っていたけれど、使うのをやめてしまった」「そもそも知らないので使っていない」等、9つに分類することができます。そのうえで、どのセグメントの顧客にどうアプローチするかを考えていくとよいでしょう。
アプローチ方法は大きくは2つあります。1つ目は、ノンユーザーに対して、ロイヤルユーザーの方々が「これはいいと思っているポイント」をしっかりと訴求する方法。これだけでも一定の効果が期待できます。
ただ、ロイヤルユーザーにとってのメリットが、多くのノンユーザーに響くとは限りません。その場合は、ロイヤルユーザーを裏切らない形で違うポイントを訴求する必要があります。「ポケモンGO」で展開したキャンペーンがまさにその好例です。当時の「ポケモンGO」は、「一度はプレイしたけれど、いまはやっていない」、あるいは「一度もプレイしたことがない」人がほとんどでした。
ロイヤルユーザーに対しては「これまで登場していなかったポケモンが登場します」とか「新しい形の対戦ができるようになりました」といった新機能などの情報が響く一方、ノンユーザーの方にはあまり効果がありませんでした。
ですから、機能ではなく、「いつものランニングがもっと楽しくなります」「夫婦での散歩が楽しくなります」「親子の会話が増えます」といったことを打ち出したのです。結果、日本ではじまったこのキャンペーンは劇的な成功を収め、その後グローバルキャンペーンとして採用されることになりました。
■注目したのは「認知」ではなく、「認識」
嶺井:ファミリーマートでも同じような手法を選択されたのでしょうか。
足立:ファミリーマートでは、「認識(=パーセプション)を変える」ことに注力しています。
コンビニ業界は特殊な業界で、「認知率」はほぼ100%であるため、考えるべきは「いかに来店頻度を上げるか」と、来店頻度を上げるためには「どんなふうに認識してもらうか」だけです。
人のイメージが簡単に変わらないように、企業や商品・サービスに対する認識も、そう簡単には変わりません。ですから、お客様との接点を増やしながら、一貫性のあるメッセージを発信し続ける必要があります。
具体的には、これまで特に強い特徴のなかった「ファミマ」のイメージを「(「クラスの優等生」的な業界トップ企業に対して)「クラスの人気者」という認識に変えたいと考えています。また、コンビニ業界は「大手三社」という表現をされることが多いのですが、私は「二強」と言われるようにしたい。「巨人と阪神」「windowsとmac」といった例は枚挙に暇がありませんが、3つと2つでは、お客様の印象はずいぶんと変わってくるからです。

「ファミマソックス」や「ボトルキープ」「40%増量作戦」なども、さまざまな「認識」を変えるための施策です。たとえば、最近ローンチした「生コッペパン」には「ファミマはおいしい」という認識をもっていただきたいという思いを込めています。おかげさまで最近は「ファミマ、おいしくなったね」と言われることが増えました。ただ、本当は「おいしくなった」のではなく、「昔からおいしかった」のですが、一度形作られた認識を変えるのは難しいのです。大きな意味で企業に対する認識が変わるには、少なくとも5~10年くらいはかかりますから、これからもさまざまな施策を展開していく予定です。
嶺井:日本マクドナルドのV字回復も「認識」を変えたことが奏功したのでしょうか。
足立:そうですね。当時のマクドナルドといえば、不祥事なども重なり、マクドナルドに行くのは、どこか「カッコ悪い」「ダサい」といったイメージが定着してしまっていました。ただし、新しい施策を打とうにも、マクドナルドはグローバル企業ですから、主力商品を変えることはできません。そのため、売っているものはそのままに、お客様の認識を、「カッコ悪い」「ダサい」から「楽しい」に変えていくことで、V字回復に貢献できたのでは、と考えています。
■なぜ、戦略は短期間で描くべきなのか
嶺井:「このあたりに勝ち筋を見出せそうだ」「こういう計画を実行していこう」といった戦略は、どのくらいの期間で描くのがよいでしょうか。
足立:私の場合は、3カ月くらいが多いですね。たとえば、ファミリーマートの時は、10月に入社して、全社プロジェクトを立ち上げて戦略を練って、翌年1月に役員会で合意、3月から実行フェーズに移行しました。
マクドナルドの時もだいたい同じで、10月に入社、12月に社内で新戦略プレゼンテーションをして合意をもらい、1月に全社発表というスケジュール感でした。
もちろん、年に2回しか新商品が出ないような業界であれば、ここまで急ぐ必要はないかもしれませんが、いずれにしても重要なのは、できるだけ早期に新しい方向に着手することです。スタートが早ければ早いほど、PDCAサイクルの回数が増え、改善や修正が進んでいくからです。
スピーディに進めることのメリットはもう1つあります。改革、方向転換というのは何かしらの痛みを伴うことが多いため、何年も続けてしまうと現場は疲弊してしまいます。そうした弊害を未然に防ぐためにも、永遠と分析ばかりするのではなく、長くても半年くらいで方向性を決めて走り出すことをおすすめします。
嶺井:改革、方向転換に向けて走り出したあと、どのくらいで成果を出すのがよいでしょうか。

足立:1年です。1年目で、なにかしらの成果が出なかったら、誰もついてきてくれません。普通の会社でも「3年計画」の1年目にまったく結果が出なかったら、見直しになるのではないでしょうか。また、2年目、3年目で息切れしてしまわないように、毎年、ある程度の結果が出るように、二の矢・三の矢をあらかじめ設計しておく必要もあります。
嶺井:成長の踊り場において、従業員はもちろん、取引先や株主に対して、どのようなコミュニケーションをしていくとよいでしょうか。
足立:踊り場というフェーズでは、経営陣だけが苦しいのではなく、従業員、取引先、株主も不安に感じています。ですから、「なぜ伸びていないのか」「私たちはこういう反省をして、こういうアクションをとっていく」「計画は現在ここまで進捗している」といったことを高頻度で発信していくべきです。
■経営陣が成長すれば、会社も成長する
嶺井:最後に、上場ベンチャーの経営者のみなさんにメッセージをお願いいたします。
足立:今回の対談では、「経営陣の限界が会社の限界であることを認識し、猛省したうえで、外部人材を登用せよ」とお伝えしましたが、もう1つ、会社を成長させるための方法があります。
それは、経営陣が率先して成長することです。ご存じのとおり、上場はゴールではありません。上場後も成長していくためには、経営層が成長するしかないのです。学びをやめたら成長は止まります。「習うは一生」という格言があるように、企業規模、売上がどんなに大きくなったとしても、学び続けること、成長し続けることの重要性を忘れないでほしいと思います。
嶺井:ありがとうございます。上場ベンチャーの経営者のみなさんと一緒に、私も学び続けていきたいと思います。足立さん、本日はありがとうございました。
足立:ありがとうございました。

