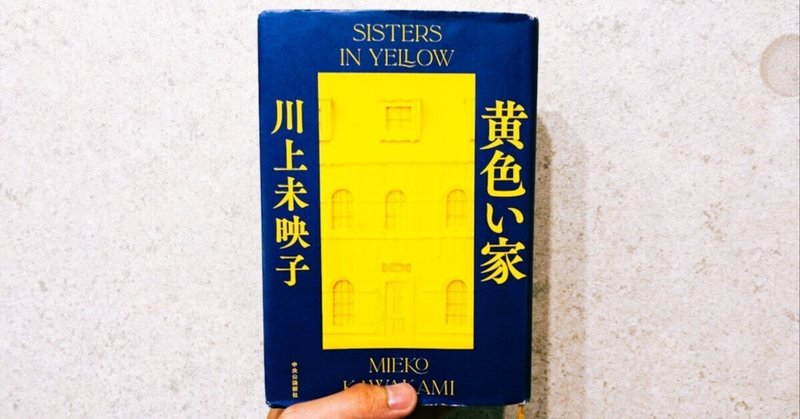
黄色い家、危うさと隣り合わせだった過去
川上未映子さんの「黄色い家」。貧困や犯罪と隣り合わせの環境や家という小さな世界以外に社会とは繋がりようもない鬱屈とした感覚は、川上さんの前作「夏物語」にも似た空気が流れているように感じた。
主人公の花は高校生時代、どうしようもない母との二人暮らしから脱するためバイトをして必死に貯金する。しかし、その努力を水の泡にするように貯金を奪われる壮絶な描写から物語は進展していく。無気力になった花はバイトを辞め、家出する。その先で頼ったのは、中学生の頃、突然母親がいなくなった時に一夏を共にした、母の知人・黄美子という女性。2人で暮らし始めた花と黄美子は三軒茶屋で「れもん」というスナックを始め、同じく家出同然の少女・蘭や桃子も加わっていく。
ここまでは良い話のようにも思えた(未成年が年齢を偽りスナックで働く時点で良くはない)ものの、そんな懸念が吹き飛んでいくほど、いくつもの不運なできごとが花を襲い「れもん」は継続を断念せざるを得なくなる。
収入が途絶えた花は生きるために、知り合いを辿ってカード詐欺に手を染め、どんどん危うい方向へと進んでいく。
なんて切ないのだろうと思った。努力家で機転も利く花は、自分の努力次第ではもっと違う環境で働けていたのかもしれない。また、必死にバイトをして貯金もできて、高校卒業と共に母の元から離れられたのならもっと違った善良な大人に出会えたのかもしれない。
彼女が進んでいく先は、家出して未成年ながらスナックで働き、カード詐欺に手を染める……。ことごとく暗闇なのだ。自分で考えて進んでいく姿には応援したくなるし、「れもん」を再開できるよう頑張ってほしいと手に汗握るシーンもある。しかし、それがどこまで行っても犯罪でしかないことが本当に切ない。
犯罪を続けることで自分が「れもん」を再開することはもう無理だと悟ったとき、道行く人たちはどうやって普通に生きていく資格を得ているのか分からないと吐露する。
この描写が本当にどうしようもなく悲しくなってしまう。
花には普通に生きるためのルートが分からないのだ。母と暮らしていた頃、貯金するのが銀行口座ではなく自分の部屋に置いていたことも周りの大人がまともだったなら……と思ってしまう。家出してからも未成年で、証明書類を持っていない花は口座を作れない。また、黄美子たち周りの大人は社会的には存在しないも同然の人々なので銀行口座を持つことや物件の審査も受けられるはずがない。
全てが暗闇の世界で、今すぐにもこの家のメンバーたちが崩壊しそうなのは分かっているが、たった一瞬でも幸せであってほしいと願う感情は昨年観た映画『ベイビーブローカー』と重なった。
ダメなことだとは分かっている。許容したいわけではないが、それぞれの不遇な過去を背負ってたどり着いた人たちが歪ながらも共に暮らすこの家で幸せになってもらいたい。だからこそ、この家を保とうと努力する花の姿を応援せずにはいられない。
僕も花と同じく、親に対して嫌いになれないながらも複雑な感情を持っている。また、高校生の頃、東北で出会った大人たちの影響で社会とのつながりを持ち、東京のスタートアップで働く現在に繋がっている。
もっといえば、自分は花のように罪を犯す方向には行かなかったが、過去にお金に困る時期もあった。お金が減っていく一方で不安に苛まれる花の心情はよく分かる。だからこそ、努力のベクトルがことごとく逆に働いていった花に歯痒い想いを感じるし、これは自分自身にもあり得たかもしれないと痛烈に感じるのである。
読後、1週間が経った今も脳裏でぐるぐるとこの小説のことを考える自分がいる。フィクションで交わらない世界でありながら、自分にとっては何か他人事だとは思えず、人生の隣り合わせにあったような気さえしてしまう物語だった。
いつも僕のnoteを読んでいただいてありがとうございます。スキ、コメント、サポートなどで応援していただけて励みになります。いただいた応援は大切に使わせていただきます。応援よろしくお願いします^^
