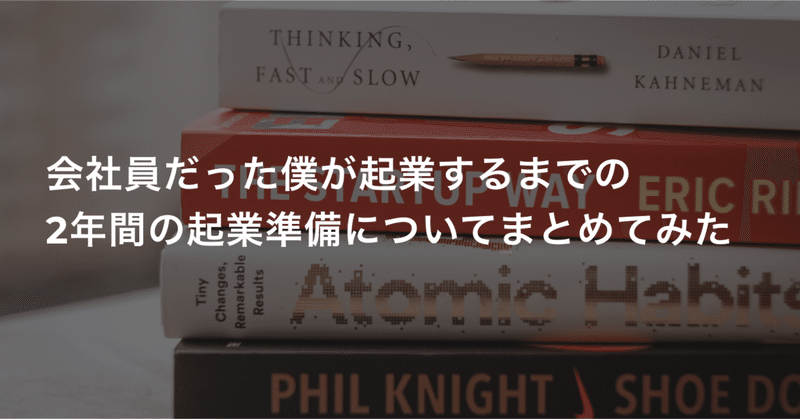
会社員だった僕が起業するまでの2年間の起業準備についてまとめてみた
株式会社Peer Lodge代表のまささいとうです。
いいね機能がなく視聴回数が見えない、やさしい音声SNS「Peer Radio(ピアラジオ)」をつくっています。
「#GW5日間で学べる起業準備」という、会社員で起業検討している方向けにまとめたツイートが好評だったので、
#GW5日間で学べる起業準備
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 1, 2021
友人から要望あり、会社員で起業検討している方向けにまとめてみます。
1日目:在職中の起業準備
2日目:創業メンバーどうやって集めたか
3日目:プロダクトどうつくったか
4日目:起業直前にやったこと
5日目:もう一度過去に戻れるならやりたいこと
後ほど1日目を更新🧑💻
2018年4月〜2020年3月の「会社員だった僕が起業するまでの2年間の起業準備」について、noteにまとめてみました。
かつての自分と同じように会社員から起業を志す方に、少しでも力になれたら嬉しいです。
【1日目:在職中の起業準備編】
会社員で起業検討している方向けに、#GW5日間で学べる起業準備
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 1, 2021
についてまとめてみます。
【今日のテーマ】
👉1日目:在職中の起業準備 pic.twitter.com/OdymFQpLon
<要約>
・いきなり辞めるのではなく、週末にプロダクト開発進めておくのはおすすめ
・会社設立してからはお金稼ぐのが最優先で時間に余裕がなくなるため、非エンジニアは退職前にプログラミング勉強して自分でコーディングできるようになっておいた方が良い
・ひとまず王道な「起業の科学」を読みながら進めてみると良い
・起業してからやることと会社の新規事業とではやること違う(給与貰えない、予算ない、人的リソースない、会社ブランドない)
・「会社辞めたら通用しないよ」は退職引き止めワードなので、特に気にせず早く起業した方が良い
・退職して起業してもいつでも会社員に戻ろうと思えば戻れるし、起業期間の経験が市場価値を高めてくれるので、実はそんなにリスクはない
■参考:起業までの経緯
・2014年に新卒でエン・ジャパンに入社
・2016年から新規事業子会社にて1→10の事業グロースを担当
・起業準備は2018年4月頃からスタート
・2020年3月に退職し、2020年4月に起業
・自分の場合、起業までに2年かけてしまったが、もっとスピードは早められるはず
■参考:起業準備期間にしたこと
2018年4月:大きな方向性を決める
・結婚前提だった彼女(現妻)に頭を下げて、平日夜と土日を起業準備の時間に当てる
・ひとまず起業の科学、RUNNING LEANを読む
・まずは解決したい課題の領域を自分の原体験に基づいて考える
・自分の場合は母のうつ病の原体験から、メンタルヘルス領域での起業を決意
2018年4月〜2019年3月:課題・ユーザーの解像度を高める
・ストレスに関するユーザーインタビューを30人ほどに実施
・メンタルヘルス事業を行なっている企業の方や精神科医の方にインタビューを実施
・ストレス、メンタルヘルス、うつ病などについての論文や市場調査などを確認し、問題の構造を理解
・競合サービスリサーチ(国内・海外)を実施
※本当はこの時に、市場規模やマネタイズ可能性についてもさらに検討を深めておくと良かった
2019年4月〜2019年10月:仲間集め
・ノーコードで出来るプロトタイピングを進めるのと併行して、デザイナーとエンジニアのメンバーを口説いてきて仲間になってもらう(※2日目で詳細に記載)
2019年4月〜2019年10月:プロトタイピング
・自分なりの課題仮説をいくつか立て、仮説が正しいかをユーザーインタビューで検証
・仮説がある程度正しそうだったので、解決策のアイデアをいくつか立てる
・Prottでペーパープロトを作成し、ユーザーインタビューで反応を見る
・反応が良さそうだったがアプリを開発して使われるかどうかは不明だったので、ひとまずFacebookメッセンジャーグループを作成し、アプリでやりたいことをそこでユーザーに試してもらう
・反応が良かったため、アプリの開発を決意
2019年11月〜2020年3月:起業直前の準備
・アプリα版をローンチ(※3日目で詳細に記載)
・α版はGoogle FirebaseというサービスでApp Store申請をせずに独自に配信(申請しなくても良いので早い)
・退職更新や手続き系を済ませ、2020年4月に起業(※4日目で詳細に記載)
【2日目:創業メンバーどうやって集めたか編】
会社員で起業検討している方向けに、#GW5日間で学べる起業準備
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 2, 2021
についてまとめてみます。
【今日のテーマ】
👉 2日目:創業メンバーどうやって集めたか pic.twitter.com/cmbuc7CL6r
<要約>
・自分はBiz職だったので、UI/UXデザイナーとエンジニアの仲間を探すことに
・同じポジションの人は採用しやすいが、役割が被らない方が上手くいく印象
・「こういう社会にしたい」という大義があれば採用しやすい
・創業メンバー採用に向け、yentaや知人の紹介・知人への連絡などを用いた
・求人募集などは用いなかった
・50人ほどに会うもなかなか創業メンバー見つからず
・結局、実の三男(実務未経験)にエンジニアとしてジョインしてもらうことに
・デザインは、次男の知人のデザイナーの方に手伝ってもらうことに
・経験もあるに越したことはないが、熱意と考え方が合うかが何より大切
■参考:創業メンバー集めに用いた手法
yenta
・毎日地道にビジネスマッチングアプリのyentaでマッチングしている人を増やす
・デザイナー、エンジニアのプロフィールの方全てに連絡
・何十人かに会うも、yentaで一度会ってすぐ起業しようとはなかなか至らなかった
・有料プランは契約していなかった
知人の紹介・知人への連絡
・Facebookメッセンジャーなどで、これまで繋がりがあって一緒に働きたいと感じている人に地道に連絡
・こういう問題を解決したい、というwhyの部分を伝える
・何十人かに会うも、自分と同じBiz職では手伝いたいと言ってくれる人が多かったが、デザイナー、エンジニアの方は見つけられず
※ビジネスミートアップへの参加などは用いなかったが、手法としては可能性ありそう(その後のメンバーはそこから採用も)
■参考:結局選んだ創業メンバー
エンジニア→実の三男(未経験)
・エンジニア採用しようとするも、なかなか採用に苦戦
・whyに共感してくれる創業メンバーというより「時給いくらであれば」という業務委託を希望する方しか見つけられず
・結局、当時大学2年生工学部でプログラミング勉強中だった実の三男に声をかける
・未経験だったが、熱意と共に猛勉強して1人でアプリを創り上げる
デザイナー→次男の知人
・デザイナー採用にもそもそもの人脈がなかったので苦戦
・次男(デザイナー)に相談したところ、次男はジョイン難しいが、知り合いのデザイナーの方を紹介してくれることに
・メンタルヘルス問題を解決したいというwhyの部分を伝え、熱烈に口説く
・同じ問題を解決したいという想いを持っている方だったため、アプリデザインに協力してくれることに
【3日目:プロダクトどうつくったか編】
会社員で起業検討している方向けに、#GW5日間で学べる起業準備
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 3, 2021
についてまとめてみます。
【今日のテーマ】
👉 3日目:プロダクトどうつくったか pic.twitter.com/DDiGufCtTR
<要約>
・まずは開発を必要としない方法でアイデアがユーザーに求められるものかどうかを検証
・つくりたいプロダクトのアイデアをペーパープロト(紙に書いたアイデア)で作成し、ユーザーインタビュー
・自分たちの場合はその後、ひとまずFBメッセンジャーグループを作成し、アプリでやりたいことをFBグループ内でユーザーにテスト
・この時点までにデザイナーとエンジニアを仲間に
・FBグループでのテスト結果を元にデザイナー、エンジニアとアプリの仕様を決定
・話す、聴く、コメントするという必要最小限の機能だけ搭載したiOSアプリα版をローンチ
・α版は早めのローンチ・早めの修正ができるように、Google FirebaseというサービスでApp Store申請をせずに独自に配信
■参考:ペーパープロトでの検証行程(自分たちの場合)・参考となる類似アプリをリサーチして実際に触ってみる
・アイデアを必要な機能に落とす
・機能を元に簡単な遷移図を手書きの絵で作成してみる
・手書きの絵を元に簡易的なUIを作成してみる
・当時はデザイナーのメンバーもいなかったので、画像をつぎはぎしてパワポでUI作成
・当時はAdobe XDやFigmaなどを使う技術がまだなかったが、無料で使えるので使えるようになると理想(※現在はFigmaを利用することが多い)
・作成したUIをノーコードで使えるProttなどを用いてアプリっぽく遷移するようにして、何人かに見せる
(※当時はStrikinglyを使っていたけどProttが良い、STUDIOなどもおすすめ)
・何人かに見せて良いリアクションが得られたので、実際に動く形で実験してみようと決定
■参考:FBメッセンジャーでの検証行程
・FBメッセンジャーで、ユーザー1人1人と運営チームのグループをつくり、声を残すことに抵抗はないだろうか?声で気持ちを残してくれるだろうか?ということを検証
・ユーザーが実際に声で気持ちを残してくれることが明らかに
・次に、複数人のユーザー同士でFacebookメッセンジャーグループをつくり、知らない人同士のコミュニティで声をシェアすることに抵抗はないだろうか?お互いの声に対してリアクションは生まれるだろうか?ということを検証
・知らないユーザー同士でも声をシェアし合いお互いにリアクションを送り合うということが明らかに
・ここからiOSアプリα版の開発に移行
■参考:サービスのネーミングについて
・FBメッセンジャーのテスト時は仮称だったが、ユーザーがサービス名をすぐに覚えて何度も口にしてくれることが分かったので、ネーミングもこれでいこうと決定
■参考:α版作成までの行程
・必要な機能を書き出す
・機能を元に遷移図を作成
・FigmaでUI作成
・作成したUIをSwiftで実装
・話す、聴く、コメントするという必要最小限の機能だけ搭載したiOSアプリα版ローンチ
・Must-have(なくてはならない機能)だけ実装、Nice-to-have(あったらうれしい機能)は実装しない、ということを強く意識
・コアな価値がユーザーに刺さるのかを検証
・大々的にリリースせず、知人やこれまでインタビューに協力してくれた方への招待のみで、徐々にユーザー獲得して検証
・α版は早めのローンチ・早めの修正ができるように、Google FirebaseというサービスでApp Store申請をせずにテストアプリを配布できる機能を使ってテスト版を配布
・TestFlightの場合でもAppleへの申請用の機能開発が必要になるので、それより簡単にテスター配布するためにFirebaseでのテスター配布を選択
【4日目:起業直前にやったこと編】
会社員で起業検討している方向けに、#GW5日間で学べる起業準備
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 4, 2021
についてまとめてみます。
【今日のテーマ】
👉 4日目:起業直前にやったこと pic.twitter.com/5SUkne2Z3x
■参考:起業直前にやったこと
・退職の半年前に退職の旨を会社に伝える
・既にローンチしていたα版を運用しながら、β版の開発を進める
・資本金を貯める(少額でも大丈夫)
・税金について簡単に調べる(ネットで複数記事見れば大体分かる)
・事業計画書を大まかに1年分作成(期中に度々修正)
・目先の資金を得るための業務委託案件の獲得(知人・クラウドソーシング)
・会社名を決める
・会社設立freeeを使って会社設立手続き(これに沿って進めればほぼ困らない)
※銀行口座は法人設立後に開設
※補助金・助成金などについてもっと調べておけば良かった
■退職の半年前に退職の旨を会社に伝える
半年前は早すぎるくらいだが、直前すぎると迷惑かかるため、早めに報告。
■既にローンチしていたα版を運用しながら、β版の開発を進める
退職前にサービスローンチしておいて良かった。ユーザーの反応が良かったので、起業することに迷いがなくなった。
■資本金を貯める
「起業のファイナンス」に書いてある資本金の目安を見習って資本金を設定。金額は個人差あると思われるが、少額でも大きな問題はないのでは。
■税金について簡単に調べる
ネットで複数記事見て、大まかに理解を深める。既に起業している人に話を聞くと良いかも。あとはその都度調べて対処。
■事業計画書を大まかに1年分作成
事業進めながら計画変わっていくので、その時点の内容でひとまず1年分作成。期中に度々修正した。3ヶ年計画などは事業の進捗読めないため、ほぼ役に立ったことがない。
■目先の資金を得るための業務委託案件の獲得
ひとまず目先の資金を得るべく、業務委託案件を獲得。前職時代の上司で転職や独立している人に退職の旨伝えたり、クラウドソーシングで案件獲得などを行なっていた。
■会社名を決める
会社名を決定。同様の社名がないか調べたり、SEO的に検索して上位表示されるかを確認したりした。
■会社設立freeeを使って会社設立手続き
これに沿って進めればほぼ困らない。資本金確定、印鑑購入、定款作成、法務局に提出する登記資料作成など全て進められる。
※銀行口座は法人設立後に開設
※補助金・助成金などについてもっと調べておけば良かった
【5日目:もう一度過去に戻れるならやりたいこと編】
会社員で起業検討している方向けに、#GW5日間で学べる起業準備
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 5, 2021
についてまとめてみています。
今回が最終回。後ほどnoteに全部まとめてアップします!
【今日のテーマ】
👉 5日目:もう一度過去に戻れるならやりたいこと編 pic.twitter.com/c2z4OXDi1X
<要約>
・期限を決めてスピード感を持って、事業を進捗させたい
・App Storeに早めのローンチをしたい
・マネタイズにつながるモデルかどうかの検証もローンチ前に実施しておきたい
・もっと早く退職・起業しておきたい(タイミングとしては2年早く)
・社外の壁打ち相手を早めに見つけておきたい
・補助金・助成金関連の情報は該当のものがないか常にリサーチしておきたい
・退職前にプログラミング勉強して、自分でコーディングできるようになっておきたい
・書籍にかなり費用をかけてしまっているので、図書館をもっと有効活用しておきたい
■期限を決めてスピード感を持って、事業を進捗させたい
期限を決めないといつまでもダラダラと事業を進めてしまう。期限を決めることでスピード感を上げたい。
ビジコンや壁打ちスケジュールを入れたりして、外部要因によって強引に期限を決めたりするのが良さそう。
■App Storeに早めのローンチをしたい
ローンチしないと正しいか間違っているか分からないことが多いので、何事も早めにローンチして失敗と成功を早めに判断したい。
■マネタイズにつながるモデルかどうかの検証もローンチ前に実施しておきたい
プロダクトに関する検証だけでなく、そのプロダクトでのマネタイズにはどのような形が最適なのかも早めに検証しておきたい。
マネタイズの部分が欠けているサービスはビジネスとしては不完全。
■もっと早く退職・起業しておきたい
会社の新規事業と起業は全く別物。成果出なければ給与出ない、事業にかけられる予算ない、人的リソースない、会社のブランドないなど条件的な違いがある。起業しないと分からないことが多く、これまでの経験が役立たないことばかり。早めに起業することに個人的には賛成。
■社外の壁打ち相手を早めに見つけておきたい
自分たちだけで事業を進めると視野が狭くなってしまったり、最適なスピードで事業進捗できているのかの判断ができない。起業家やVCの壁打ち相手などを早めに見つけたい。
■補助金・助成金関連の情報は該当のものがないか常にリサーチしておきたい
補助金や助成金を侮るべからず。サイトはかなり見づらくて心が折れそうになるが、該当するものには申請した方が絶対にいい。気付いた時には期限切れというパターンが多いので定期的にチェックしたい。
■退職前にプログラミング勉強して、自分でコーディングできるようになっておきたい
会社設立してからはお金を稼ぐことや目先のタスクが最優先で時間に余裕がなくなるので、非エンジニアで起業したい人は退職前にプログラミング勉強して自分でコーディングできるようになっておいた方が良い。
■書籍にかなり費用をかけてしまっているので、図書館をもっと有効活用しておきたい
書籍でのインプットはとても大切で必要不可欠だが、非常にお金がかかる。図書館には意外とビジネス書やスタートアップ関連の名著も揃っている(特に東京)。借りられるなら借りてコストを抑えるのが創業期には良い。
おわりに
なかなか上手く進められなかったことばかりでしたが、自分が行ってきた2年間の起業準備について、まとめてみました。
思い返すと「あの時こうしておけばよかったな」と思うことばかりですが、それも全て今の経験になっているように感じます。
まだ偉そうに何かを語れるほど何も成し遂げていないですが、かつての自分と同じような境遇の誰かに届いて、少しでも力になれたら嬉しいです。
--
いいね機能がなく視聴回数が見えない、やさしい音声SNS「Peer Radio(ピアラジオ)」をつくっています。
気になられた方おられましたら、よろしければユーザー登録いただけたら嬉しいです👏
--
Twitterにて起業からの日々の学びを共有しています👇
GWも終わりなので、起業家2年目の僕が連休明けで仕事のモチベーションを上げたい時に読むおすすめ記事を紹介してみます
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 5, 2021
リプ欄に記事へのリンク記載してます👇! pic.twitter.com/lzBMA4Ya5w
GWなので起業家2年目の僕が創業1年目に読んでよかったおすすめ本を紹介してみます pic.twitter.com/5WM0LFTnxJ
— 斎藤 雅史 | Masa Saito | Peer Lodge CEO (@masashignio) May 1, 2021
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
