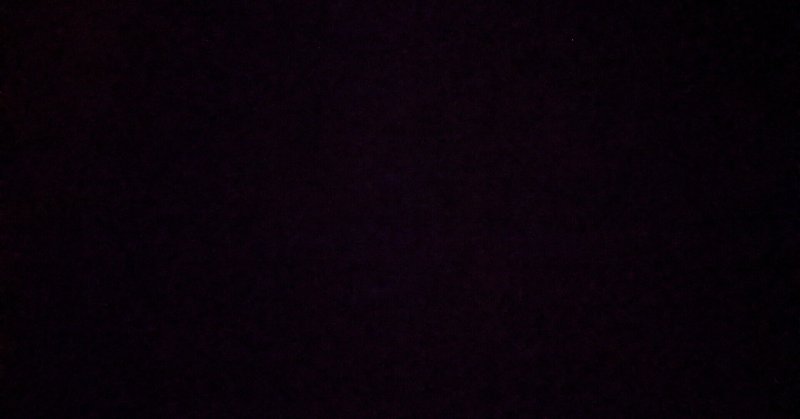
shift innovation #43(f∞ studio hack 4)
今回は、FabCafe Kyotoで開催された「f∞ studio『これも写真❓』ワークショップ」に参加しました。

今、「写真」に囲まれて生きている中で、スマートフォンのカメラで簡単に写真を撮り、SNSで瞬時に共有する時代である一方で、「写真」の定義は曖昧になっています。
f∞ studioは、従来の「写真」の概念にとらわれず、その周辺の未来の写真の意味や価値を探求するコミュニティーであり、「写真」の可能性を信じ、未来の写真の意味・みることの意味を模索し続けています。
今回のワークショップでは、f∞ studioがこれまでに得た知見を基に、フィールドワークに出かけ、「これも写真❓」と感じるものを写真や写真以外の方法で採取し、それらを持ち帰り、グループディスカッションを通して、未来の「写真とは❓」を考えていきます。
【「見えないもの」の可視化】
shift innovation #42(f∞ studio hack 3)において、「今後、デジタルのさらなる進展により、視覚的要素がないものであっても「これも写真❓」の概念の範囲となるかもしれない、また、「記録する」ものではなく、脳内に「記憶する」ものであっても「これも写真❓」の概念の範囲となるかもしれない」とまとめました。
今回は、「視覚的要素がないものであっても『これも写真❓』の概念の範囲となる」という視点から、「『見えないもの』を可視化する」というテーマに基づき、新たなコンセプトを検討することとします。
【「これも写真❓」の構造】
「これも写真❓」
⚫︎「対象物」→「媒体」→「対象物の過去・現在・未来を表現」
「写真」
⚫︎「対象物」→「媒体(カメラなど)」→「写真(印画紙)」「3D画像」「立体物」
「FedEx」ワリード・ベシュティ氏
⚫︎「対象物」→「物流システム(移動)」→「対象物の移動に伴う傷などの痕跡」
「コンセプト2」
⚫︎「スマートフォン」→「雨(自然)」→「水面の波紋(仮想画像)」+「音」
「コンセプト4」(「tap diary」)
⚫︎「スマートフォン」→「指(タップ)」→「写真」+「音楽の自動選曲」
【コンセプト1 「砂丘の風紋」】
はじめに、shift innovation #42(f∞ studio hack 3)で提示した事例のうち、「FedEx」は、「媒体」が「物流システム」という人工物(システム)であり、「コンセプト2」は、「媒体」が「雨」という自然物ですが、比較的取り組みやすいと考える「自然物」に基づき検討することとします。
「自然物」を「媒体」とする上で、「見えないもの」として、「風」を捉えることとします。
例えば、「風が強いと木の葉が大きく揺れる」「海に風があると波が大きくなる」というように、「これも写真❓」の構造に基づき、「風」を「媒体」とし、様々な「対象物」を検討するものの、「変換した対象物を記録する」(「カメラ」の場合、写真(二次元の画像))を思うようにイメージすることができませんでした。
これは、木の葉が大きく揺れた場合であっても、大きく揺れた木の葉は元に戻る、また、波が大きくなった場合であっても、大きくなった波は元に戻るため、「変換した対象物を記録する」をイメージすることができない理由であると理解することができました。
そこで、風が吹くことにより、対象物が変化するものの、対象物が元に戻ることなく、そのまま維持されるものとして、「砂丘」(「砂」)をイメージすることができました。
「砂丘」の場合、「風」が吹くと「砂丘」に大きな「風紋」ができるというように、「砂丘」であれば、変化後に対象物が元に戻ることなく維持されることから、「変換した対象物を記録する」ことができることとなります。
これらのことから、「これも写真❓」の構造としては、「砂丘」→「風(自然)」→「砂丘の風紋」となり、「見えない風に吹かれる砂丘」を「風により砂丘に描かれた風紋」により表現することによって、「砂丘の風紋」というコンセプトとなりました。
【コンセプト2 「スマホ依存からの更生」】
次に、コンセプトである「砂丘の風紋」から新たなコンセプトを検討することとします。
「砂丘の風紋」である「砂丘に風が吹くと風紋ができる」から「砂丘に風が吹くと足跡が消える」へ視点を反転させることとしました。
そして、「砂丘に風が吹くと足跡が消える」から「いつの間にか自然に消えている」へと解釈し直しました。
そして、「いつの間にか自然に消えている」から「スマートフォンの利用履歴」をイメージしたことにより、スマートフォンの利用履歴は一定期間が過ぎると自動的に消えていくことを捉えました。
我々は、朝、目覚まし時計代わりにスマートフォンを利用することからはじまり、SNSやニュース・天気を起きてからすぐにチェックします。
そして、出勤途中の駅でコーヒーをスマートフォンの電子マネーを使い、電車に乗るときは改札口でスマートフォンをかざし、電車の中ではひたすらスマートフォンでゲームをする・・・・・。
スマートフォンがあると便利ではあるものの、スマートフォンに依存して過ぎてしまうことにより、スマートフォンがないと生活できない、何もすることがないということとなっています。
もし、スマートフォンの利用履歴が残り続けることとなり、それも、利用履歴の文字が立体化され、目にみえるものとなった場合、自分の部屋は、どれくらいの期間で、立体化した利用履歴の文字で埋め尽くされてしまうのでしょうか。
1週間、1日、いや1時間で、立体化した利用履歴の文字で自分の部屋が埋め尽くされてしまうかもしれません。
そこで、スマートフォンの利用履歴と3Dプリンター機器を連動させることにより、スマートフォンを利用すると、3Dプリンター機器から立体化した利用履歴の文字が大量に出続けることにより、スマートフォンに依存していることを自認させるなど、「スマホ依存」を警鐘するというコンセプトとなります。
(「文字で埋め尽くされる、息苦しい、死んでしまう・・・❗️」)
3Dプリンター機器から出てくる立体化した利用履歴の文字は、バラバラになって出てくることとなり、それは、スマートフォンの利用が自分にとって意味があるものであれば良いのですが、そのほとんどが意味のないものであることを表しています。
(「鹿の糞のようにポロポロポロポロ出てくる❗️表現の仕方がちょっと・・・❗️」)
意味のないスマートフォンの利用を少なくし、意味のあるスマートフォンの利用の仕方とはどのような仕方であるのかを考えるきっかけになればと思っています。(「なんか、『これも写真❓』っぽい感じになったような・・・❓」)
これらのことから、「これも写真❓」の構造としては、「スマートフォンの利用履歴」→「3Dプリンター機器」→「立体化したスマートフォンの利用履歴の文字」となり、「スマートフォンに依存した行為」を「スマートフォンの利用履歴の文字を立体的に可視化すること」により表現することによって、「スマホ依存からの更生」というコンセプトとなりました。
【コンセプト3 「傷アート」】
次に、コンセプトである「スマホ依存からの更生」から新たなコンセプトを検討することとします。
前段で検討した「コンセプト」の構造とは、「砂丘」→「風(自然)」→「砂丘の風紋」、「スマートフォンの利用履歴」→「3Dプリンター機器」→「立体化したスマートフォンの利用履歴」であり、これらは、「いつかは消えてなくなるものを可視化し残す」というものとなります。
いつかは消えてなくなるものとして、「残しておきたいが消えてしまう」というものもあれば、一方で、「できれば残らず消してしまいたい」というものもあります。
例えば、「大切なものに傷が残る」という場合があると、「大切なものに傷がなければよかった」というように、後悔している場合もあると思います。
これは、現実として起こってしまったことを、ないものとしたいというように、自分ごととして受け入れることができず、悩んでいる状態であると考えることもできます。
このような悩みを自分ごととして受け入れることができるように、「大切なものに傷が残る」ものの一部をあえて残すというコンセプトとなります。
(「大切なものの捉え方、すごくセンシティブ、ん・・・難しい・・・。」)
しかし、傷をそのまま残すと、他者がその傷に気付くことにより、さらに自分ごととして受け入れることが困難となる場合があると考えられます。
そこで、実際の傷を抽象化して残すことにより、他者に気付かれないようにするという方法もありますが、逆に、あえて実際の傷を具象化(拡大)し、その一部分のみ残すことにより、他者には気付かれず、自分だけが傷があることを知ることによって、自分ごととして受け入れることができるのではないかと考えられます。
そして、「大切なものに傷が残る」を複数の視点から捉えた画像を立体処理した上で、3Dプリンター機器を使用することにより、立体物として抽出し、オブジェとして家に置いておく、小さなアクセサリーとして持ち運ぶなど、様々な形として残すことができます。
これらのことから、「これも写真❓」の構造としては、「大切なものに残った傷」→「3Dプリンター機器」→「傷の一部を拡大したオブジェ」となり、「自分ごとにしたい傷への思い」を「傷の一部分を拡大し立体的に可視化すること」により表現することによって、「傷アート」というコンセプトとなりました。
【まとめ】
今回、「これも写真❓」として捉えたコンセプトは、フィールドワークをする前に捉えた「対象物」→「媒体」→「対象物の過去・現在・未来を表現」という構造に基づき検討したものとなります。
そして、「これも写真❓」の条件として捉えた「画像」「映像」など視覚的要素があること、「変換」するための物理的な装置があること、「記録する」という機能があることを踏まえた上で、コンセプトをブラッシュアップしたものとなります。
しかし、今回検討したコンセプトは、「これも写真❓」というよりも、「写真」に極めて近いものではないのかと感じました。
もしかすると、はじめに「これも写真❓」の構造を検討したことがトリガーとなり、それが固定観念となることによって、「写真」の範囲から出ることができなかったのではないなかと感じました。
そこで、はじめに捉えた「これも写真❓」の構造にとらわれることなく、「無」の状態でフィールドワークにおいて、関心があるものを感じたままにスマートフォンで撮った方が、「これも写真❓」として広がりがあったのではないかと感じました。
そして、はじめに捉えたコンセプトは、何か面白いものができるのではと思っていたものの、最終的なコンセプトは普通のものに収束したことからも、固定観念にとらわれることなく、飛躍的な視点でコンセプトを検討する必要があると改めて感じました。
(「っていうか、どのコンセプトも実現可能性が低い妄想だよね・・・❗️」)
なお、これらの「コンセプト」は、フィールドワークなどにより捉えた自然物から感じた現象を可視化し(「水溜り」「砂丘の風紋」)、プロトタイプ的に捉え直した上で(「コンセプト2」「スマホ依存からの更生」)、プロダクト的なものに変換する(「コンセプト4」(「tap diary」)「傷アート」)というプロセスを経たことにより、コンセプトが作り上げられる中で、思考が発散し収束することを捉えることができたのではないかと考えられます。
「水溜り」
⚫︎「水溜り」→「雨(自然)」→「水面の波紋」
「コンセプト2」
⚫︎「スマートフォン」→「雨(自然)」→「水面の波紋(仮想画像)」+「音」
「コンセプト4」(「tap diary」)
⚫︎「スマートフォン」→「指(タップ)」→「写真」+「音楽の自動選曲」
「砂丘の風紋」
⚫︎「砂丘」→「風(自然)」→「砂丘の風紋」
「スマホ依存からの更生」
⚫︎「スマートフォンの利用履歴」→「3Dプリンター機器」→「立体化したスマートフォンの利用履歴」
「傷アート」
⚫︎「大切なものに残った傷」→「3Dプリンター機器」→「傷の一部を拡大したオブジェ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
