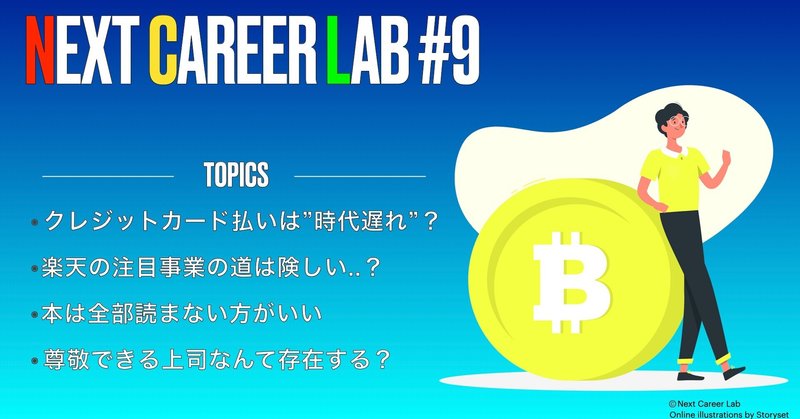
Next Career Lab. #9 - クレジットカードvs後払い,楽天モバイル事業の黒字化への道,本は全部読むな,尊敬できる上司はどこにいる?etc
Next Career Lab.(ネクストキャリアーラボ)は「次のキャリアの"一手"を考えるメディア」です。
キャリアを考えるヒントをお届けして、みなさんとキャリアの攻略法について考えていきたいです。
本記事の内容は次の通りです。
1. Biz Update
2. 決算から読み解く業界動向
3. 失敗を語ろう
4. 質問コーナー
5. 今週のオススメ本
6. 雑談&コラム紹介
Next Career Lab. について詳しく知りたい方は⬇︎の記事からどうぞ。
バックナンバーはこちらから!
それではいきましょう!
1. Biz Update - クレジットカード払いはもはや時代遅れ? -
今週は新たな決済手段として注目を集める「後払い」に注目です!
「BNPL(Buy Now Pay Later)」つまり「今買って、後で支払う」という言葉が海外でもバズワードになったりと盛り上がりを見せています。
今年9月、アメリカのフィンテックの巨大企業であるPayPal(ペイパル)が日本の後払いサービスを提供するPaidy(ペイディ)を買収したことで話題になりました。
Paidyは「スマホでかしこく後払い」をテーマに、amazonやappleにもサービスを提供している注目の会社です。

Paidyの1つの特徴は「利用のハードルの低さ」です。なんと、メアドと携帯番号を登録するだけで使うことができるのです。
後払いというと、"クレジットカード払い"を想像する人も多いと思いますが、クレジットカードを登録するときは会社や貯金額などの細かい情報まで登録して、審査があってやっと使えるのが一般的です。
それに比べてPaidyのサービスはメアドと携帯番号だけで後払いを始めることができるので、かなり簡単です。
さて、ではなぜ最近この後払いが注目されているのでしょうか。
「後払いもクレジットカードも一緒でしょ?」
と思う人もいるかもしれません。しかし、実はこの後払いはクレジットカードの不便さを見事に解消したサービスなのです。

上の図は、メルカリが行った「メルペイ、後払い決済サービスに関する実態調査」の結果です。
後払い決済サービスを使う理由に注目してみましょう。
① 支払うタイミングを調整できる
② 支払う前に商品を確認できる
③ 利用金額を把握しやすい
1位は「支払うタイミングを調整できる」ことです。
例えばPaidyの支払い方法を見ると、手数料無料で翌月や、3回払い、24回払いなどを選択することができます。
そして、3位の「利用金額を把握しやすい」という点でもクレジットカードとの差別化が見えます。
支払い方法の柔軟さ、予算管理、そして利用履歴の見やすさなどのUIUXを改善してクレジットカードの利用金額がわかりづらいことや、ついつい使いすぎてしまう問題を解決しようとしています。
クレジットカード払いの不便さを解消して取って変わるのがこの「後払い決済サービス」というわけです。
そしてもう1つクレジットカードとの違いは「決済金額」にあります。

後払いサービスではクレジットカードに比べて圧倒的に少額決済が多いです。
これまでデータを総合的に判断すると、少額から手間なく便利に使える、というのが後払いの売りになっていることがわかります。
矢野経済研究所の調査によると、このまま成長を続ける後払いの市場規模は、3年後の2024年には「1.8兆円」に達すると予測されています。

(EC決済サービス市場に関する調査を実施(2021年)より引用)
そしてもう1つ後払いについても面白いのは、EC各社と後払いサービスの業務提携の動向です。

大手ECサイトがそれぞれ違う会社とコンビを組んで、後払いサービスを導入しています。
唯一、メルカリだけが自社の決済サービスを使っている状況です。
後払いサービスを大きくしていけるかどうかは、ECサイトと一心同体、という状況もどんな影響があるのか、注目です。
以上、今週のBiz Updateでした!
2. 決算から読み解く業界動向 - 楽天の注目事業の黒字化の道は険しい...? -
今週は第4のキャリアとして注目のあの企業、そうです「楽天」に注目です!
楽天グループ
三木谷浩史によって創設された新興財閥であり、インターネット関連サービスを中心に展開する日本の企業。インターネットショッピングモール「楽天市場」、総合旅行サイト「楽天トラベル」、フリマアプリ「ラクマ」などのECサイトを運営する。日経平均株価の構成銘柄の一つ。
Wikipediaより引用
楽天が「2021年度第3四半期」の決算を発表したので解説していきます。
■ 決算概況

(2021年度決算短信・説明会資料 より)
各サービスごとの売上収益、営業利益、そして前年比の成長率は以下の通りです。
(単位: 十億円)
・インターネットセグメント
売上収益 : 239.4 (+11.6%)
営業利益 : 24.5 (+185.2%)
・フィンテックセグメント
売上収益 : 150.9 (+4.8%)
営業利益 : 21.2 (-5.1%)
・モバイルセグメント
売上収益 : 54.9 (+21.2%)
営業利益 : -105.2 (-43.8)
・連結
売上収益 : 406.9 (+12.6%)
営業利益 : -57.7 (-29.1)
最終の連結業績としては約580億円の「赤字」に終わりました。
やはりモバイルセグメントの投資の影響が大きいですが、楽天カード、楽天銀行やポイント、などで構成されるフィンテックセグメントにおいても営業利益がマイナス成長と少し停滞気味の決算になっています。
■ モバイルセグメントの行方やいかに

(2021年度決算短信・説明会資料 より)
増収とコスト増の要因はそれぞれ以下のようなポイントです。
[増収の要因]
・無料プランなどから課金プランへ移行したユーザーが増えた
・ローミングエリア(KDDI)を自社回線に切り替えた
[コスト増の要因]
・エリア拡大のためのネットワーク関連費用がかさんでいる
特にこの中で楽天にとって優先度が高いのは「ローミングエリアの自社回線への切り替え」でしょう。
前回の決算会見で三木谷浩史会長は「KDDIへのローミング費用が高すぎる」とぼやいていたりもしました。
いかに早く基地局を拡大して、ローミングエリアを自社回線に切り替えて不要なコストを削減していけるかが、楽天モバイル黒字化への第一歩となりそうです。
しかし不運なことに、世界的な半導体不足が基地局拡大の足止めをしていたりと、まだまだ課題はたくさんありそうです...
モバイル事業は9月までの契約数は411万件と増加傾向ではあるものの、1月から9月の全体の最終損益は922億円の赤字になっています。
決算での三木谷会長の「2023年度のモバイル事業黒字化」は達成されるのでしょうか。
今後も注目です!
3. 失敗を語ろう - 本は全部読まない方がいい -
今週の「失敗を語ろう」のコーナーは、少し趣向を変えて"読書"に関する話です。
大袈裟な話をするわけではないのですが、これまで転職を成功させたり、仕事で成果を出せてこれたのは「読書」のおかげだと思っています。
読書は最強のライフハックです。
読書の素晴らしさはまた別のところで話すとして、今回伝えたいのは、読書を最大限に有効活用するためにはという点です。
私は昔はほとんど本を読まなかったのですが、転職を意識し始めてから少しずつ読書をするようになりました。
ただ、最初は本選びも適当だし、最初から最後までとりあえず通して読んで終わり、みたいな状況でした...
それすなわち、時間をかけて、身になることがないって感じです。
読書を始めたばかりの頃は、同じような読み方をしている人は意外と多いのではないかと思います。
でも、これだと読書のメリットを半分も活かせていません!
読書はできるだけ短時間で、自分の目的に合った知識を得ることに最大の価値があります。
そこで年間50冊くらいは読むようになって感じる、読書を最大限活かす方法を3つほど紹介したいと思います。

ポイントは3つあります。
① 何を学ぶか決める
② 全部読まない
③ まとめて人に話す
結局、読書が身になるのはそこに「自分の欲しい情報」があるときです。
知りたいことや、学びたいことについての情報があれば誰でも興味をもって接することができます。
実は、読書から知識を得るには「関心」が1番重要です。
そのためには、何を学ぶか決めて読書を始めることが効率的な読書の第一歩になります。
そして、本は全部読む必要はありません。
なぜなら、1冊の本には必ず"自分が欲しい情報以外の情報"が入っているからです。
1回の読書で身になる情報は全体の1~2割ほどです。
そうであれば、本の全ての読む必要はなくて、学びたいテーマに合った箇所だけ読んだ方が効率的になるでしょう。
そして、せっかく学んだことは人に話したり、文章でまとめることで知識の定着率が高まります。
メモにまとめて人に話すことで、周りの人のためにも、自分のためにもなる最強の読書術が完成するのです。
【今日のポイント】
読書をするなら「本は全部読まない方がいい」
何を学ぶか決めて、必要な箇所だけ読んで、人に話すことで効率的な読書ができる。
4. 質問コーナー - 良い上司なんて存在するのか -
今週の質問コーナーはこちらです!

どこの会社でも、いい上司と悪い上司はいると思います。なので、正直なところ、上司ガチャは運の要素が大きい気がします。。
それと、"自分にとってのいい上司"となると、さらに狭き門のハードルが上がりますよね...
ですが、質問への回答としては「Yes」です。
まず言っておきたいのは、100%全て尊敬できる上司なんてのはこの世に存在しません。
なぜなら、上司と自分は違う人間だからです。
哲学的な話ではなく上司と自分とでは、価値観も、大切なものも何もかも違うはずです。
仕事のやり方はそういった個人の価値観に基づいて形成されていくので、100%尊敬できる、というケースはなかなかありません。
ですが、どんな上司には必ず学ぶべき点があります。(そう信じています)
自分よりも経験が豊富な部分は、きっと自分の将来にとって役に立つはずです。
なので、絶対に尊敬する上司に会うんだと思うことなく、その時に会った上司のから何を学べるかと考えて行動した方が、自分にとってプラスになるのではないでしょうか。
こんな感じで答えていくので、随時質問お待ちしています!
みんなからの匿名質問を募集中!
— masa|Next Career Lab. (@masa_cons) September 22, 2021
こんな質問に答えてるよ
● 転職あるある教えてください…
● 在職中に転職活動しようとすると…
● 行動力ってどうやったら身につき…
● 転職、または退職を決意した瞬間…#質問箱 #匿名質問募集中https://t.co/21kHFE9z8D
5. 今週のオススメ本 - お金2.0 -
今週紹介する本は、学生時代にメタップスを起業し、タイムバンクなどのサービスをリリースし、現在は株式会社スペースデータの代表として宇宙開発に関する投資と研究をする佐藤航洋著作の「お金2.0」です。
この本の個人的な面白ポイントは「お金がなくなる未来がくる?」ということについての考察です。
今の世界は「資本主義経済」を中心にまわっています。資本主義経済とは、それぞれの企業が利益を目的に企業活動を行う経済のことです。
経済というのは、簡単にいうと人間が生きていくためのあらゆる仕組みです。
資本主義経済では「お金」が共通の価値を持ちます。なので貨幣経済とも言われます。
そしてこの経済を支えているのはそれぞれの「国」です。日本でも政府が主導してお金を発行したりして経済活動をコントロールしています。
まとめると、私たちには生きていくには経済が必要で、今の世の中で一般的になっているのが資本主義経済。そこで価値を持つのが「お金」で、「国」が中心となって管理されている、ということになります。
さて、面白いのはここからです。
では、お金や経済の世界において最もインパクトのある現象、大きな変化の流れとは何でしょうか?
もちろん100年という単位で考えるのは難しいですが、これから10年という単位で考えれば、それは「分散化」です。
『第2章 テクノロジーが変えるお金のカタチ』より引用
本の中で「分散化」というワードが出てきます。
今世界ではテクノロジーの発達によって、あらゆるものの分散化がすすんでいます。
例えばブロックチェーンもその1つです。ブロックチェーンを活用することでトークンを発行し、それが現在のお金と同じく価値を持つようになりました。これがビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨の仕組みです。
これまで「お金」は国という中央管理者しか扱うことはできませんでしたが、ブロックチェーンによって企業でも通貨を発行して経済圏を作ることができるようになりました。
つまり、国から、企業や個人へと、経済をつくって管理する権利が分散化されたというわけです。
このような分散化が広がっていけば、今のお金のような「全員で共通の価値」を持つ必要がなくなります。
あるひとはビットコイン、あるひとはイーサリアムを所属する経済圏で使えばいいからです。
テクノロジーによって経済圏が分散化されて、トークンを活用した経済が回りだすと本当に「お金」がなくなる日が来るかもしれません...
個人的には面白そうだけど、どんな世界になってしまうのか不安もあるような気がします笑
とはいえ、確実に言えるのはお金だけが価値ではなくなることです。
例えばYoutubeの登録者数や、Twitterのフォロワー数などその人が持つ影響力がテクノロジーによって見えるようになりました。
本の中ではこれを「価値主義」と呼んでいます。
お金は価値を資本主義の中で使える形に変換したものに過ぎず、価値を媒介する1つの選択肢に過ぎません。
『第3章 価値主義とは何か?』より引用
価値主義の世界で重要なのは、お金ではなく、共感や感謝、興奮などの内面的な価値です。
就活生に役立つツイートをするツイッタラーや、何かに挑戦する動画を投稿するYoutuberなどはフォロワーという形で周りに与える価値が可視化されています。
この価値はいつでもお金に変換することができるという点で、お金よりも重要なものになっていくでしょう。
さて、お金の未来の形を予想して、今何を考えるべきなのかを知りたい人はぜひご一読を!
6. 雑談&コラム紹介 - 手軽にいい情報を掴む方法 -
最後は雑談のコーナー!
手軽にいい情報って掴みたいですよね(いきなり願望)
すいません、真面目に雑談します。
ビジネスマンの多くの人が、新聞を読んだり、ニュースサイトを読んだり、キュレーションサービスやメルマガを登録して日々情報収集に励んでいますよね。
情報収集は大事だと思うのですが、最近これに時間を使いすぎるのも良くないなと感じていて、どんな形が最適なのか悩んでいます...
dimeで「ビジネスパーソン10000人に聞いた最も重要視している情報収集手段」という記事を見かけました。
ベスト3の結果は以下のような感じです。
① 信頼している人からの情報
② WEB記事
③ 新聞
なんと1位は「信頼している人からの情報」となっています。
確かに、専門家や信頼できる情報筋からの情報は信頼度が高そうですよね。
そしていい感じに人脈がないと使えなそうな方法なので、ある意味特別な方法かもしれません。
やはり、本当にいい情報は限られたエリアの中で回っているということでしょうか...
とはいえ、一般人としては、2位のWEB記事(これはSmartNewsなんかのニュースアプリも含んでいるはず)、3位の新聞の中で自分に合ったものを見つけるのが正攻法ですかね。
みなさん、何かいい情報収集の方法があったらぜひコメントで教えてください!
7. 終わりに
今週もここまで読んでいただき、本当にありがとうございました!
さらに良い情報をお届けできるように、コメントなど頂けましたら次回作も気合が入ります。
Twitterでも少しずつ発信しているので、気軽にフォローお待ちしております!
NEXT CAREER LAB(ネクストキャリアーラボ)はじめます。
— masa|Next Career Lab. (@masa_cons) September 19, 2021
ニュースレター的なマガジンで、毎週日曜日18時に更新予定です!キャリアについて考える"きっかけ"を提供していきます。#NextCareerLab で記事が見れます。
詳細を知りたい方は⬇︎の記事からどうぞ。https://t.co/1dUJNsrEo5
今年もあと少し!
悔いのない1年になるように今週も良い1週間を過ごしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
