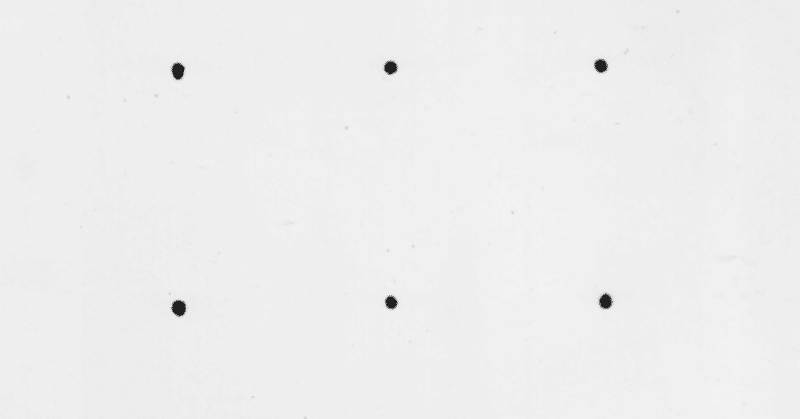
ジョン・ケージ論(4)
『4分33秒』以降
(前)
無心と融通無礙という立場は『4分33秒』以外の作品にも見られる。『カリヨンのための音楽第1番』(1952)は『易の音楽』における厳格な記譜法の反省として、音価を記さない曖昧な記譜法を採用した作品である。カリヨンという楽器の性質上、音の持続時間をコントロールできないため、楽譜には音高と打鍵のタイミングだけが記されている。カリヨンには統一された規格もなく楽器ごとの差異が大きいため、また重量のある鐘をワイヤーで鍵盤に繋いでおり、演奏者が打鍵する際の力加減によって音の強度が変わるため、音の持続時間は演奏ごとに異なったものとなり、それゆえこの作品では音の持続に関して自由な記譜法が取られたのである。また『ピアノのための音楽』(1952-56)でも曖昧な記譜法が採用されている。この作品は四つの小品(No. 1, 2, 3, 20)と、各16曲ずつの五つのグループ(No. 4-19, 21-36, 37-52, 53-68, 69-84)からなっている。この作品でケージは楽譜の各ページにいくつの音を書き込むかを易経で決定し、その音数だけ、紙の汚れや傷を目安に音符を書き込むという作業を行っている。この「紙の偶有性」とも言うべき方法は、「厖大な時間と極度の厳密さが必要」になる易経を使用した音の決定を簡素化し、短時間で作曲することを可能にするために取られた手段であった*1。そしてこの『ピアノのための音楽』シリーズは、1グループ16曲を単独で演奏しても、数人のピアニストによる同時演奏で複数の曲を重ねてもよいとされ、作品全体に不確定性が付与されている。このような作品の重複可能性は融通無礙の立場から各々の作品が相互に浸透することを狙った指示であろう。
この重複可能性は、時間の長さをタイトルに冠した作品群にも当てはまる。ピアニストのための『34分46.776秒』、『31分57.9864秒』(共に1954)や、弦楽器奏者のための『26分1.1499秒』(1955)、そして打楽器奏者のための『27分10.554秒』(1956)の4曲は、いかなる組み合わせで演奏されてもよく、また『一人の話し手のための45分』(1954)の講演と同時に演奏してもよい。
しかしこれらの作品は『ピアノのための音楽』シリーズとは異なり非常に厳格な記譜法で作曲されている。ピアニストのための『34分46.776秒』と『31分57.9864秒』では、鍵盤上で多くの音を弾きつつ内部奏法を行ない、それと同時にプリパレイションを変更したりホイッスルなどのアクセサリー楽器を演奏したりすることが要求される。ドナウエッシンゲンでの初演時には、実験的なパフォーマンス作品として受け取られ、ピエール・ブーレーズやカールハインツ・シュトックハウゼンらに影響を与えた。また弦楽器奏者のための『26分1.1499秒』では、ヴィブラートをかける位置、弓の圧力、ピッチカートの種類や弓のどの部分を使って弾くか等、さまざまな要素が詳細に確定されており、あわせてアクセサリー楽器の演奏も要求される。一方で打楽器奏者のための『27分10.554秒』では、記譜は簡略化されており、四つのパート――金属打楽器、木質打楽器、膜質打楽器、その他(ラジオ、笛など)――それぞれの音を出すタイミングと強度のみが示されている。しかし楽器そのものについての指定は一切なく、演奏者が自ら選択しなければならない。また音現象の密度も非常に高く、多くの音が書き込まれているため、演奏に当たっては高度な技術が必要とされる。
これらの作品における厳格な指示は『易の音楽』に共通する「非人間的」な性格を思わせるが、実際には「楽譜に書かれていることはどのような焦点の当て方をされてもかまわない」という注意書きがあり、さまざまに指定された要素すべてを取り上げてもよいし、一部でもよいとされている。これらの作品の楽譜は正確な再現を求めるものではなく、演奏者に対して演奏行為の材料を提供するにとどまる。
これらの作品以降、ケージは個別の楽器のための連作ではなく、多くの楽器が相互に関係性をもたずに纏まっているような作品を書くようになる。そのひとつが独奏ピアノと十三の楽器を用いた『ピアノとオーケストラのためのコンサート』(1957-58)である。この作品は各楽器が相互に無関係であるため、パート譜のみで構成され総譜が存在しない。また各演奏者は自分のパート譜を他のいかなる楽曲と組み合わせて演奏してもかまわない。そのため音響的に混沌とした状態も、『4分33秒』と同じ状況も発生しうることになる。パート譜もさまざまな図形譜で書かれており、特殊奏法も要求される。
これらの作品の内部にはケージの意志はなく、作曲者はただ聴覚的な体験の機会をつくる提案者としてのみ機能することになる。それに伴って、演奏者と聴衆、そして作品の関係も変化することになる。それぞれが中心にあり、相互に浸透しあって主客二元論を超えた事態を受容することだけがここでは問題となる。
1960年代になるとケージの作曲活動はそれ以前と比べて活発ではなくなるが、聴覚的な体験の機会を提供するという作曲のありかたを示す作品が作られている。八十六の楽器のためのソロの集合として書かれた『アトラス・エクリプティカリス』(1961-1962)においては、すべてのパートがたったひとつの技法――星図表をなぞって楽譜に音を書きこんでゆく――で作品がつくられている。演奏者は舞台上に整然と配置されるのではなく、観客席にも入りこんで一人ずつばらばらに演奏する。複数人の演奏者を個別の独奏者として扱うことで、演奏者それぞれの融通無礙なる状況がつくられることになる。『アトラス・エクリプティカリス』とともにひとつの作品群を形成する『ヴァリエーションズ第4番』(1963)と『0分00秒(4分33秒第2番)』(1962)においては、いかなる方法で音を出すのかということについてさえ、ケージは指示を行なわなくなる。『0分00秒』は、音が増幅される状況で、音楽的な修練を伴わない動作を一度もしくは幾度か行なうという作品であり(初演時にはそのことを記した指示書がケージによって舞台上で書かれた)、『ヴァリエーションズ第4番』では作品が演奏される空間についての指示しか与えられていない。またレジャレン・ヒラーとの合作、『HPSCHD』(1969)は、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、シューマン、ゴットシャルク、ブゾーニ、シェーンベルクの作品と、ケージ、ヒラーの自作の楽曲をハープシコードで演奏し録音したものをコンピュータ加工したテープを作成し、公園などの外部空間で行なわれる七台のハープシコードの演奏と同時に52チャンネルのスピーカーからテープ音楽を流すという作品である。この作品は、作品内部で起こる音現象は確定的であるものの、聴取によって可変的な性格を帯びることになる。というのは、作品内部の音が提示される空間が広範囲に亘るため、どこで聴くのか――聴取者の位置が聴覚上の音現象を変えてしまうからである。そのため全体の把握が不可能であり、かつまたさまざまな環境音が聞こえうるため、『HPSCHD』は聴取に際して不確定な作品であると言えるであろう。
*1 Cage, Charles, 青山訳, ibid., p. 20.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
